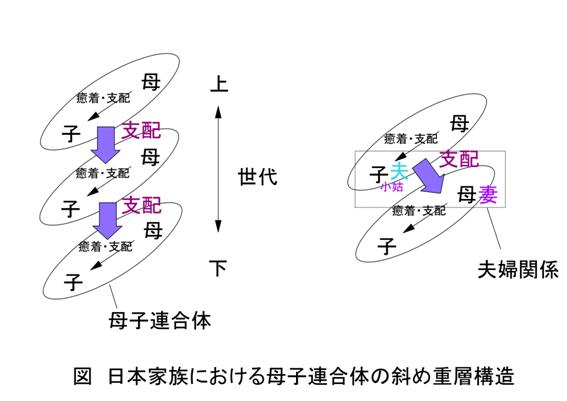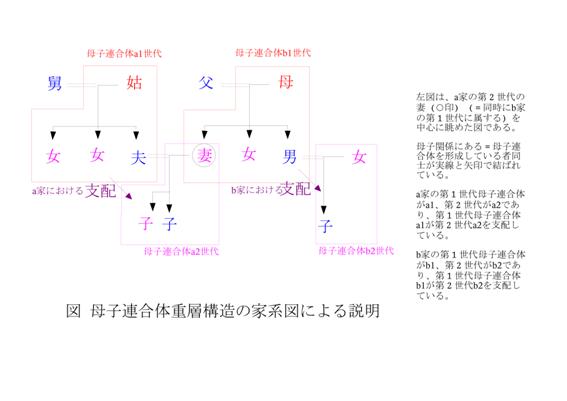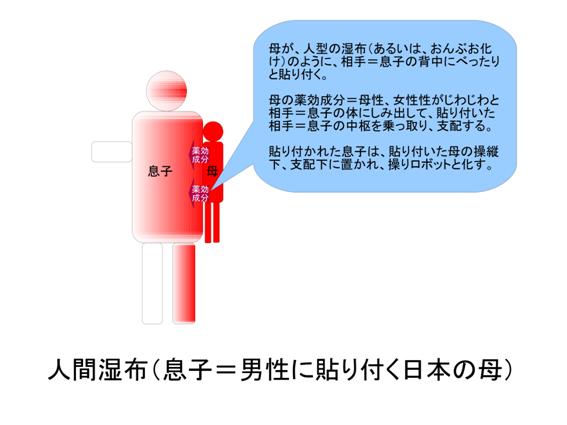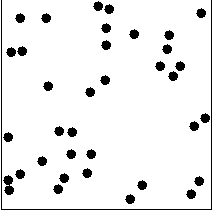
母権社会日本
ー支配者としての母、姑ー
第8版
本書では、日本社会において男女の性差がどのような影響をもたらしているか、従来の日本の女性学や日本のフェミニズムに再考を促す形で考察しています。
例えば、従来の日本女性学・日本フェミニズムの通説では、「日本社会は、男性中心、家父長制社会である」「女性は男性に比べ、世界どこでも普遍的に、弱い劣位の解放されるべき存在である」とされてきました。
本書では、こうした通説に疑問を抱いた筆者が、日本社会を調査したり、分析したりした結果をもとに、「ウェットな、液体的な日本社会は女性の方が強い、母性中心で動いている母権社会である」「日本男性こそが、女性、母性による支配から解放されるべき存在だ」などの主張を展開しています。
そうすることで、欧米フェミニズム思想を機械的に直輸入し、何も考えずに強引に日本社会にそのまま当てはめているだけの、現状の日本女性学・男性学、フェミニズムのあり方を批判しています。欧米理論の機械的直輸入ですっかり誤った方向に向かってしまった日本の女性学、フェミニズム、そして男性学が、本来どういう方向に向かうべきなのか、指針としてまとめ、提言しています。
本書では、日本社会における真の男女平等実現のために、日本男性の母性からの解放と父性の強化を提言しています。日本の男女の力関係を50:50に対等化するための施策について幅広く提案しています。
文中、各セクションは、それぞれ独立した読み物、エッセイとなっており、どこからでも読み始めることができます。
本シリーズの著作の目的は、以下のように説明される。
(1) 欧米で定説になっているBachofen, EngelsらのMatriarchy理論(従来、母権制論と訳されてきた)を打破するのが目的である。母親が権力を握る社会は消滅したとするこの定説をひっくり返し、母権社会は、今でも世界中の稲作農耕民族の間に広く存在し、一大勢力であると主張する。あるいは、Matriarchyの概念が、日本のような母権社会の正しい把握にとって不適切な概念であり、無くすべきと主張する。Matriarchyを母権制と訳すことを止めさせる。
(2)現状の日本フェミニズムを打破する。すなわち、日本のフェミニズムが、本来、西欧のような父性社会向きの社会理論を直輸入して、機械的に、母親が強い日本社会に強引に当てはめる過ちを犯していると主張し、その是正を求める。日本のフェミニズム、女性学、男性学が本来どういう方向に向かうべきなのか、指針としてまとめ、提言する。
(3)日本社会の最終支配者が母であること、女性であることを明示する。日本社会の女性、母性による支配を打破する。妻、母や姑からの男性解放を主張する。日本における母性からの父性の解放を目指し、日本社会における父性を強化して、湿った日本社会のドライ化を目指す。日本社会における男女のパワーバランスを50:50へと平等化、対等化することを主張する。
日本社会の正しい解明と認識を得ることが、本シリーズの著作の目的である。
(初出2012年1月)
〔1.はじめに〕
現代日本のフェミニズムは、欧米社会で唱えられた女性解放論を、そのまま日本に直輸入して、男尊女卑など、女性が差別されているように見える現象に当てはめて考えようとしている。結果として、「日本は男性中心社会である」「日本の家族は家父長制である」といった解釈を行っている。女性の地位は、男性に比べて、全世界どこでも普遍的に低い(女性は、普遍的に男性より弱い)ものであると見なし、声高に、「低い」女性の地位を向上させようとしている。
ところが、一方では、「日本は母性原理で動く社会である」「日本の国民性は女性的である」といったように、日本の社会が持つ女性的性格を示唆する言説も、(そのほとんどは、一言印象を述べただけのものであるが)かなりの数見られるのも事実である。以下に、その例をいくつかあげる。
日本社会の女性的性格については、
例えば、〔芳賀綏1979〕では、日本人像のアウトラインを、「《おだやかで、キメこまかく、ウェットで、『女性的(強調筆者)』で、内気な》ややスケールの小さい人間たちの集団」と述べている。
あるいは、〔会田雄次1979〕では、「日本社会の伝統的な特徴を一口でいえば昔から『女流(強調筆者)』の国だったということに尽きよう....いつの世にも広く文化一般に女性が活躍している...日本文化はもとより社会そのものが、『女性的(強調筆者)』性格を強く帯びており、男性的な時代というのは、戦国時代と幕末から明治という外患と変革と動乱が重なった短い2期間しかなかった....この本来的に「女々しい」が平和な国は、男性的資質を帯びるのは外国から強い危機が感じられたときに限られる。その危機が克服されたり、去ってしまったりすると、またもとの女流の世界になる..」、と述べている。
または、〔木村尚三郎1974〕では、「日本人の能力は一般に『女性的(強調筆者)』能力であり、いわゆる「学校での頭の良さ」がある..欧米の学問、科学と技術、芸術をみごとに習得はするが、新しい境地をひらく、学者、思想家、芸術家となると、国際的にまことに数少ない...日本人の心的態度はおそらく秩序形成的、『女性的(強調筆者)』、あるいは伝統的、農業的であるといえよう..」と述べている。
〔佐々木孝次 1985〕では、「女性にとって日本ほど気楽で居やすい社会というのは、他にないと思います。女性が精神的な意味で、すっかりこの社会を支配していますし、別に女性が支配しようと一所懸命になっているわけでなく、男のほうが、自分の幼児性を乗り越えられないで、どこにでもお母さんを作ってしまうからなのです。…男性が無差別に母親を求めるという状態からなんとか自分を解放しないと、一方で女性がウーマン・リブをとなえても、笑い話になってしまう。」と述べている。
〔Ben‐Ami Shillony 2003〕では、日本の天皇制が、女性的性格を持っていると指摘している。
日本社会を母性社会、母権社会と見なす考えについては、
〔河合隼雄1976〕では、「母性原理は、「包含する」機能で示され、すべてのものを絶対的な平等性をもって包み込む。それは、母子一体というのが根本原理である。...日本社会は、『母性原理(強調筆者)』を基礎に持った「永遠の少年」型社会といえる。」と述べている。
〔山下悦子 1988〕では、「家父長的「いえ」制度といわれるものが、・・・「いえ」の王たる家父長が超越的に君臨する西欧的な家父長制と違って、日本の場合は家父長たる息子の母親が実質的な力を持つ」と述べている。
〔山村賢明 1971〕では、日本の女性の地位について、「妻=嫁と母=主婦の間には同一にあつかえない差異があることがわかる。前者の地位においては、たしかに低かったかもしれないが、後者の地位においては決してそうではなかったのではなかろうか。かねて筆者は、日本の母はそうとうな高い地位とそれに伴う重要な役割をもっていたはずだ…」と述べている。
〔Kenrick 1991〕では、日本の妻が、家庭で家計管理の権限を握り、夫に対して小遣いを渡すさまを、母権制ではないかと指摘している。
〔Ederer 1991〕では、教育ママゴン等の実例を元に、日本において家庭の中心にいるのは女性であり、日本の社会を母親の権力に基づいたものとして捉えている。日本の母親が教育者であり、夫と子供を業績と出世に駆り立てていると指摘している。
日本社会は、男性・女性、どちらのペースで動いているのであろうか?あるいは、日本においては、実質的には、男女どちらが勢力・地位として上なのであろうか?以下においては、この疑問について、対人感覚のドライ・ウェットさをキーとして、解明を試みている。
〔2.行動のドライ・ウェットさと性別・社会のタイプ〕
この項では、行動様式のドライ・ウェットさと、性別・社会・自然環境のあり方との関係について述べる。
行動様式のドライ・ウェットさ(個人の取る行動が、周囲の人にドライ・ウェットな感覚を与えるのはどのような場合か、についての分類)は、筆者の調査によれば、個人主義-集団主義、自由主義-規制主義...など、10数項目からなっている。これらの項目を全て合わせると、人間の様々な行動様式を、一通り説明するに足る、十分包括的・網羅的な内容を持っている。このことから、人間の多様な行動様式を、「ドライ」ないし「ウェット」の一言で総括する(ひとまとめにして考える)ことが、可能である。
筆者は今回、
(1)対人感覚(人がその行動・振る舞いによって、他者に与える感覚)のドライ・ウェットさ
(2)自然環境の乾湿(ドライ・ウェット)に対応する社会のあり方(遊牧・農耕)のドライ・ウェットさ
(3)人間の性別(男女)と、取る行動のドライ・ウェットさの面からの性差
について、相互の関連性を検証した。
その結果、これら(1)~(3)の間の相関関係を取ると、
|
対人感覚 |
自然環境 |
社会のあり方 |
当てはまる性 |
|
ウェット |
湿潤(ウェット) |
農耕 |
女性 |
|
ドライ |
乾燥(ドライ) |
遊牧 |
男性 |
という関係が成り立つことを確認した。
詳細は、本書の資料文書編を参照されたい。
調査した結果、行動様式のドライ・ウェットさの次元で、行動様式の男女性差に関する学説の大半をカバーできていることが分かった。
この中から、社会のあり方と、性別との関係を取り出して見ると、
農耕=女性
遊牧=男性
という結びつきが成り立つ。
この結びつきについては、
(1)文化人類学の分野では、例えば、[石田英一郎1956][石田英一郎1967]において、
竜蛇の形をとった水神が、農耕の神として崇められ、同時にまた原初の女神として人類の始祖となるというのが、大地母神の基本的性格である。植物の採取、ひいてはその栽培に人間の生活が依存するとき、そうした営みの担当者として女性の地位が中心的である。農耕的=母権的な文化基盤を持つといえる。
馬をめぐるもろもろの文化要素は、内陸草原地帯に由来する、遊牧的、父権的、合理的、上天信仰的な文化の系統に属する。(以上、筆者による要約。)
といった説明がなされている。
石田の説明から判断すると、自然環境と宗教との関連は、
遊牧= 天空の父なる神(男性神)= 天空を指向する
農耕= 大地の女神(女性神)= 大地を指向する
という関係が成り立ち、農耕=女性(=ウェット)、遊牧=男性(=ドライ)の、相互結合を支持する結果が出ている。
石田は、農耕=母権的、遊牧=父権的という図式も、同時に提示している。これは、いいかえれば、農耕社会では、女性(母親)が支配し、遊牧社会では、男性(父親)が支配する、ということになる。
(2)地理学の分野では、例えば、[千葉徳爾 1978]で、
「農耕は、定着して、作物成熟の遅々とした進行を待つ。緻密で倦むことのない繰り返しを必要とするが、女性は、体質・体格ともに男性よりはるかに適している。女性が農耕を主宰することで、作物により高い生産力を期待できる。農耕社会は、女性優位である。農耕のもととなる採集文化は、女から進化した。」
「牧畜社会では、軍事行動の必要と、家畜管理上の要求から、体力的に優位にある男子青壮年が重視され、老人と女性・子供の地位が低い。家庭では夫の権力は妻より高い。」(以上、筆者による要約)
といった説明がなされている。
これらの関係が本当に成り立っているかどうかを、性格・態度のドライ・ウェットさを調べるアンケート調査(1999.5~7)で確認したところ、以下のように、予想通り当たっていることが分かった。
詳しくは、著者の湿度感覚と気体、液体に関する著作を参照されたい。
|
番号 |
項目内容 |
-ドライ- |
どちらで |
-ドライ- |
項目内容 |
-Z得点- |
有意 |
|
C12 |
男性的である |
46.154 |
24.434 |
29.412 |
考え方が女性的である |
2.863 |
0.01 |
|
A11 |
一ヵ所に定着せずあちこち動き回る |
50.450 |
20.721 |
28.829 |
一ヵ所に定着して動かない |
3.618 |
0.01 |
|
B10 |
遊牧生活を好む |
62.727 |
20.909 |
16.364 |
農耕生活を好む |
7.733 |
0.01 |
|
C33 |
天空を指向する |
45.249 |
23.982 |
30.769 |
考え方が大地を指向する |
2.469 |
0.01 |
結局、アンケート結果では、
(1)女性=ウェット=農耕、男性=ドライ=遊牧という結びつきがある。
(2)ドライ/ウェット性格・態度の内容は、社会的性格を捉えるに十分に網羅的である。
ということが確認された。このことから、
(a)農耕社会では、女性が社会運営の主導権を握る、ないし、社会を動かす最も基盤の位置を占有する、社会の根本部分を支配する。その理由は、社会が女性向き(女性的)にできていないと、農耕型の社会を要求する自然条件に適合して行けないからである。言い換えれば、社会が女性のペースで動くことになる。その点、女性の方が、実質的な地位・勢力が上である。
(b)遊牧社会では、男性が社会運営の主導権を握る。その理由は、社会が男性向け(男性的)にできていないと、遊牧的社会体制を要求する自然条件に適合して行けないからである。社会は、男性のペースで動き、男性の方が、実質的な地位・勢力が上である。
以上まとめると、
農耕社会 女性向き(女性が支配する)=母権制
遊牧社会 男性向き(男性が支配する)=父権制
ということになる。
社会において、生活様式が農耕が支配的になり、農耕民が強くなると、社会における女性、母の地位が向上し、男性、父の地位が低下する。一方、生活様式が遊牧、牧畜が支配的になり、遊牧、牧畜民が強くなると、社会における男性、父の地位が向上し、女性、母の地位が低下する。
(2008年5月 追記)父権制・母権制と気体(ガス)・液体(リキッド)タイプ
上記の対人感覚のドライ、ウェットさは、物理的な気体(ガス)、液体(リキッド)と関係がある。
詳しくは、筆者の湿度感覚と気体、液体に関する著作を参照されたい。
気体タイプ、液体タイプの行動様式を表した動画を以下に示す。
気体タイプ(気体分子運動パターン) 説明動画
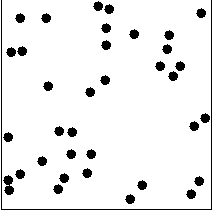
液体タイプ(液体分子運動パターン) 説明動画
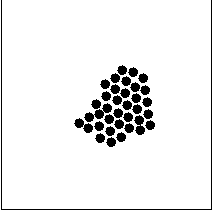
※ご注意
上記シミュレーション動画の原作者および著作権保有者は、池内満さんです。
池内さんのwebサイト http://mike1336.web.fc2.com/
この気体、液体タイプの分類から、農耕社会と女性の支配(母権制)、遊牧社会と男性の支配(父権制)との関係を見ることが可能である。
アメリカは、遊牧社会タイプに属し、日本は、農耕社会タイプに属する。
アンケート調査を行った結果、
アメリカ的パーソナリティと気体分子運動、日本的パーソナリティと液体分子運動が相関することが分かった。
また、男性的パーソナリティと気体分子運動、女性的パーソナリティと液体分子運動が相関することが分かった。
詳細は、本書の資料文書編を参照されたい。
このことより、
アメリカ的=遊牧社会=気体的(ガスタイプ)=男性優位=父権制
日本的=農耕社会=液体的(リキッドタイプ)=女性優位=母権制
という関係が成り立つと言える。
〔3.日本社会の女性的性格〕
日本社会は、自然環境のドライ・ウェットさの分類から行くと、「湿潤気候=農耕社会=ウェット」という相関により、ウェットな社会であると、当然ながら、予想される。
筆者は、日本人の国民性が、どの程度ウェット/ドライかについて、文献調査を行った。
その結果は、本書の資料文書編にまとめられている。
上記の調査結果からは、「伝統日本的」=ウェット、という結果が出た。
また、筆者が抽出した、「ウェット」な行動様式は、「ウェット」という一言で、日本人の国民性(行動様式)に関する学説の大半を、カバーできていることが分かった。
一方、「女性的」=ウェットである。
行動様式の「ウェットさ」への当てはまりの有無について、日本人の国民性(行動様式)と、女性的性格(行動様式)との間の関係を、文献調査結果をもとに、洗い出してみたところ、両者(日本人-女性)の間に正の相関があることを確認した。
したがって、ドライ/ウェットの次元からは、日本的=女性的という図式が成り立ち、日本は女性が支配する(優位に立つ)社会である、ということになる。
その理由付けは、
(1a)日本の国民性が、ウェットである。農耕(特に稲作)社会だから、当然である。
(1b)女性の性格が、ウェットである。
(2)ウェットな性格の内容は、十分に網羅的である(伝統的日本人の国民性についての学説、および男女の性差に関する学説の大半をカバーしている)。
(3)日本の国民性は、(ウェットさを相関軸として考えた場合、)女性的である。
ドライ-ウェット以外の次元でも、日本の国民性は、女性的である。すなわち、安全指向、成功例の後追い(失敗を恐れ回避する)、冒険心の欠如、大組織への依存心の強さ(寄らば大樹の陰)、などが女性的であることを示す例である。
女性的(女らしさを示す)行動様式についてのより詳しい説明は、筆者による、女らしさの生物学的貴重性の視点からの検討を行った文書を参照されたい。
なぜ、日本の国民性が女性化したかについては、次のように説明することができる。日本は稲作農耕を基盤にした社会であり、そこでは、土地への定着性や水利面での他者との相互依存など、行動様式としてウェットさが求められてきた。ウェットな行動様式を生み出す原動力は女性にあり(男性にはない)、稲作農耕に適応するための社会のウェット化には、女性の社会全般への影響力が欠かせない。社会のウェット化に女性の力を利用する副作用として、社会における本来ウェットさとは無関係の領域(自分の取った行動に責任を取るか否か、取る行動の安全性に敏感かどうかなど、生物学的貴重さとは関係があるが、ウェットさとは関係がない領域)にまで、女性の勢力が及び、その結果、男性の行動様式の女性化を含めて、日本社会全体が女性的(自分の保身のため、自分の取った行動の責任を周囲の他者に取ってもらおうとする無責任体制、安全さが確認されたことしかしようとしない冒険心の欠如など)となった。
社会において、女性の勢力が男性を上回るから、国民性が女性的となるのであり、国民性がウェットなことは、日本社会において、女性が男性より強いことの証拠である。
日本社会が、男性中心社会というのは誤りである。実は、日本社会は、女性を中心に回っている。言い換えれば、日本社会の仕組みは女性向けにできており、男性には不向きである。
日本において、なぜ女性が強いか?まとめると、農耕(稲作)という,ウェットさ(定着性や対人関係面での相互依存など)を求める、したがって女性的な行動様式を求める、自然環境に囲まれた社会だからである。
〔4.母権制の再発見〕
日本は、従来の通説と異なり、実際には、女性の勢力が男性のそれを上回る、女性優位=母権制の社会である。日本を含む東アジアの稲作農耕社会は、対人関係にウェットさを必要とする自然環境であり、その下では、生得的によりウェットな女性が、有利であり、実際に家計管理権限などを掌握しているからである。
母権制は存在しないと言えるか? 結論から言えば、存在しないとは、とても言えない=「明らかに存在する」。農耕社会は、基本的には母権制である。
母権制の存在が、これまで認められなかった理由を、以下に、着眼点毎にまとめた。
1)「姓名」の付け方
母系制と混同した。男女どちらの姓が、子孫に継承されていくかについて、関心を払い過ぎた。姓が継承される方の性を強いと見なしたため、父親の姓が継承されることがほとんどだったことを、父親の強さと勘違いし、父権制があたかも全世界的な標準であることのように勘違いした。姓は、血縁関係を示す「看板」=外に向けて掲げるものの役を果たす、いわば、「表」の世界のものである。男性の方が、表面に出やすい=外に露出しやすいため、男性の方を付けるのが適当とされたと考えられる。これは、父権制とは、直接には、無関係であると思われる。
2)「財産」の所有・管理のあり方
2a)家庭における財産の所有・相続者の性が男女どちらかであるかに、関心を払い過ぎた。財産の名目的に所有する者と、実際に管理する者とが同一でない=分離している場合があることに気づかなかった。名目的所有者が男女どちらかという方にのみ注意が行って、管理者が男女どちらかということに関心が足りない。ドライな遊牧社会では、両者は、男性ということで一致するが、農耕社会では、前者は男性のこともあるが、後者はたいてい女性である。
2b)財産を単に名目的に所有している者よりも、財産の出入り(財政)の実質的な管理権を握る方が、実質的な地位が上である、ということに気づかなかった。財産管理者(家計の財布を握る者)は、遊牧社会では、男性であるが、農耕社会では、女性である。これは、農耕社会の家庭では、女性の地位の方が実質的に上であることを示している。
3)「地域」毎の事情
3a)欧米では、自分の「家父長制」的な文化基準からは、母親がより強い文化があることを想像できなかった。父権制をデフォルトとみなし、「母権制は、遠い過去に消滅した」とする、欧米の学説(Bachofen、Engels)が主流となってしまったため、全世界的に、母権制の存在自体が考えられないものとされてしまった。
3b)日本など東アジアでは、男尊女卑を、男性支配(家父長制)と混同した。あるいは、自分たちより先進的な欧米学説が母権制の存在を否定したため、それを権威主義的に無批判に受け入れてしまい、本当は自分たちが母権制文化を持つことに気づかなかった。
4)「自然環境」との関連
男女間での自然環境への適応度の違い、という視点が欠如していた。湿潤環境下で成立する農耕社会のように、「ウェットな人間関係が必要→女性がより適応的=強い」という場合を、想定していなかった。
5)「公的組織上の地位」との関連
女性は、生物学的により貴重な性であるため、失敗を犯したことで責任を取らされて、社会の中で公然と生きていけなくなったり、助けてもらえなくなること、すなわち自己の保身ができなくなることを恐れる。公的組織(官庁、企業)において高い地位につくことは、社会的に大きな責任を伴うため、失敗時のリスクが非常に高いため、女性は、組織上の高い地位につくのを進んで避けようとする。その結果、組織上の高い地位は、男性が占めることになる。女性は組織上の高い地位に能力不足などで「つくことができない」のではなく、自己保身の都合上「自ら進んでつこうとしない、つかない、つくのを避ける」。したがって、従来のように、日本において、官庁、企業といった公的組織の高い地位につく人々の男女比率を見て、女性の数が少ないから、女性が弱い、と簡単に言い切ることはできない。女性は例え社会的影響力が強くても、公的組織上の高い地位を、自らの社会的責任回避、リスク回避を目的として、男性に押しつけている側面があるからである。
日本女性による男性支配は、主に、母=息子関係を通じて行われる。日本の女性(母親)は、育児の過程で自分の子供との間に強い一体感を醸成し、自分の息子=男性が自分に対して精神的に依存する、自分の言うがままに動くように仕向けることで、息子である男性に対して強い影響力を保持する。女性は、「教育ママ」として息子=男性を社会的に高い地位につくように叱咤激励し、高い地位についた息子=男性を、自分の操り人形、ロボットとして、思うがままに操縦、管理する。これなら、自分自身は社会的責任を負う必要なく、男性=息子をダシにして強大な社会的影響力を行使できる。妻と夫の関係も、妻=女性が、夫=男性を心理的に母親代わりに自分のもとへと依存させ、夫を高い地位へつくように競争に向かわせたり、高い地位についた夫=男性の管理者として支配力を振るう点、上記の母と息子の関係に根本的に似ている。そうした点、日本の女性は、男性の生活や意識を管理、支配する=男性を自分の思うがままに動く「ロボット」化する者として、社会的地位の高い男性よりも、さらに一段高い地位についていると言え、なおかつ、社会的責任を取ることからはうまく逃れている。男性は、公的組織で例えどんなに高い地位についていても、女性に対して心理的に依存し、管理されている限り、女性に支配されていることになる。
なお、日本の公的組織(官庁、企業の職場)が男性中心であって、そこへの女性の進出が進まないのは、女性の高い地位につくことを避ける性向以外にも理由がある。それは、そこが、男性の自尊心を保持できる(家族を経済的に支えているのは私をおいて他にいない、との誇りを保てる)最後のとりでであって、そこに女性が進出してくるのを脅威に感じているからだと考えられる。男性側は、女性には、公的組織における自分の居場所を簡単に明け渡したくない。明け渡すと、せっかく保って来た見かけ上の高い地位からも一挙に転落し、最後の自尊心が消えてしまう。後は(見かけ・実質両面で男性を圧倒する)女性のペースに合わせてひたすら従うだけの社会的落伍者に成り果てるからである。
6)「力の強弱」の見せ方との関連
6a)女性は、自分のことを、自ら進んで強いと、言わない(生物学的により貴重な性であるため、男性に守ってもらおうとして、自らを弱く見せる)傾向がある。また、強いことを認めると、取る行動に社会的責任が生じてしまう。そこで、取った行動の失敗時に責任を取らなくて済むようにするために、自分のことを(例え実際は強者の立場に立っているとしても)決して強いと認めず、弱いふりをする必要がある。そのため、自分が権力を握る強者であることを示す「母権制」という言葉を使うのを、好まない。その結果、母権制が存在しないかのように、考えられてしまった。
6b)男性は、自分のことを、進んで強く見せようとする傾向がある。強く見せることで、自分が自立した存在である(1人でいても、他に守ってくれる人がいなくても、十分大丈夫である、やっていける。あるいは、他者を自分の配下において、統率できる。)こと、ないし、女性を守る能力があること、を周囲にアピールしたがる。そこで、必要以上に、父の権力を強調しがちであった。その結果、父権制が一人歩きすることになってしまった。
7)「男尊女卑」現象についての解釈の仕方との関連
ある人のことを、他者よりも優先する場合には、「強者優先」と「弱者優先」との相反する2通りが存在する。「男尊女卑」は、男性的なドライさを否定する農耕社会において、男性を社会的弱者として保護し、その人権・自尊心を保持するための、「弱者優先」の考え方である、と見なすのが正しい。これを、男性を強者と見なす「強者優先」と取り違えた。この点についての詳細は、男尊女卑の本質とは何かについてまとめたページを参照されたい。
注)男女間での力の強弱を説明しようとするモデルには、
1)筋力・武力モデル(男性優位) 男の方が、筋力が強い。
2)生命力モデル(女性優位) 女性の方が、長生きである。
3)貴重性モデル(女性優位) 女性の方が、貴重であり、大切にされる。
4)環境適応モデル 乾燥=遊牧=(ドライ=)男性優位、湿潤=農耕=(ウェット=)女性優位。
5)育児担当者モデル(遊牧=男性優位、農耕=女性優位) 社会における男女の強弱は、自分の性に基づく行動様式を、子供にどれだけ多く吹き込めるかによって決まる。例えば女性が子供に、(男性よりも)より多く自分の行動様式を吹き込めば、社会は女性化し、女性にとってより居心地のよいものとなる。
が考えられる。従来は、1ばかりが取り上げられ、3~5などは、ほとんど考慮されてこなかった。そのため、父権制=男性優位が全世界的に通用するかの様に捉えられるという過失を招いた。3~5を考慮すれば、母権制=女性優位という考えも十分成り立つことが分かる。
なお、5)育児は、女性(母性)の占有物とは、世界的には必ずしも言えない。Floidの精神分析論やParsonsの家族社会論に見られるように、欧米(遊牧系)社会では、育児への父親の介入(割り込み)の度合いが強く、父親が育児のdirectorの役割をしている。日本のような農耕社会では、女性が育児のdirectorである。
なぜ女性は弱く見えるか?あるいは、自分を弱く見せるか?
1)「筋力」モデル 筋力が男性よりも弱い。
2)「守護」モデル 男性よりも、生物学的に貴重であるために、(より貴重でない、使い捨ての性である)男性に守ってもらいたがる(守ってもらおうとする)。その守ってもらおうとする行動が、弱者が強者に守ってもらいたがるのと混同された。
〔5.終わりに〕
以上述べたことをまとめると、女性の社会的な強さ(影響力、勢力の大きさ)、社会的地位の高さは、その社会のかもしだす雰囲気(国民性、社会的性格)が女性的、ウェットであるかどうかで決めるのが本筋である(最も確実である)、と筆者は考えている。ある社会の国民性は、その社会において最も大きな影響力、勢力を持つ者の色に染まる、一種のリトマス試験紙のようなものである。社会で女性がより強ければ、その社会の帯びる性格は女性的になるであろう。要するに、国民性は、その国においてメジャーで強大な社会的勢力の色に染まるということであり、日本の国民性が女性的であるということは、日本社会において女性が支配的な力を振るっていることと関係していると考えられる。
従来のように、名目的な財産名義を持っていない、公的組織における高い地位についていない、などといった視点だけで、日本女性の地位を低いと決めつけることは、実は、社会のあり方と性差との関係を表面的にしか見ることができない、社会分析能力の低さをさらけ出していることに他ならない。日本社会は、伝統的な国民性としては、ウェット、液体的=女性的であり、それはとりもなおさず、女性の勢力が男性のそれを大きく上回っている、社会において女性が男性よりも強い、社会が女性のペースで動いていることを示している。
従来の日本の女性学、フェミニズムは、性差心理学、すなわち男性女性の社会的性格と、日本人の国民性、すなわち日本の社会的性格との照合を怠っていたため、女性的性格と日本人の社会的性格との相関に気づくことが出来ず、日本社会を男性優位と見なす誤った結論にはまったと考えられる。
今後、日本における女性の地位の高さを正当に評価する人々の数が少しでも増えることが、筆者の望みである。
注)以上述べた理論が、現在の日本で受け入れられる余地は少ないと考えられる。その理由は、
1)男性→ 自分が優位であるという観念(優越感)が崩れて、不快に感じるため。自分を強者とおだててくれる、既存のフェミニズム理論へと向かう。
2)女性→ 自分の強さを認めようとしない(認めると、自分を守ってくれる男性がいなくなると考える。あるいは、認めると、自分が社会を支配している結果の責任を取らなくてはならなくなり、リスクが大きいと考える。)ため。弱いふりをしていたい。従来のフェミニズム・女性学の「男強女弱」という見解に固執する。
上記の日本母権社会論の主張は、自分たちの保身、安全確保をしようとする、あるいは、自分たちが日本社会を支配することへの責任逃れをしようとする日本女性たちの退路を断つ、要するにあなたたちが本当の支配者だ、支配責任を取れ、と断じることで、女性たちの心理的急所を突く行為に当たり、女性たちとしては、不愉快であり、無視したいと考えられる。
〔参考文献〕
会田雄次:リーダーの条件,新潮社,1979
芳賀綏:日本人の表現心理,中央公論社,1979
石田英一郎:桃太郎の母,法政大学出版局,1956
石田英一郎:東西抄,筑摩書房,1967
G.Ederer Das Leise Laecheln Des Siegers, Econ Verlag, 1991(増田靖 訳,勝者・日本の不思議な笑い-なぜ日本人はドイツ人よりうまくやるのか?, ダイヤモンド社, 1992)
河合隼雄:母性社会日本の病理, 中央公論社,1976
D. M. Kenrick, Where Communism Works: The Success of Competitive-Communism in Japan, Tuttle, 1991 (飯倉 健次 訳, なぜ“共産主義”が日本で成功したのか, 講談社, 1991)
木村尚三郎:ヨーロッパとの対話, 日本経済新聞社,1974
佐々木孝次:母親と日本人,文藝春秋,1985
Ben‐Ami Shillony, Enigma Of The Emperors: Sacred Subservience In Japanese History, Global Oriental, 2006 (大谷 堅志郎 訳, 母なる天皇―女性的君主制の過去・現在・未来,講談社,2003)
千葉徳爾:農耕社会と牧畜社会(山田英世編 風土論序説 国書刊行会) 1978
山村賢明:日本人と母,東洋館出版社,1971
山下悦子:日本女性解放思想の起源,海鳴社,1988
(初出1999年08月)
母権制論は、従来BachofenやEngelsらによる「母権制は過去のもので、地球社会全体が父権制に既に移行済みである」という主張がそのまま疑いを持たれずに受け入れられている。
しかし、この「母権制は既に消滅した過去の遺産に過ぎない」という主張は、日本や東南アジアのような稲作農耕社会における、人々の国民性や、社会風土が母性優位であることを知らずに、相対的に父性優位のヨーロッパや中東付近の知見だけでなされたものである。
Bachofenらは、母性優位な、稲作農耕民の心理に無知だったし、調査範囲を東南アジアまで広げて考えることも怠ったまま、自分たちの社会が父権優位であることを正当化することを暗黙の目的として、「母権制は過去の遺物」という結論に達したのである。
Bachofenらヨーロッパの人は、遊牧、牧畜系の人たちであり、父権優位の彼ら遊牧、牧畜民にとって、「母権社会が父権社会に敗北し、消滅した」というのは、彼ら自分たちにとってはごく自然な結論であると言える。
しかし、その遊牧、牧畜民向け結論を、スコープの違う今なお母性優位の東アジアの稲作農耕民の社会にまで、適用可能かどうかを確認しないまま普遍化して持ち込もうとするのは、明らかな越権行為であり、間違いであると言える。
西欧の母権制論者の、母権制は過去のもので、地球社会全体が父権制に移行したという主張は、父権の強い西欧のような遊牧、牧畜社会が自らの正当性を主張するためのイデオロギーであり、遊牧、牧畜民が自らの父権社会の社会タイプを世界標準化し、東アジアのような農耕民側にある母性の影響力を奪い、少なくすることで、農耕民に打ち勝ち、農耕民を支配するための策略の一種なのである。
当然、強い父権のもと女性が弱い立場に置かれ差別されていることを主張するフェミニズムも、西欧母権制論者と同じ戦略で、自らの遊牧、牧畜民の父権社会向け理論を世界標準として、残りの社会全体に強引に適用し、押しつけることで、世界において支配的地位を確立しようとするものである。
そういう背景があることに無知なまま、まんまと西欧遊牧、牧畜民の戦略にはまって、彼らのイデオロギーを一生懸命自分たちの社会に適用しようと宣伝しているのが、従来の日本の女性学者、フェミニストであると言える。
逆に考えれば、こうした西欧の母権制消滅論を日本社会に当てはめ、日本人の間にあまねく広めることで、日本社会における母権の強さを社会から葬り去ることが可能なのかもしれない。そういう点では、西欧の母権制論者の主張は、日本男性をその母親による支配から解放するために役立つとも言える。
(初出2009年4月)
母権制が消滅したと言われることは、事実に反する。日本の母親の力は強大であり、その点、日本社会は母権制と言うことが可能だからである。一方、母親を血縁の系譜代表として捉える母系制が消滅したと言われることについても、こちらもインドネシア等に実在するとされており、正しくない。日本社会については、母系制は当てはまらず、母権制のみ当てはまる。
母権制と母系制の混同がなぜ起きたのか?
それは、Matriarchy(女家長制)の考えを生み出した欧米社会が主に家父長制、Patriarchyであったからと思われる。
家父長制においては、家族の対外代表者(姓、血縁系譜における)と権力者が、両方共、父であり、一致しているのである。その点、代表している者には権力がある、あるいは逆に、権力ある者は代表している、という暗黙の了解が出来上がったと考えられる。
一方、日本社会は、母権制だが父系制であると言える。日本の母親は支配者であり、権力は振るっているが、一家の代表責任者の役回りは父親にお任せにし、押し付けている。すなわち、自己の保身に支障が出る、対外的に外部露出する危ない大変な役回りは、父、男に押し付け、自分は、奥座敷で守られ、リスクを負うのを免除されているのを好むのである。そこには、自己の保身、安全第一の、より生物学的に貴重な性としての行動様式が見える。
このように、日本社会では、権力者と代表者が一致しないが、これは欧米のMatriarchyの概念では想定されていないのではないだろうか。
要するに、Matriarchyの概念においては、母親が対外的に代表者であり、かつ権力者であることを想定しており、そのため、家族の代表責任者と権力者の概念が混ざってしまっているのである。
これは、従来の「長」Headの概念が内包する問題点であるとも言える。「長」は代表責任者と権力者を兼ね備えた存在であり、「家長」Head of familyに当たる人物が、性別の観点から、父親の場合がpatriarchy、母親の場合がmatriarchyが成立していると呼ぼうとしたのだと考えられる。このpatriarchy、matriarchy両方とも、代表責任者と権力者、支配者の概念が混ざってしまっており、それが、「母権制は存在する、しない」といった、学説上の混乱の原因となっていると言える。
こうした混乱を解決するには、父母の、権力者、支配者としての側面を表す、母権、父権の概念と、代表責任者としての側面を表す母系、父系の概念とをはっきり別々に分けて表現する、世界で広く使用される欧米言語とかによる新たな用語を確立する必要があると考えられる。日本語では、母権制と母系制というように分けて表現可能だが、従来の欧米のmatriarchyの概念では混ざってしまい、分けることが不可能なため、新たな用語が必要になる。例えば、母権社会、母権制は、society of strong, powerful motherとかsociety of strong maternal powerとか言えば良いのであろうか。あるいは、母系社会、母系制は、society of maternal representativeとか言えば良いのであろうか。早急に決定する必要がある。
要するに、母権制の英語とかでの対応訳語は、従来のmatriarchyではマズいのである。新しい英語表現が必要である。Matriarchyは最近では女家長制と訳されるようになってきているようであるが、母権、母系を両方兼ね備えた時に成立する言葉であり、日本みたいに、母親の力が強い母権社会であるが、母親が家族を代表しない、すなわち母系社会ではない社会を表すには適当でない。
母親が家庭内で権力を振るう、支配する母権社会は、日本のような稲作農耕社会で普通に見られる。一方、母親が一家を代表する社会、一家の責任を取る母系社会は、日本では、ほとんど無いと考えられる。この現状を、例えば英語で一言で簡単に言い表せるようになればと考える。
(初出2012年1月)
なぜ、これまで日本社会は、母権社会でありながら、母権社会と言われてこなかったのか?あるいは、母権が無視、隠蔽されてきたのか?
日本社会全般のあり方からは、以下の理由が考えられる。
(1)日本にとって権威筋に当たる欧米の言論が、母権制を過去のもので、もう存在しないと断定したため、とかく欧米の権威によりかかって物事を考える日本人は、日本社会は母権制ではない、家父長制だと、そのまま、きちんと確認を取ることなく思いこんでしまったためである。
日本男性のあり方からは、以下の理由が考えられる。
(1)これまで男尊女卑で、「自分は女より立場が上なのだ」として高いプライドを持って威張って生きてきた日本男性が、自分の社会的立場が、実際は女性に比べて決定的に弱いことを認めたくないためである。
(2)日本男性が自ら母の支配下に入っていること、マザコンであることを、女性に認識されると、恋愛対象として見てもらえなくなり、性的に値打ちが下がってしまうことを嫌うため、母の支配を公式に認めたくないためである。
日本女性のあり方からは、以下の理由が考えられる。
(1)日本女性が、自分のことを「お母さん」と呼ばれたくないためである。
女性は、一般に「お母さん」と呼ばれると、良い気分がしない、気分を害する傾向がある。
その理由は、
・「お母さん」という言葉が、既婚で子供がいることを表すので、もう男性の恋愛対象でなくなっていること、
・子供がいるほどに結婚年齢を重ね、歳を取っていて、もう若くなく、男性から女として見てもらえなくなっている、女の魅力が見てもらえなくなっていること、
の確認がなされてしまうため、自分が性的に値打ちが下がっていることを否応なく認識させられ、性的意識の側面で喪失感を感じることによると考えられる。
その結果、日本女性は、自ら母として大きな権力を振るっているにも関わらず、「母であること」「母と呼ばれること」を良しとしない。そして、「母権」「母性」が強調されることを、ことさらに避けよう、無視しようとする。
(2)日本女性は、自ら母として社会を支配していることを認めてしまうと、そのことに対する社会的責任が生じてしまう。自己保身、安全第一を指向する女性にとっては、社会運営失敗時のリスクを取らねばならなくなるのが都合が悪くて、社会を支配していることを認めたくないため、母権という言葉を避けようとする。
(3) 自身の保身、安全の確保に人一倍敏感な日本女性は、対外的に代表となることを避けて、奥様でいようとする。日本女性が、自ら母として社会を支配していることを認めてしまうと、本来奥にいることで外から見えないはずの、その存在自体が外部に透けて見えて、表面から知られて、分かってしまい、「真の支配者が奥に潜んでいる」として、奥に踏み込まれる追撃の対象となってしまう。自己保身、安全第一を指向し、外に透けて見えない、より安全で温もりに満ちた奥の院に留まって社会を支配し続けようとする女性にとっては、支配者としての自身の存在が外部に明らかになってしまうことで、自身の身の安全が脅かされるのが都合が悪くて、社会を支配していることを公には認めたくないため、母権という言葉を避けようとする。
これらが、日本社会が実質母権社会でありながら、そう言われてこなかった大きな理由であると考えられる。
(初出2012年3月)
日本男女の性的役割は、「母と息子」として表される。
女性は、母の役割で、息子の役割を担う男性を大きな力でやさしく包み込み、かいがいしく世話をすると共に、男性を彼女の自己実現の手段と見なし、稼いだり、出世するように男性を動機付け、尻を叩く。
男性は、息子の役割で、母の役割を担う女性の意向を実現すべく、稼ぎや出世に励み、必要に応じて女性を頼もしく助けると共に、女性に心理的に依存し、甘え、母たる女性の支配下に入る。永遠の息子として、心理的に父親になれない、父性未満の存在である。
(初出2012年2月)
日本の最終支配者は、
家庭では、母、姑であり、職域では(数は少ないが)姉御である。
職場で姉御で、家庭で母、姑である女性が日本社会では最強である。
従来彼女らは、表に出てこない奥まったところに居て、そこから表だった見せかけの代表者である息子である男性たちをコントロールしてきた。表に出ない裏、闇の存在なので、従来の表層的なジェンダー研究では、支配者と気づかれなかったのである。
これからのジェンダー研究においては、こうした最終支配者の女性を奥座敷から表へ引っ張り出す作業が必要である。
(初出2010年7月 )
K.ヴォルフレンが、日本社会を解明する上で、謎である、不明なシステムであるとしたものこそが、「女性、母性社会システム」であり、日本社会の中核をなしている。
日本の社会システムは、母なるシステム、女性システムで動いているが、どのような動きをするか、まだきちんと研究されていない。今後、解明が必要である。
(初出2011年3月)
日本社会は、母の王国、楽園として捉えることができる。
母の、重たく、しつこく、うるさく、パワフルな本性が、日本社会全体を覆っていると言える。
液体的な、女性、母性システム社会=母なるシステムは、本来、退嬰的であり、自分からは近代化を行う芽を持たない。
一方、男性、父性システム社会=父なるシステムは、自分から進んで危険に立ち向かい、革新的な知見を得ようとする点、近代化への芽を内蔵している。
母なるシステム(日本)は、父なるシステム(欧米)から、新しい技術とかの輸入を行い、そうすることで近代化を実現する。
(初出2011年3月)
既存の日本社会の顕著な特徴として、会社や官庁における新卒一括採用の原則が上げられる。
これは、学年初めの新入生同士のように、人間関係が最初何も形成されていない状態、まっさらの更地状態から始めないといけないという「更地開始」原則である。新入生同士の友人、人間関係は、最初の一瞬が肝心で、そこで以後のほとんどが出来上がってしまう。そして、部活とか、人員が固定化されていて、新陳代謝、人の出入りが少ない条件下では、最初の一瞬でどこかの人間関係、集団に潜り込めなかった人間が、既に出来上がった友人、人間関係の中に後から割って入るのが大変であり、友達が新たにできない、作れない原因となる。
いったん開通した人間の絆、コネ、コミュニケーション回路を、再びスパッと切って、他にさっさと移動できるのが、ドライな父性的欧米社会であり、できないのが、ウェットな母性的日本社会である。
ウェットな日本社会においては、いったん生成した対人関係はweb、蜘蛛の巣のような感じで作用する。すなわち、ベトベトと絡み付くのである。そのため、既存の対人関係を壊して、再び構築し直すパワーや能力に欠けることになる。
そのため、先祖や先輩といった先人や、既に同じグループとなった同士が張り巡らした既存のコネクションをひたすらそのまま流用するだけとなる。人々の関係、コネの線を追加で引くことしかできない。切断、消去して、仕切り直すことができない。いわば、「初期化」ができないため、コネの線がどんどん増えて、複雑にこんがらがって、どんどん身動きが取れなくなって行く。これは、自分の力では治せない一種の病気である。既存のコネクション、コネの前例維持の力が強すぎて、柵でどんどんがんじがらめになっていって、社会の自由な流動や活気が失われていくのである。世代間で柵が連鎖して、重層化して、新たな仕切り直しの機会がほとんど消滅しているのが、日本の地方の農村とかの伝統的ムラ社会である。
抜本的なコネクションの新規形成は、最初の1回のみ可能であり、そのことが、日本の会社や官庁が、新規一括採用に根本的なところで依存する大きな理由である。
(初出2011年10月)
[要旨] 日本の男性たちは、「母性」に完全に支配されており、また「母性的な女性」に強度に依存しています。日本の男性たちが、本来あるべき父性を取り戻し、こうした母性への依存状態から脱却するための処方箋を述べています。
◇
従来より、日本社会は、母性が中心となって動く、「母性型社会」であると言われてきた(例えば[河合1976])。筆者としては、その際、母性の担い手である女性だけでなく、男性までもが、母性的態度を取っている、という点に問題があると考えている。
日本の男性たちが、職場などで実際に取る態度は、いわゆる「浪花節的」と称される、互いの一体感や同調性を過度に重んじる、対人関係で温もりや「甘え」を強く求める、内輪だけで固まる閉鎖的な対人関係を好む、など、ウェットで母性的な態度が主流である。(母性的態度、父性的態度についての説明は、著者の他著作を参照して下さい。)
彼ら日本男性は、一応男性の皮をかぶっているが、実際には、母性的な価値観(それ自体、女性的な価値観の一部である)で行動しているのである。これは、日本社会における母性の支配力の強さを見せつけるものであり、日本社会の最終権力者が、実際には、彼ら男性たちの「母」(姑)ないし「母」役を務めている妻であることを示している。
こうした母性的行動を取る日本男性は、母に包含され、母性の麻酔を母によって打たれ、「母性の漬け物」と化している。その点、自分とは反対の性である母性の強い影響のもと、自分たちが本来持つべき父性を失っている。
要するに、日本社会を支配していると表面的には見える男性たちは、実際には、「母」によって背後から操縦、制御される「ロボット」「操り人形」なのであり、「母」に完全に支配されているのである。日本の男性たちは、「母」によって管理・操縦されているため、集団主義、相互規制、閉鎖指向といった、男性本来の個人主義、自由主義、開放指向とは正反対の、ウェットで母性的な振る舞いをするのである。
日本社会は、その全体像が一人の「母」となって立ち現れるのであり、男性は、母性の巨大な渦の中に完全に呑み込まれ、窒息状態にある。
日本男性を、こうした、自分とは反対の性の餌食になっている現状から救うには、「母性からの解放」が必要である。
今までは、日本における「母性」は、男性にとっては、自分たちを温かく一体感をもって包み込んでくれるやさしい存在として、肯定的、望ましいものとして捉えられることが多かった。日本男性がその結婚相手の若い女性に求める理想像も、「自分が仕事から疲れて帰って来た時に温かく迎えてくれる」「自分のことをかいがいしく世話してくれる」といったように、母性的なものになりがちであった。
また、「母性」の行使者である「母」「姑」といった存在が権力者として捉えられることはなかった。日本の女性学においては、権力者は、「家長」としていばっている男性であるという見方がほとんどである。彼ら「家長」たる男性が、その母親と強い一体感で結ばれ、母親の意向を常に汲んで行動する、言わば、「母の出先機関・出張所」みたいな意味合いしか持たない存在であることに言及した書物はほとんどない。
例えば、一家の財産の名義は、「家長」である男性が持つとされ、それが日本は男性が支配する国であるという見解を生んでいる。しかし、実際のところ、母親との強い癒着・一体感のもと、「母性の漬け物」と化した男性は、実質的にはその母親の「所有物」であり、その母親の配下にある存在である。彼は、独立した男性というよりは、あくまで「母・姑の息子」であり、母親の差し金によって動くのである。
だから、男性が財産の名義を持つといっても、それは、「母」が息子=自分の子分、自己の延長物に対して、管理の代表権を見かけだけ委託しているに過ぎず、実際の管理は、「母」が行うのである。その点、財産権は、実質的には、息子の母のものである。ただ、母親は、女性として、一家の奥に守られている存在であることを望み、表立って一家を代表する立場に立つことを嫌うので、その役割が息子に回ってくる、というだけのことである。母は、息子に対して、財産の名義を単に持たせているだけであり、実際の管理権限は母(姑)ががっちり握って離さない。
このように、母親に依存し、女性一般を母親代わりに見立てて甘えようとする、「母性依存症」とも呼ぶべき症状を起こしている日本男性に対しては、母性支配からの脱却を目指した新たな処方箋が必要である。日本男性にとっては、本来母性は、決して望ましいものではなく、脱却、克服の対象となる存在となるべきなのであるが、それをわかっていない、母性に対する依頼心の強い男性が余りにも多すぎるのが現状である。
筆者の主張する、「母性依存症」への対処方法は以下の通りである。
(1)まずは手始めに、取る態度を、本来男性が持つべき、個人主義的で自由や個性を重んじる、ドライな「父性的」態度に改めるべきである。言わば、自らの心の中に欠如していた父性を取り戻すのである。これについては、例えば「家父長制」社会=遊牧・牧畜中心社会の立役者である、父性を豊富に備えている、欧米の男性が適切なモデルとなると考えられる。欧米のような家父長制社会を実現しようとなると極端になってしまうが、今まで母性偏重だったのを、母性と父性が対等な価値を持つところまで、父性の位置づけを向上させることは必要であろう。
(付記)なお、従来も「父性の復権」が言われたことがあった(例えば[林道義1996])が、その際言われた「父性」とは、全体を見渡す視点、指導力、権威といったことを指しており、筆者が、上で述べた、個人主義、自由主義、対人面での相互分離、独創性の発揮といった、ドライさを備えた父性への言及が全くない。その点、従来述べられてきた復権の対象としての「父性」は、今までの母子癒着状態をそのまま生かしながら、従来の母性で足りない点を補完する「母性肯定・補完型」の父性であって、筆者の主張する、母性に反逆して、母性の延長線とは正反対の父性を築こうとする「母性否定・対抗型」の父性の復権とは異なると考えられる。
(2)また、「母」的価値からの逃走、ないし反逆を試みるべきである。今まで、自分が一体感をもって依存してきた母親に対して反抗とか独立を試みるのは、非常に難しいことであるのは確かだが、これを実行しない限り、永遠に母性の支配下に置かれることになる。そのためにも、相手との一体感や甘え感覚がなくても自我を平静に保てるように、相手からのスムーズな分離や独立を目指す、「母性からの脱却」「父性の回復」訓練を、自ら進んで実践することが必要である。女性一般に対しても、心の奥深くにある彼女たちへの依存心(自分の母親みたいに、温かく世話して欲しいなど)を克服し、「自分のことは自分で世話する」という自立の精神を持つ必要がある。
(3)子育てに父親として積極的に参加し、母子の絆の中に割り込んで、彼らを引き離すことが必要である。従来、日本の男性は、「仕事が重要である」として、子供との心理的な交流をほとんどしてこなかった。それが、男性が子供と自分とを切り離し、子供から無意識のうちに遠ざけられるようにすることで、母親と子供の間にできる、強固な、誰も割って入ることのできない絆を生み出し、それが、母性による子供の全人格的支配を生み出してきた。(この状態にある母子を、筆者は、「母子連合体」と仮に名付けています。詳細な説明は本書の他セクションを参照して下さい。)
男性が子供との交流をしないのは、自分自身の子供時代に、父親との満足な交流の経験がないというのも影響している。一つ前の世代の父親が子供と心理的に隔離された状態に置かれることが、「母子連合体」の再生産を許してきたのである。
従って、子供が母親と完全に癒着した、母性による子供の支配が完成した状態である「母子連合体」の再生産を阻止するには、父親が、母と子供の間に割って入って、自ら主体的に子供との心理的交流を図る作業を実行することが大切である。今まで日本男性が子育てを避ける口実としてきた「仕事が忙しいから」というのは、子供と父とを近づけまいとする、母による無意識の差し金によるものであることを自覚し、それを克服すべきである。外回りの仕事を女性により任せるようにして、その分、自分は家庭に積極的に入るべきなのである。
[参考文献]
河合隼雄、母性社会日本の病理、1976、中央公論社
林道義、父性の復権、1996、中央公論社
(初出2003年05月)
日本の人たちは、お母さん、お袋さんに強度に依存している。お母さんがいないと何も出来ない、生きていけないと感じている人が多い。皆が精神的に、お母さんに頼り切りになっており、「お母さんの子供」状態を続けている。太平洋戦争時、敗戦で死に行く日本人の兵隊たちが、「お母さん」と叫びながら死んでいったという話は有名である。母に単に身辺の世話をしてもらうだけでなく、社会で生きていく力それ自身を供給されている感じである。母である女性が、家族や社会全体の精神的な支柱になっていて、真に強大な存在である。これは、母である女性が、社会の真の支配者であることを示している。
一方、男性は、母に依存した、父親未満の単なる子供に留まっていることが問題であると言える。
(初出2012年06月)
[要約] 「日本=母性社会」論は、その本質が、日本社会を最終的に支配している社会の最高権力者が母性(の担い手である女性)であることを示すものだと筆者は捉える。日本の女性学による「母性社会論は、女性に子育ての役割を一方的に押しつけるものだ」という批判は、女性たちが日本社会を実質的に支配していることを隠蔽する、責任逃れのための「焦点外し」だと考えられる。また、女性たちが従来の「我が子を通じた社会の間接支配」に飽き足らず、自分自身で直接、会社・官庁で昇進し支配者となる、言わば「社会の直接支配」を目指そうとする戦略と見ることもできる。
◇
従来の日本女性学では、臨床心理学者などが提唱している日本を「母性社会」とする見方について、「日本社会が、子供を産み育てる役割を一方的に女性(母親)のみに押しつけていることを示しており、有害である。修正されなくてはならない。」という反応が主流である。
これに対して、筆者は、日本を「母性社会」とする見方は、本来、「日本社会における母性の影響力、権勢が強い。日本社会において、母親が社会の支配者となっている」ことの現れであると見る。要は、日本社会において「母」が社会の根底を支配しており、万人が母親の強い影響下で「母性の漬け物」になっている社会であることを示すのが、「母性社会」という表現だと考えている。
日本の母親は、例えば「教育ママゴン」みたいに、その力の強さを怪物扱いされるような、巨大で手強く、誰もが逆らえない存在なのである。
日本の女性学による、「臨床心理学者たちは、母性社会という言葉を使って、「母」としての女性のみを称賛し、子供を産み育てる役割を女性に押しつけている」という批判は、「日本社会の根幹を支配しているのが母性(の担い手である女性)である」という現状から人々の目を外して、自分たち女性が社会の支配責任を負わなくて済むようにしよう、自分たち(支配側にある)女性に被支配者(男性、子供)の批判、反発が集まらないようにしようとする、「焦点外し」の巧みな戦略、策略だと、筆者には思えてならない。要は、自分たち女性(母性)が社会の実質的支配者であることを、人々に気づかせまいと必死なのである。
また、「子供を産み育てる役割を女性に押しつけるのはいけない」みたいな論調が広がっているが、本来、日本の女性が社会で支配力を振るってこれたのは、彼女らが、子育ての役割を独占することで、自分の子供を、自分の思い通りに動く「駒」として独占的に調教できたから、というのが大きいと考えられる。日本の女性たちは、自分の子供を「自己実現の道具」として、学校での受験競争、会社での昇進競争に、子供の尻を叩いて駆り立て、子供が母親の言うことを聞いて必死に努力して社会的に偉くなった暁には、自分は「母」として、一見社会的支配者となったかに見える子供を更に支配する「最終支配者」的存在として、社会の称賛を浴び、社会に睨みを効かせることができる。
要は、子供の養育を独占することで、自分の子供を完全に「私物化」できることが、日本の女性たちが社会で大きな権勢をこれまで振るってこられた主要な理由であり、要は、「(自分の)子供を通した(日本社会の)間接的支配」というのが、日本の女性たちが社会を支配する上でのお決まりのパターン、手法であった。要は競走馬(我が子)のたずなをコントロールする騎手として、日本女性は、社会をコントロール、支配してきたのである。
「子供を産み育てる役割を女性に押しつけるのはいけない」という論調に日本女性が同調しているのは、彼女らが今まで築き上げてきた、「子供を通じた社会支配」という、彼女らによる日本社会支配手法の定石を自ら捨て去ろうとしている点、実は、日本女性にとってはマイナスであり、むしろ男性にとって、子供を女性の手から取り戻す機会が増える点、プラスであると言える。
ただ、日本男性にとって一番恐ろしいのは、日本女性が、従来の「我が子を通じた、社会の間接支配」に飽き足らず、自ら社会を「直接支配」する者になることを開始することである。従来の我が子を私物化することでの「我が子経由での社会支配」を維持しつつ、自分自身も、会社・官庁で昇進をして偉くなることで、「直接・間接」の両面で日本社会支配を完成させること、これが、本来なら日本のフェミニスト(女権拡張論者)の最終目標となるはずのものであり、日本男性としては、これが実現しないように最大限努力する必要がある。幸い、日本のフェミニストは、この最終目標にまだ気づいておらず、我が子を通じた間接(社会)支配権限を自ら捨て去ろうとしている。これは、日本男性にとって、女性から我が子を取り戻す絶好のチャンスである。
「子育ては女性がするもの」という固定観念は、日本女性による我が子の独占と、我が子を通じた社会の間接支配権限を助長する考え方であり、女性を利する点が多く、男性にはマイナスなのであるが、日本の男性は、そのことに気づかないまま、自分の母親の「自己実現の駒」として、会社での仕事にひたすら取り組み、それが「男らしい」と勘違いしている。
日本の男性は、もう少し、自分の子供に対する影響力を強化することに心を配るべきなのではないか?自分の子供に自分の価値観をきちんと伝えて、自分の後継者たらしめる努力をもっとしないと、いつまで経っても、子供は女性の私物のままである。そして、女性たちが、子供を自分にしっかりと手なずけつつ、自分自身、会社での昇進を本格化させると、心の奥底で、母性に依存したままの男性たちは、寄る辺もなく総崩れになってしまうであろう。そうならないように、自分と母親との関係を見直し、「母からの心理的卒業」と「子供をコントロールする力の確立」を果たすべきなのである。
(初出2005年10月)
[要旨] 従来の日本の女性学は、自分たちの立場を「娘」「嫁」といった、弱い立場の女性に限定して捉えてきました。そのため、同じ女性でも、極めて強大な権力を持つ「母」「姑」の視点が欠けているように思えます。今後はより正しい日本社会の把握のために、「母」「姑」の視点をより大きく取り入れるべきであると考えます。
既存の日本のフェミニズム、女性学は、社会的弱者である「娘」「嫁」の立場の女性ための学問であり、社会の支配者、権力者である「母」「姑」の立場からの視点が、決定的に欠落している。
今までの日本の女性学の文献を調査すると、「嫁」「妻」「女(これは未婚の女性である「娘」に相当することが多い)という言葉は頻繁に出てくるが、「母」となると急速に数を減らし(それもほとんどは、女性と「母性」の結びつきを批判する内容のものであり、「母親」の立場に立った内容の記述はほとんど見られない)、「姑」に至っては、全くといってよいほど出てこない。要するに、「母」「姑」の立場から書かれた女性学の文献は、今までは、ほとんどないというのが現状だと考えられる。要するに、日本の女性学は、「娘」「嫁」の立場でばかり、主張を繰り返しているようなのである。
既存の日本の女性学は、「日本社会の男性による支配=家父長制」を問題視し、批判の対象としてきた。しかし、彼女たちが真に恐れるのは、本当に男性なのだろうか?
例えば、日本の若い女性は、結婚相手の男性を選ぶ際に、長男を避けて次男以下と結婚しようとしたり、夫の家族との同居を避け、別居しようとする傾向がある。こうした行動を彼女たちに取らせる核心は、「ババ(姑)抜き」(「お義母さんと一緒になりたくない」という一言に尽きる。
要するに、彼女たちにとって一番怖いのは、夫となる男性ではなく、夫の母親である「姑」(女性!)なのである。なぜ、彼女たちが「お義母さん=姑」を恐れるかと言えば、姑こそが、夫を含む家族の真の管理者(administrator)であり、彼女には家族の誰もが逆らえないからである。結婚して同居すれば、夫も夫の妻も、等しく彼らの「母」ないし「義母」である「姑」に、箸の上げ下ろし一つにまでうるさく介入され、指示を受ける。従わないと、ことあるごとに説教されたり、陰湿な嫌がらせを受けたり、といった、精神的に逃げ場のないところまでとことん追い込まれてしまうのである。また、経済的にも、「母」「姑」に一家の財布をがっちりと握られるため、どうしても彼女たちの言うことを聞く必要が出てくる。
こうした点、「母」「姑」こそが、その息子である男性にとっても、「嫁」「娘」の立場にある女性にとっても、等しく共通に、乗り越えるべき「日本社会の最終支配者」なのである。特に、母子癒着こそが、「母」「姑」が自分の子供(特に男性=息子)を、強烈な母子一体感をもって、自分の思い通りに操る力の源泉となり、「母性による社会支配」の要となっている考えられる。
日本の女性学が、そうした「母」「姑」のことを、今まで取り上げてこなかったのはなぜか?
[1]日本の女性学は、社会的に不利な立場にある女性の解放というのを、主要な目的として掲げてきたが、日本社会の支配者としての「母」「姑」という存在は、「弱小者としての女性を解放する」という目的に反する、厄介なものだったからであろう。いったん強大な権力者である「母」「姑」の視点を取ってしまうと、「女性=弱者」という見方は実質的に不可能となるからである。
[2]日本の女性学は、女性同士の連帯・団結を重要視して発展してきたと考えられる。従来は、「娘」「嫁」「妻」の立場を取ることによって、広く女性全体がまとまりを作りやすかった。しかるに、そこに「母」「姑」の立場を持ち込むと、(a)子供を持つ「母」の立場の女性と、未だ持たざる女性、および(b) 「姑」の立場の女性と、その支配を嫌々受けなくてはいけない「嫁」の立場の女性との間に亀裂が生じ、女性同士の連帯感、一体感が大きく損なわれると考えられる。そのため、女性全体の一体性を保つために、あえて「母」「姑」を無視してきたと考えられる。
これら[1][2]は、いずれも「臭いものにはふた」「自説を展開する上で都合の悪い事象は無視」という考え方であり、日本の女性学が、説得力のある内容を持った「科学」として発展していく上で、大きな阻害要因となると言える。日本の女性学が科学として今後も伸びていくには、「母」「姑」の視点を取り入れることで、
(1)「女性=世界のどこでも弱者」という見方を根本からひっくり返して、「日本社会においては、女性=強者である」として、女性に関する社会現象を正しく取り扱えるようにする
(2)女性同士の表面的な連帯感・一体感の深層にある、「母」と「未だ母ならざる女性(娘、妻)」、「姑」と「嫁」との対立を、連帯感・一体感が損なわれることを恐れずにとことんまで明らかにして、もう一度見つめなおすことで、今までの表面的なものではない、女性同士の真の、心の底からの新たな連帯の可能性を見出す
といったことが必要なのではあるまいか?
一方、日本の女性学が、「母」「姑」を軽視してきたのには、以下のような理由もあると考えられる。
[3]日本の女性学は、視点が、(男性が活躍してきた)社会組織(すなわち企業、官庁)における女性の役割や地位向上に向いており、その分、家庭の持つ、一般社会に対する影響力を過小評価してきたからである。要するに、家庭において「母」「姑」が権力を握っていることを仮に認めたとしても、その影響力はあくまで家庭内止まりであって、社会には影響が及ばないと考えているため、「母」「姑」を無視してきたと考えられる。
これに対しては、家庭こそが、社会における基本的な基地、母艦であり、そこから毎日通勤、通学に出かける成員たちが、いずれはそこに帰宅しなくてはいけない、最終的な生活の場、帰着地である、とする見方が考えられる。この見方からは、社会の最も基礎的なユニットが家庭であり、企業や官庁といった社会組織の活動も、家庭という基盤の上に乗って初めて成立するということになる。要するに、「家庭を制する者は、社会を制する」ということになる。
こうした見方が正しいとすれば、「母」「姑」は、企業や官庁で活躍する人々(その多くは男性)の意識を、根底から支え、管理、制御、操縦する、「社会の根本的な支配者、管理者」としての顔を持つことになる。要するに、家庭は、一般社会に対して大きな影響力を持つ存在であり、その支配者としての「母」「姑」を無視することは、日本社会のしくみの正しい把握を困難にする、と言える。そうした点でも、「母」「姑」を女性学の対象に含めることが必要である。
なお、日本女性学で「母」「姑」が無視されてきたのには、次のような推測も可能である。
[4]日本の女性学での主張内容は、そのまま女性たちの不満のはけ口となっていると考えられる。彼女たちにとって不満なのは、弱者としての「娘」「嫁」としての立場なのであって、「母」「姑」となると、社会的にも地位が高止まりで安定し、それなりに満足すると考えられる。女性たちは、自分たちにとって不愉快な「娘」「嫁」としての立場に異議申し立てをする一方、「母」「姑」については、その申し立ての必要がなくなり、そのため、日本女性学の主張内容から外れたと考えられる。
日本の女性学が、社会現象を正しく捉える科学として成立するには、上記のように女性自身にとって不満な点のみを強調するだけでは、明らかに片手落ちであり、何が不満で何が満足かという、両面を把握する必要があるのではないか?
以上、述べたように、今後の日本の女性学は、自らを「被支配者」「下位者」「弱者」として扱う、「娘」「嫁」の視点から、自らを「支配者」「上位者」「強者」として扱う、「母」「姑」の視点への転換を行うべきである。そうすることで、日本女性たちは、今まで正しく自覚できてこなかった、社会の根本的な管理者、支配者(administrator)としての自らの役割に気づくことができるはずであり、そこから、新たな社会変革の視点が見えてくると考えられる。
そういう点では、今後の日本女性学では、「姑」の研究、ないし「母」の研究が、もっと活発になされるべきであろう。
あるいは、従来の日本史のような歴史学においては、姑が日本社会の真の支配者である可能性が高いのに、今まで殆どその存在が言及されて来なかった。
今後は、歴史の分野においても、新たに姑の研究が必要である。
(初出2003年05月)
[要旨] 日本では女性が息子・娘と強力に癒着することで「母子連合体」を形成して、社会の最もベーシックな基盤である家族を支配しています。従来の日本の家族関係に関する「夫による妻の支配=家父長制」という現象も、実際は、上世代の母子連合体(姑-息子)による、次(下)世代の母子連合体(嫁とその子供)支配として捉えられ、「母性による(母性未満の)女性の支配=母権制」の一つの現れとして説明することができる、と筆者は考えます。
◇
1.日本を支配する母性
一般に、「日本の支配者」というと、表立っては、政治家とか官僚、大企業幹部といった人々が思い浮かぶのが普通であろう。しかし、実際には、彼ら支配者を支配・監督する「支配者の支配者」と呼び得る立場にいる人々が、表立っては見えない、隠れた形で確実に存在する。
そうした、日本社会の根底を支配する人々、すなわち日本社会の最終支配者は、実際には、一般に「お母さん(母ちゃん)」「お袋さん」と呼ばれる人々である。彼女たちには、日本人の誰もが心理的に依存し、逆らえない。日本男児は、肉体的には強くても、「お袋」には勝てないのである。日本は「母」に支配される社会である。従来、日本の臨床心理の研究者たちは、日本社会を「母性社会」と呼んできたが、この呼称は日本社会における「母」の存在の大きさを示していると言える。
当たり前のことであるが、「母」「お袋」と呼ばれる人々は、言うまでもなく女性である。しかし、従来、日本社会において女性の立場はどうかと言えば、男尊女卑、職場での昇進差別やセクシャルハラスメントの対象であるといったように弱い、差別されている被害者の立場にあるという考えが主流であった。
この場合、「女性」と聞いて連想するのは、若い「娘さん」とか、「お嫁さん」といった立場の人が主であると考えられる。「女」という言葉には弱い、頼りないイメージがどうしても先行しがちである。従来の日本の女性学やフェミニズムを担う人たちが「女性解放」の対象としたのは、「娘」「嫁」といった立場にある女性たちであった。
しかし、同じ女性でも、「母」という呼称になると、一転して、全ての者を深い愛情・一体感で包み込み呑み込む、非常にパワフルで強いイメージとなる。「肝っ玉母さん」といった言い方がこの好例である。あるいは、「姑」という呼称になると、自分の息子とその嫁に対して箸の上げ下ろしまで細かくチェックし命令を下すとともに、夫を生活面で自分なしでは生きていけないような形へと依存させる強大な権力者としての顔が絶えず見え隠れする存在となる。
「母」「姑」の立場にある女性は、強力な母子一体感に基づいた子供の支配を行うとともに、夫についても、自分を母親代わりにして依存させる形の「母親への擬制」に基づいた支配を行っている。家庭において、子供の教育、家計管理、家族成員の生活管理といった、家庭の持つ主要な機能を独占支配しているのが「母」「姑」と呼ばれる女性たちの実態である。
言うなれば、「母」「姑」は社会にどっしりと根を降ろし、父とは重みが段違いに違う存在である。そういう点で「母」「姑」には、日本社会の根幹を支配するイメージがある、と言える。しかるに、日本女性のこうした側面は従来の日本の女性学やフェミニズムでは、自分たちの理論形成に都合が悪いとして「日本女性には、母性からの解放が必要だ」などという言説で無視するのが一般的であった。要するに日本の女性学やフェミニズムの担い手たちは、自分たちをか弱い「娘」「嫁」の立場に置くのが好みのようなのである。
確かに、日本の夫婦・夫妻関係では、日本のフェミニストたちが「家父長制」という言葉を使うように、夫が妻を抑圧する、夫優位の関係に少なくとも結婚当初は立つことが多いように思われる。夫による妻に対するドメスティック・バイオレンス問題も、この一環として捉えられる。これは、「男性による女性支配」というように一見見えるのであるが、実際は、直系家族の世代連鎖の中で、夫の母親である「姑」が、我が息子を「母子連合体」として自分の中に予め取り込み、自らの「操り人形」とした上で、その「操り人形」と一体となって「嫁」とその子供を支配する現象の一環に過ぎないと取るべきであると、筆者は考えている。
つまり、一見、妻を支配するように見える夫も、実は、その母親=「姑」の「大きな息子」として「母性」の支配を受ける存在であり、「姑」の意を汲んで動いているに過ぎない面が強い。その点、彼は、母親による支配=「母性支配」の被害者としての一面を持つ。
「妻に対する夫優位」の実態は、「嫁に対する姑の優位」のミニチュア・子供版(姑の息子版)=つまり、「嫁に対する『姑の息子』の優位」に過ぎないと言える。夫が妻に対して高飛車な態度に出られるのも、「姑」による精神的バックアップ、後ろ楯のおかげである側面が強く、「姑」の後ろ楯がなくなったら、夫は妻を「第二の母性(母親代わり)」として、濡れ落ち葉的に寄りすがるのは確実である。
要するに、「母性による(母性未満の)女性の支配」というのが、日本のフェミニストたちによって批判されてきた「家父長制」の隠れた実態であり、そういう点で実際には、日本における「家父長制」と呼ばれる現象は、女性同士の問題として捉えるべきなのである。この場合、「母性未満」の女性とは、まだ子供を産んでいないため、母親の立場についていない女性(未婚の娘、既婚の嫁)を指している。
2.「母子連合体」の「斜め重層構造」の概念について
日本社会においては、母親と子供との間は非常に強力な一体感で結ばれている。これは従来、「母子癒着・密着」という言葉で言い表されて来た。この、父親を含めた他の何者も割って入ることを許さない母親と子供との癒着関係をひとまとめにして表す言葉として、ここでは「母子連合体(ユニオン)」という言葉を使うことにする。この場合、子供は、性別の違いによって息子・娘の2通りが考えられるが、「母子連合体」は、そのどちらに対しても区別なく成り立つと考えられる。言うまでもなく、母子連合体の中で、母は、息子・娘を親として支配する関係にある。
日本の直系家族の系図の中では、「母子連合体」は、複数が重層的に積み重なった形で捉えられる。世代の異なる「母子連合体」の累積した「斜め重層構造」、より分かりやすく言えば「(カタカナの)ミの字構造」が、そこには見られる。新たな下(次世代)の層の「母子連合体」の生成は、家族への新たな女性の嫁入りと出産により起きる。この場合、より上の層に当たる、前の世代の母子連合体が、より下の層に当たる、次の世代の母子連合体を、生活全般にわたって支配すると捉えられる。上の世代の母子連合体に属する成員の方が、下の世代の母子連合体に属する成員に比べて、その家庭の行動規範である「しきたり・前例」をより豊富に身につけているため、当該家庭の「新参者」「新入り」である下の世代の母子連合体の成員は、彼らに逆らえない。この「母子連合体の斜め重層構造」を簡単に図式化してみた。
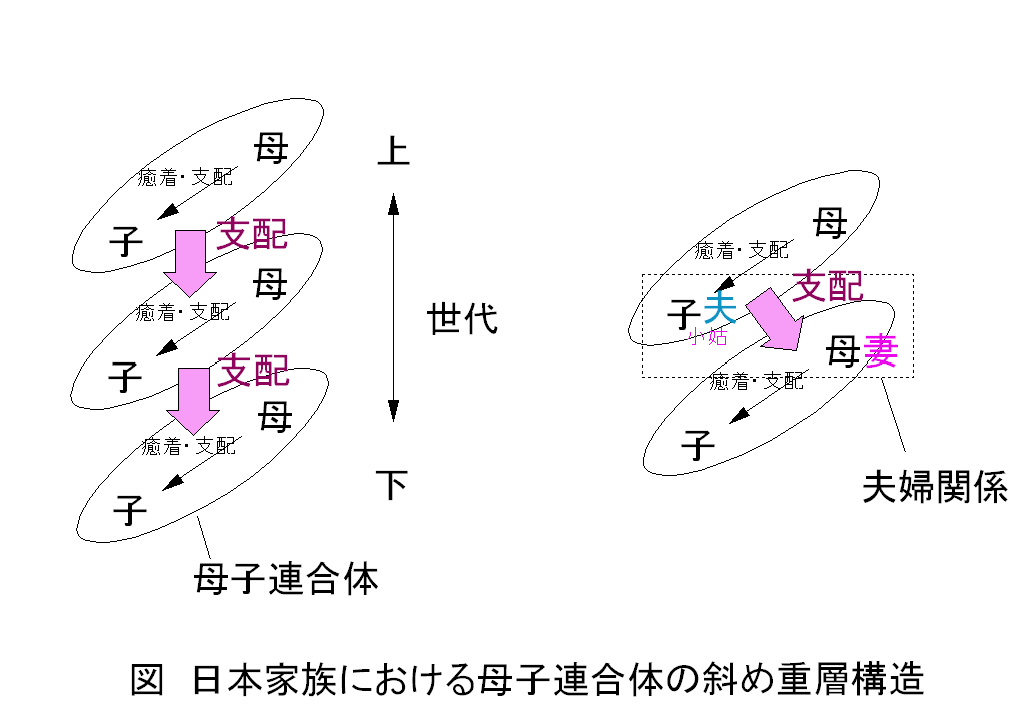
ここで着目すべきことは、家族の系図において、夫婦関係のみを取り出して見た場合、夫=姑の息子は、上の世代の母子連合体に属し、妻=嫁(あるいは姑の息子にとって自分の妻になりそうな自分と同世代の女性)は、次(下)の世代の母子連合体に属する(か、属する予定である)という点である。夫婦間で夫が妻を抑圧・支配しているように見える現象も、実際は上の世代の母子連合体の成員(姑の息子)が、次の世代の母子連合体の成員(嫁)を抑圧・支配しているというのが正体であると考えられる。
要するに、姑が、息子を自分の陣営に取り込む形で嫁を抑圧しているというのが、夫による妻抑圧のより正確な実態と考えられる。この場合、夫は、(従来の日本女性学が「家父長」と称してきたような)自立・独立した一人の男性と捉えることは難しく、むしろ「姑の息子」「姑の出先機関・出張所」として、姑(母親)に従属する存在として捉えられる。嫁にとっては強権の持ち主に見える夫も、その母親である姑から見れば自分の「分身・手下・子分」「付属物・延長物」であり、単なる支配・制御の対象であるに過ぎない。
母子連合体の支配者は母親であるから、家族という母子連合体の重層構造の中では、実際には母である女性が一番強いことになる。これは、日本社会が、見かけは「家父長制」であっても、その実態は「母権制」であることの証明となる。
日本男性は、母子連合体において、母によって支配される子供の役しか取れない(母になれない)ため、家庭~社会において永続的に立場が弱いのである(上記の母子連合体説明図において、「父」の字がどこにも存在しないことに注目されたい。これは、日本の家庭において、父の影が薄く、居場所がないことと符合する。日本の家庭では、男性は、(その母親の)「子」としてしか存在し得ないのである)。
この辺の事情を説明するのが、「小姑」と呼ばれる女性の存在である。つまり、嫁として夫(の家族)に忍従してきた女性が、一方では、自分の兄弟の嫁に対しては、「小姑」として高圧的で命令的な支配者としての態度を取るという、矛盾した態度を引き起こしている、という実態である。要するに、女性は、2つの異なる世代の母子連合体に同時に属することができるのである。「小姑」として威張るのは、上の世代の母子連合体に属する立場を、「嫁」としてひたすら夫(の家族)の言うことを聞くのは、次の下の世代の母子連合体に属する立場を、それぞれ代表していると考えられるのである。
要は、上の世代の母子連合体の成員である、姑、夫(姑の息子)、小姑が一体となって、自分たちの家族にとって異質な新参者である夫の妻=嫁(下世代の母子連合体成員)を、サディスティックに支配しいじめているのであり、それは、企業や学校における既存成員(先輩)による「新人(後輩)いびり」「新入生(下級生)いじめ」と根が同じである。これらのいじめを引き起こす側の心理的特徴は、共通に「姑根性」という言葉で一つにくくることができる。
ここで言う「姑根性」とは、要は、相手を自分より無条件で格下(であるべきだ)と見なし、相手の不十分な点を細かくあら探ししたり、相手の優れた点を否定する形で、相手を叱責・攻撃し、相手の足を引っ張り、相手を心理的に窮地に追い込んで、自分に無条件で服従、隷従させようとする心理である。
日本の若い男性が、同世代の女性に対して、高圧的で威張った態度に平気で出るのは、単に「男尊女卑」の考え方があるというだけではない。自分たちが、未来の家族関係において、結婚相手の候補となる同年代の女性たちよりも、一つ前の世代の母子連合体に属することが決まっているため、母子連合体の「斜め重層構造」から見て、「嫁」となって一つ下の世代の母子連合体を構築するはずの同年代の女性を、自分の母親と一緒になって、一つ上の母子連合体の成員として支配することができる有利な立場にあるからである。
夫による妻への暴力であるドメスティック・バイオレンス(DV)は、夫による妻の暴力を利用した支配、いじめということで、一見、男性による女性支配に見えやすい。しかし、実際には、日本の家族の場合においては、妻=嫁を支配したり、いじめたりしているのは、夫だけに限ったことではなく、夫の母親である姑や、夫の姉妹である小姑も、夫の妻=嫁をサディスティックに支配し、いじめている。
この点、夫によるドメスティック・バイオレンス(DV)は、実は、上世代の母子連合体成員(姑、夫、小姑)による、下世代の母子連合体成員(嫁とその子供)の支配、いじめの一環に過ぎないと言える。要は、日本における夫による妻へのドメスティック・バイオレンスは、嫁いびりをする姑のいわゆる「姑根性」と根が同じというか、その一種なのである。家風、その家の流儀を既に身につけた成員(姑、夫、小姑)=先輩による、家風をまだ身につけていない新人、後輩(=嫁)いじめの一種とも言える。
この場合、男性が高圧的になれるのは、男性自身に権力があるからでは全然なくて、心理的に(一つ上の世代の)母子連合体を一緒に形成する自分の母親という後ろ楯があるからであり、そこに、日本男性の母親依存(マザーコンプレックス)傾向が透けて見えるのである。
夫が妻に対して、高飛車で命令的で、乱暴な態度に出られるのも、夫がその妻よりも、一つ上の世代の母子連合体に属することで、妻とその子供が形成する次の下位世代の母子連合体を支配することができるからである。
この場合、見かけ上は、夫は妻(嫁)よりも常に優位な立場にいることができる訳であるが、だからと言って、それが日本社会において男性が女性よりも優位である証拠かと言われると、それは間違いであるということになる。つまり、夫は男性だから優位なのではなく、「姑の息子」だから=妻よりも1世代前のより上位の母子連合体に属するから、妻よりも優位なのである。
要は、夫(姑の息子)による妻(嫁)の支配は、小姑による嫁の支配とその性質が同じである。夫も小姑も、嫁よりも一つ上世代の母子連合体の成員=嫁にとっての先輩だから、嫁を共通に(嫁を後輩として)支配できるのである。この場合、言うまでもなく、夫は(小姑も)、その母と形成する母子連合体の中で、母である女性の支配を受ける存在である。
要するに、夫は、母親である姑と癒着状態で、その支配下に置かれており、その点、日本社会において本当に優位なのは、「母=姑」である女性であり、その息子として支配下に置かれる男性(夫)ではない。この点、日本は女性=母性の支配する社会であり、男性社会ではない。
日本の家庭においては、先祖代々、夫が威張って、妻が服従的な態度を取ることが繰り返され、それが、日本の家庭は、男性優位という印象を与えてきたわけであるが、実際には、その高飛車な夫が、その母親である姑の全人的な密着した支配下に置かれた「姑の付属品、出張所」に過ぎない存在であることを考えれば、日本の家庭は、実際には先祖代々恒常的に、母性=女性優位である、と言える。
おとなしく夫に従属しているかに見える妻も、実際のところ、その子供と強力に癒着して、何者も割って入ることのできない強烈な一体感のうちに、自分の子供を支配している。妻の子供(息子)は、大きくなっても、その母(夫にとっての妻)と強い一体感を保ち、母に支配された状態のまま、結婚をする。そして妻は、その息子を通して、新たな結婚相手の女性とその子供を支配することになる。
要するに、母子連合体においては、母はその子供(息子、娘)の全人格を一体的に、息苦しい癒着感をもって支配する存在である。日本の直系家族は、その母子連合体が、上世代の連合体が下世代の連合体を支配する形で積み重なって形成されてきた。日本の直系家族は、「母による子供の支配」の連鎖、重層化によって成り立ってきたと言える。
こうした母子連合体重層化の考え方は、「日本の家族において、夫婦関係が希薄で、母子関係が強い」、という家族社会学の従来の見解とも合致する。日本の家族では、各世代の母子連合体に相当する母子関係が非常に強力で家族関係の根幹をなしており、夫婦関係は、異なる世代の母子連合体同士を単にくっつけるだけの糊の役割を果たしているに過ぎないため、影が薄く見えるのである。
以上述べた母子連合体重層化のありさまを、家系図の形で表した図を作成した。
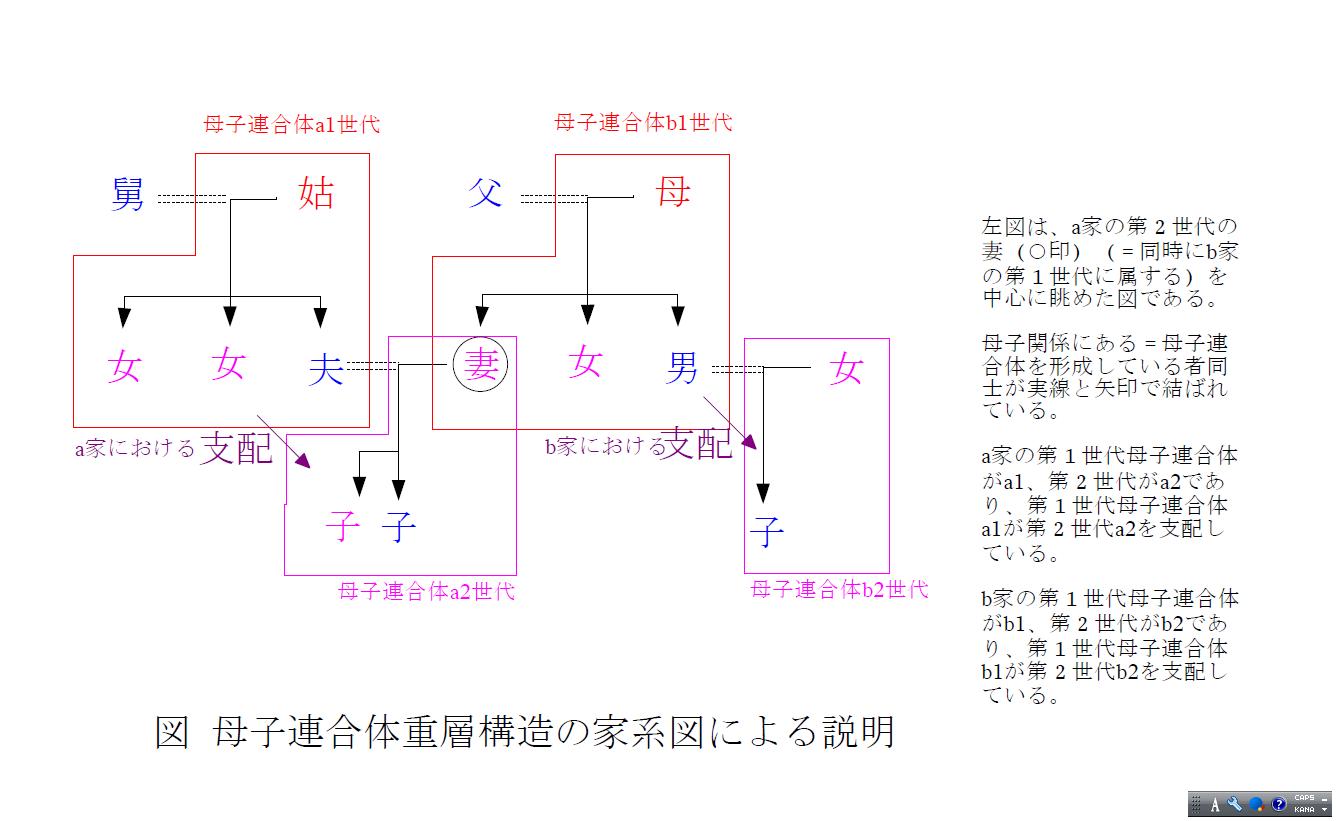
母と複数の子供との関係は、母子連合体の重層的なクラスターとして捉えられる。以下の図を参照されたい。
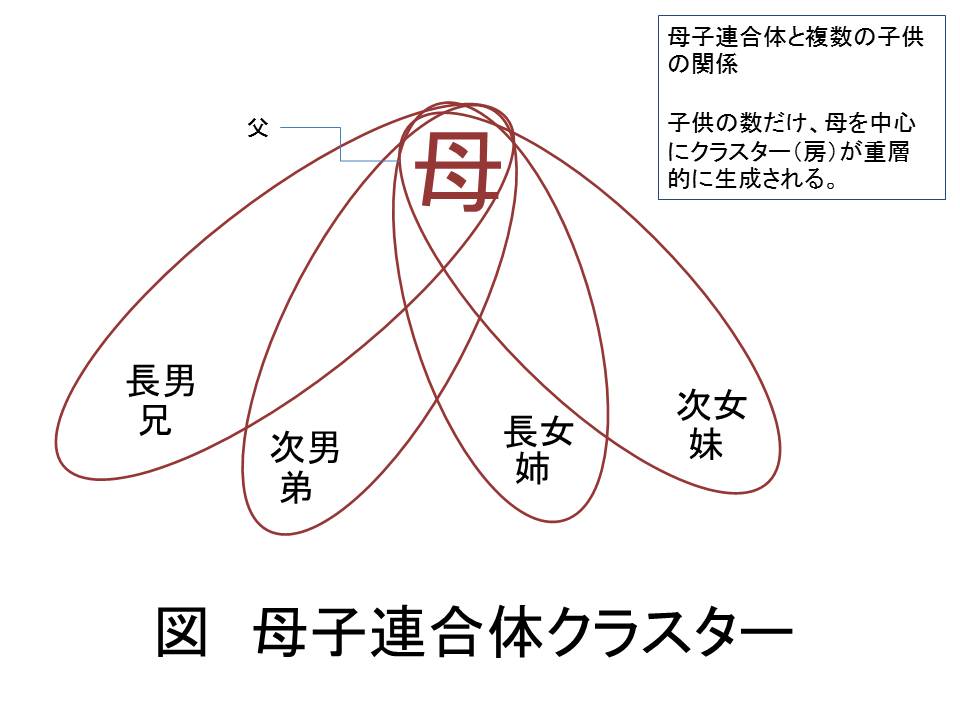
以上述べたように、日本では女性が「母子連合体」を形成して、社会の最もベーシックな基盤である家族を支配している。従来の日本の家族関係に関する「夫による妻の支配=家父長制」という現象も、実際は、上世代の母子連合体による、次(下)世代の母子連合体支配として捉えられ、それは、母子連合体の中における母による息子・娘の支配という関係を視野に入れることで、「時系列的に上位(前)の世代の女性(母性=姑)とその配下の子供(息子=夫、娘=小姑)による、下位(後)の世代の女性(嫁またはその候補)の支配=母権制」の現れとして説明することができる。
以上は、日本の家族について説明したものであるが、この「母子連合体」の概念は、育児における母子癒着の度合いが強い他の東アジアの社会(中国、韓国...)における家族関係にも応用可能と考えられる。
(初出2002年04月)
[要旨] 日本の会社や官庁は、その性質が母性的と捉えられます。筆者は、その際、成員の母親が、自分の子供(主に息子、男性)を組織へと没入させ、完全帰属させる心理を生み出しており、組織を「母性的」たらしめる原動力・エネルギー源となっていると考えます。母性的組織としての日本の会社・官庁を成立・維持させているのが、成員の母親たちであり、従来「日本的経営」と言われてきた経営のあり方の特徴は、「母性的経営」と呼ぶことができると捉えます。
◇
1.母性的組織と成員との関係
日本の会社・官庁といった組織は、成員同士の温かな全人格的一体感、包含感を重んじ、組織の「ウチ」「ソト」を厳しく峻別して閉鎖的な態度を取る、成員の組織への依存心(「寄らば大樹の陰」)を育むなど、成員に対して母親のように接する、母性的な性格を色濃く持っている。そうした組織のあり方は、例えば「母性的組織」と呼ぶことができる。
母性的組織に属するのは、その成員にとっては、あたかも実際の「母の胎内」に抱かれているのと同じような温かい一体感をもって捉えられる。
日本の会社・官庁組織は、それ自体が、一つの大きな「母的存在」として成員の前に現れる。日本人にとって、会社、官庁に就職することは、「母の胎内」に入り込み、その中に抱かれるのと同じ感覚である。
日本の会社・官庁組織の成員は、組織と全人格が完全に一体化しており、自分と会社を、ドライに切り離して考えることができない。日本の会社は、母性的組織なので、成員は全人格を拘束され、捧げなければいけない。成員は、自分の周囲を、母性的組織としての会社・官庁に完全に包囲されており、逃げ場がない。
日本男性は、会社・官庁で全てのエネルギーを使い果たす。会社が、自分の人生にとって100%である。その点、母性的組織は、成員の全てを包み、呑み込み、吸い取る、と言える。
全てのエネルギーを会社で使い果たした男性は、自宅に戻って、母や妻に対して「自分の世話をしろ」と寄っ掛かってくる。母の場合は、自分の子供だからその態度を十分許容できるが、妻の場合は、元は赤の他人なので、男性(夫)の態度に、気遣いが足りないと感じ、不満に思う。
組織で働く男性たちは、そもそも疲れていて気遣いする余裕がない。もともと、「自分のことを世話してくれて当然」と思っているので、思わず横柄な態度に出てしまう。
組織の成員が、組織に全人格を束縛されても、何ら意に介さず、むしろ満足感を得ているようなそぶりを示すのは、成員の持つ、組織に温かく一体感をもって抱かれたいという欲求が根底にある。それは、母親を求める欲求と根が一緒である。母性的組織の持つ温かい一体感が、成員を仕事から抜けにくくさせている。
成員にとっては、会社の組織目標に自己の人生目標が一致している。と言うよりは、会社の目標に自己を没入させている。組織目標に自分を合わせている。合わない面を無意識のうちに殺している。これは、一種のマゾヒズムである。
日本の会社、官庁のような母性的組織は、成員の全人格を呑み込み、掌握・管理し、成員の全エネルギーを吸い取る。成員に全エネルギー、全時間を自分のために費やさせる。
日本では、所属する組織に全時間を費やすことが理想的な男性像とされている。遅くまでサービス残業をして組織に尽くさせるような心理的な仕組みが出来上がっている。所属組織のための労働を最優先に考える「労働至上主義」、自分の所属する組織のことを何をさておいても第一に優先させる「所属組織第一主義」が、母性的組織のイデオロギーである。
成員は、組織の中で、自分の全てを消費・燃焼させる。残りは、もぬけの殻状態である。
一方、成員にとっては、母親に対するのと同じ、周囲との一体感を求める要求を、会社・官庁組織に属することで満たすことができるというメリットがある。会社・官庁組織が、母親の温もりと同じ快感を成員に対して与えている。成員は、自分が心の奥底で求めている温かな相互一体感を満たすために、積極的に、会社・官庁組織に入ろうとする、という側面もあることを忘れてはならない。
2.母性的組織と「専業主婦」
組織のために100%働いた成員は、自分で自分のことを世話する余力、余裕がない。そのため、組織の外側に成員のサポートをする役目の人間、成員の管理・世話役の存在が必須となる。それが、従来「専業主婦」と呼ばれてきた人々である。彼らは、母性的組織の外側にいながら、実は、母性的組織の申し子、協力者なのである。
専業主婦が家を守らずに外に働きに出る(兼業になる)と、組織成員の心理的バックボーンとしての役割がおろそかになる。組織成員のサポートが十分でなくなり、成員が不安を覚えて十分な働きができなくなると、組織で働く側からは見なされ、非難の対象となる。専業主婦がいないと、母性的組織は、成員のサポートが不十分になり、維持ができなくなるのである。
専業主婦は、組織成員を心理的に支えるために「100%専業」でなければならない。日本において女性一般の職場進出を阻んでいる理由が、実は日本の職場組織が母性的だからであって、成員に組織に対して100%の一体化・献身を求めるからだということになる。この現象は、キャリア指向の「女性」と「母性」的組織との対立として捉えられる。
日本において、女性に学歴が求められず、会社でも昇進差別があるのは、女性が劣った存在と見なされているからでは全くない。それは、若い女性に対して、「専業主婦」という、母性的組織の維持に非常に重要な役割を果たすことを受け入れる方向へと進路を取るように、「専業主婦」以外の道をわざと魅力なく見せるというやり方で社会的誘導が行われている証拠である。
専業主婦業の内容と学歴とは今のところあまり関係がないので、わざわざ高い学歴を取ってもあまり意味がない。また、母性的組織にとっては、大勢の女性たちに会社に居残られることで、成員の組織外サポート役としての「専業主婦」の供給が不足するのも困る(成員の結婚相手が「専業主婦」でないせいで、成員が組織のために全力投球してくれなくなるから)ので、わざと待遇を悪くしているのである。
ちなみに、専業主婦は、組織成員の全人格的な管理・制御を行う「管理者administrator」として、振るうことのできる実質的な権力は、管理される立場である男性を上回る。それは、特に、専業主婦が成員の母親である場合に言えることである。
母性的組織の成員が女性の場合、組織外のサポート役、世話役に異性の男性を見つけることが難しい。男性は、組織で働くことがデフォルトとして考えられているからである。組織外の世話役は同性の女性が想定されてしまう。そのため、組織で働き続ける、組織内で出世しようとする女性は、結婚出来ず、独身を貫く事になってしまいやすい。
そうかといって、結婚すると、男性に、組織の外でサポート役になることを求められ、組織内で働き続ける事を止めなくてはいけなくなる。これは、江戸時代の御殿女中以来の、母性的組織で働く女性が抱える根本的な課題である。
もちろん、組織外でのサポート・世話役(専業主婦)の役目には、家計管理の元締め、子供の全人格的統制・教育といった重要でうま味のある役得がある。特に、「母」になると、自分の子供(特に息子)を完全に「子分」にして操縦でき、会社や官庁に好きなように再投入できるようになるため、そのうま味が格段に上昇する。
3.母性的組織と成員の「母親」
従来は、専業主婦というと、妻の立場ばかりがクローズアップされ、関心を集めてきた。しかし、実は、母の立場の方がより重要である。つまり、自分の息子・娘を、組織に送り込む存在としての「母」である。
成員を、母性的組織の一員として、組織内での自己のエネルギーを完全燃焼へと向かわせるのに、成員の母親の果たしている役割が非常に大きい。母親こそが、自分の子供(主に息子、男性)を組織へと没入させ、完全帰属~全エネルギーを燃焼させる心理を生み出している。また、組織を「母性的」たらしめる原動力・エネルギー源となっている。母性的組織を成立・維持させているのが、成員の母親なのである。
母性的組織の主役は男性であり、母性の本来の担い手である女性ではないという、逆説的な現象が起きている。男性が母性的な行動を取っている。彼らは、母なる組織に一体感・甘えを求めて、没入・帰属している。そうした母性的な行動を取らせているのが、男性たちの母親である。彼女たちが母性的組織の本当の生みの親なのである。
母親がなぜ息子を組織に強く一体化させるかと言えば、母親が息子を自分の自己実現の駒、道具として使っているからである。母親は息子を組織へと駆り立て、組織内での出世競争に邁進させる。息子が組織内で偉くなる事が、すなわち、自分にとっての自己実現ということになる。妻も、母親と同じ考えを継承する。
母親は、また、息子以上に「(息子の)会社人間」である、という側面を持つ。彼女らは、息子の勤めている会社の業績や社会的なステータス(どの位、格が高いかなど)の上下に、まるでわがことのように一喜一憂する。母親自身が、息子の所属する組織と心理的に一体化したかのように振る舞うのである。
母親は、息子に組織に全人格的に一体化させて、息子が「自分(息子自身)⊆組織」と見なすように仕向ける。そして、息子に、「会社人間」として、所属組織の中で全エネルギーを出して組織の業績向上・格上げに寄与させ、他の成員との間で昇進競争をさせることで、息子の組織の格上げ=母親自身の格上げ、息子の昇進=母親自身の昇進、のように見なす。組織の社会的格式の上下は、組織成員の母親の社会的格式の上下と連動している。組織成員同士の昇進競争は、実はその背後に、彼らの母親同士の競争という側面を隠し持つと言える。
(注)この場合、上記の官庁・会社に入った息子を昇進に駆り立てる母親の行動は、「教育ママ」の取っている、自分の子供を少しでもいい学校に入学させるために、子供を叱咤激励する行動と共通する。
こうした母親による息子(=組織成員)の私物化やコントロールは、母親と息子が、相互に癒着し、強い絆で結ばれる「母子連合体」を形成しており(「母子連合体」の概念の説明は、本書の他セクションを参照して下さい)、息子が、程度の差はあれ、自然と母親の意を汲んで自発的に行動するからこそ可能となる。
母親にとって自分の子供、特に息子を活躍させるのに望ましい組織像を実現したのが、母性的組織としての日本の会社、官庁である。息子の組織での活躍が、そのまま母親の自己満足につながる。言わば、母性的組織は、組織成員の母親にとって、主要な自己実現の場なのである。一方、組織にとっては、成員の母親は、成員(自分の息子)に一生懸命組織のために働くように仕向けてくれる、組織活動のエネルギー源として欠かせない存在である。
日本の会社、官庁の性格が母性的なのは、成員がその母親の意を汲んで行動するため、相互の一体感や相互依存を重んじるなどといった、成員の母親の意向・価値観を反映した、母親好みの性格を持つように至ったと言える。その点、日本の会社・官庁の真の主役は、表面的に主役として振る舞っている男性成員ではなく、彼らを自分の自己実現の駒として、より上位の地位を目指して働くようハッパをかけている母親たちであると言える。母性的組織の真の支配者は、成員(社長、管理職~平社員)の母親である。
日本の会社、官庁は、自分の母親たちによって母性色=真っ赤な赤色に染められた「真っ赤な戦士」「赤色兵士、兵隊」(男性のことが多い)の着ぐるみのキャラクタが表に出て活躍しているさまを思い浮かべて貰えると分かりやすいかも知れない。活躍しているのは確かに男性メインなのかも知れないが、彼らは自分たちの母親によって、完全に赤い母性の色に染まり、その行動は、母性的、女性的色彩の強い、集団主義、和合、協調性の重視、年功序列、リスク回避メインのものになっている。この場合、男性自身が活躍しているというよりは、男性を母性色に染め上げた大本の母親、女性が実質的に活躍していると捉えることができるのではないだろうか。こうした(実質母性に支配された)上辺だけの男性の活躍の場である会社、官庁を、男社会だと呼ぶのは不適当と感じる。
また、母親は、組織のために100%エネルギーを尽くす自分の息子に対して、彼をサポートする次世代の世話役、専業主婦を、自分の嫁として求める。その点、キャリア志向の若い女性を邪魔する「専業主婦」「良妻賢母」イデオロギーは、実は、男性の「母」「姑」の要請に基づくものである、とも言える。要するに、フェミニストや女性学者によって批判されてきた、女性は専業主婦であれとする「専業主婦」イデオロギーは、実はキャリア志向の女性と同性である、(男性たちの)「母」「姑」=女性によって担われてきた側面があるのである。
また、会社で働く女性の中には、「男性が仕事に専念して、会社の重役とか偉い地位を独占している。自分たちは偉くなれない。」と男性を批判する人たちがいる。実際のところ、そうした、会社の仕事ばかりを一生懸命やって、家事をほとんど手伝わず、会社で昇進することに必死な男性たちを作り出しているのが、彼らの母親や、母親代わりの専業主婦指向の妻たちなのである。彼らの母親たちが、彼らに、もっと仕事をしてもっと偉くなりなさいとハッパをかけているのであり、彼らを必死になって働かせる影の原動力となっている。会社で働いていて、男性たちのせいで昇進できないと不満をもらす女性たちは、自分たちの本当の敵が、実は、自分たちと同性の女性たち=(男性の)母親たち、あるいは(男性の)母親代わりの専業主婦指向の妻たちであることに気づいていないのである。
会社の中で女性たちが昇進するようになるには、男性たちの母親や妻たちが、自分の自己実現の駒として男性たちをあてにするのを止めさせるしかない。つまり、男性たちの母親や妻たちが、自分の自己実現を、男性経由でなく、自分自身で行おうと決心させるしかない。彼女らが、男性を昇進へとせき立てるのを止めれば、男性は、必死になって家庭を省みずに働くのを止めて、自ずと仕事以外にも生きがいはいろいろあることに気づくだろう。そうすれば、従来男性にかかっていた仕事への圧力が弱まり、昇進へせき立てられる気持ちも弱まり、女性に道を譲るようになる。その分、女性が活躍して、昇進する余地がどんどん開けてくる。
要は、男性たちの母親(妻)が、息子(夫)の昇進を自分の生きがいとすることを止めさせるのが、日本の会社・官庁組織において、女性たちが(男性並に)昇進するようになる一番の早道と言える。このことは、今までほとんど誰も言及して来なかった重要事項である。
その他、自分では給与を稼ぐことをせず、息子(夫)の経済的稼ぎをあてにしてATM(現金を女性側で一方的に勝手に引き出せる、自動現金預け払い機)扱いし、少しでも多く稼いでくるように、尻を叩いて働かせ、昇進をせき立て、かく言う自分は、家庭の財布の紐をがっちり掌握しているのをいいことに、息子(夫)に最低限の小遣いしか渡さない一方、自分は握っている家計の弾力的運用で自由に高い買い物を楽しみ、なおかつ「三食昼寝付き」の生活を希望し、息子(夫)の稼ぎが悪くて、自分も働かなければならなくなったら、「甲斐性のない息子(夫)だわね」と悪態をつきながら、仕方なく働きますか、というところが本音の、専業主婦指向の女性たちが未だに数多く存在し(というか未だ主流であろう)、彼女たちが、男性を精神的余裕なく、給与稼ぎや昇進目当ての仕事に没頭させるのに多大な貢献をしているのである。こうした女性たちをなくすのも、日本の会社・官庁組織において、従来男性にかかっていた仕事への圧力が弱まり、女性たちが(男性並に)昇進できるようになる上で極めて重要であると言える。
ちなみに、日本において、従来、性別役割分業を支持し、妻に対して、「専業主婦になって欲しい。仕事して欲しくない。」と宣言する夫は、たいがい、上記の母親の欲求を、そのまま汲んで妻に対して反映しているのが実情であると言える。
4.母性的組織の持つ隠れた罠
母性的組織には、母親の視点から見ると、もう一つの隠れた側面がある。それは、息子を嫁から切り離すため、息子を嫁に奪われないようにするため、息子を嫁の待つ家庭に帰らせずに、組織(会社、官庁)に没入させる、という側面である。それは、母親自身と息子との母子連合体(相互癒着関係)を維持するとともに、嫁の世代における母子連合体を再生産する。
夫は「家族(妻子)のため一生懸命働く」と言う。彼らは収入を得て、家族の経済的な支えとなろうとして、仕事に自分の全時間を注ぎ込む。しかし、そのことが、夫の思いとは裏腹に、家族(妻子)とのコミュニケーション不足をもたらし、家庭内での妻子からの疎外につながっている。
実際のところ、夫の注意・関心は、自分の働く組織に全面的に絡め取られている。と言うのも、夫は、関心・注意を、自分の属する会社・官庁組織に専ら向けるように、母親によって無意識のうちに仕込まれているからである。夫の家族(妻子)とのコミュニケーション不足や、家庭内孤立は、(息子に自己実現の夢を託すとともに、息子と嫁を切り離そうとする)夫の母親によって暗黙のうちに仕組まれた事態である。
そうした、(自分の所属する会社を一次として)自分の家庭(妻子)を二の次にしてしまう後ろめたさが、「自分は家族のために一生懸命自分を犠牲にして働いているんだ」という言い訳になる。そして、家族のために働いているという言説の正当化のために、自分の家庭に対して及ぼす力を最大限に見積もろうとし、それが、自分自身を家父長と強迫的に見なそうとする原動力となる。
単に、夫-妻のラインを見ただけでは、夫妻のコミュニケーション不足、夫によるコミュニケーション能力の欠如としか見えない現象が、実は、母-息子(=夫)のラインに注目する事で見えてくる。なぜ、息子=夫が一生懸命会社勤めをするか、なぜ妻とコミュニケーションしないかが見えてくる。
緊密な母子一体感のうちに、母親が息子(自分の子分)に対して、母親自身の自己実現の手段として、組織で一生懸命働いて出世・昇進するようにハッパをかける。組織で働く息子は、母の自己実現のための手先である。それとともに、母は、息子に組織で全ての力を吐き出させ、妻=嫁との間でコミュニケーションを行うためのエネルギー余力が残らないようにして、夫妻(息子と嫁)間を分離させようとする。息子は、こうした母の戦略に、気づかぬ内にまんまと嵌まっているのである
5.母性的組織と白紙採用・終身雇用
母性的組織は、内部で強固な(成員相互の)一体性・同質性を保持する分、対外的には閉鎖的であり、集団内と外とを厳格に区別し、ヨソ者に対して門戸を閉ざす。
例えば、日本における中央官庁や大企業では、成員の採用の機会は新規学卒一括採用がほとんどで、白紙状態でまだどの社会集団の色(しきたり、組織風土など)にも染まっていない若者に対してのみ門戸を開く。この慣習は「白紙採用」という言葉で言い表すことができる。そこでは、本格的な中途採用の道は閉ざされている。純血性を保った自集団(「ウチ」)内で他集団に対抗する形で強固に結束し、内部に縁故(コネ)の糸をはりめぐらす。
日本における母性的組織は、強固な閉鎖性、純血指向性を持ち、基本的に新規学卒一括採用の際しか外部に対して採用の門戸を開こうとしない、中途で所属する社会集団を変更することを許さない。学生は事実上一生に一回しか、中央官庁、大企業といった、社会的に大きな影響力を持つ組織に入れるチャンスがないので、そこでうまく希望の組織に入ることができるように、学歴や、学閥のようなコネの獲得に躍起となるのである。
また、いったん集団に入ると、定年やリストラなどで用済みになるまでその中にずっとい続ける(浮気をしない)こと=「終身雇用」が要求される。
白紙採用や終身雇用がなぜ必要か?組織内成員の同質性を確保し、成員間に強固な一体感を持たせることを可能とするために必須である。
いったんある組織に入った成員は、全人格的にその組織固有の色に染まることになる。この場合、「色」とは、その組織固有の規範、しきたり、慣習、心理的風土といったものを表している。
成員は、「白紙」の場合のみ、その組織固有の「色」に染め上げることができる。同じ「色」を持つ成員同士は、互いに同質であり、強固な一体感で結ばれる。こうした組織内の同質・一体性を強く求めるのが、母性的組織の特徴である。そうした点から見ると、組織成員を同一の色で染め上げる上での前提条件となる「白紙採用」は、組織成員の同質性・一体性を確保しようとする母性的組織にとって必須であることが分かる。
成員が既に「他の色付き」の場合には、既に付いている色がじゃまをして、組織本来の色に染め上がらないため、「色」の面で他成員との間の一体性、調和を乱すこととなる。母性的組織では、「他の色付き」は、そうした点で、本質的に忌避されることになる。
白紙状態の若者は、一回ある組織に入ると、その組織固有の色に染まった「色付き」になる。そうなると、他の組織にとっては既に「他の色付き」となり、忌避すべき存在となる。そのため、いったんある組織に入ってその組織固有の色が付いた者は、他の組織に移ることができず、一生、最初に入った組織で過ごさなければならない。
母性的組織においては、自分たちとは違う「他の色付き」のヨソ者は、自分たちとは異質な分子であり、自分たちと行動様式が異なり、何を考えているか分からないので安全でない、一緒になると自分の属する集団のしきたりや風紀を乱すことを平気でされるのではないかと不安で、安心できないと考える。「他の色付き」のヨソ者を中に入れることが、組織成員相互の一体感の保持に悪影響を与えるという母性的な心配が、気心の知れた安全な身内だけで身辺を固めようとする、閉鎖的な風土を生み出す要因となっている。
なお、この「他の色」付きの忌避は、身内集団内部の一体感を保つため、ヨソ者が入るのを防いでいるという点、母性が好む互いの一体融合性を維持しようとする働きに通じるものがある。
成員は、ある組織の色に染まると、他の組織には、「既に、他の色付きである(白紙でない)」と見なされ、自分たちとは違う「色」を持つ者=組織の同質性、調和を乱す者として疎んじられ、移ったり入ったりすることができない。そのため、よくも悪くも最初に入った組織に「飼い殺し」になり、一生をその組織で過ごすことになる。これが母性的組織において「終身雇用」現象が起きる真の原因である。
成員の「終身雇用」は、成員の「白紙採用」と表裏一体の関係にある。この両者は共に、母性的組織における成員の出入りを決定する慣習であり(「白紙採用」が組織への「入り」、「終身雇用」が組織からの「出」に関わる)、互いに切り離せないものである。その点、「白紙採用」も「終身雇用」も、両方とも組織の母性性を保つ上での根幹に関わる重大な特徴である。
こうした、「組織内=同一色への染め上げ」へのこだわりが、日本の中央官庁・大企業のような母性的組織において、成員の中途採用を妨げる大きな要因となっている。
また、ある組織にいったん入ってその組織の色に染まると、他組織への転進が効かないという現象は、「どの組織に入るか」という最初の選択で失敗した若者にとって、そのままでは人生のやり直しが効かないことを意味する。最初の組織選択で失敗した者は、一生後悔しながら、その組織に「飼い殺し」になる他ない。組織から出て、「ベンチャー起業家」として自分で一旗上げる途も存在するが、困ったことに、日本のような母性的な(女性優位の)風土の社会では、「ベンチャー」は、冒険的過ぎる、危険すぎるとして嫌われ、十分な社会的サポートが得られないのが現状である。
こうした「組織選択における、やり直し不能性」は、母性的組織の抱える大きな問題点の一つである。
こうした「終身雇用」「中途採用の忌避」といった性質は、成員間の全人的一体感を重んじる閉鎖的な母性的組織において本質的、不変的なものであり、欧米流の父性的組織(成員の出入り流動性、組織の開放性を重んじる)が優勢になった際に一時的になりを潜めるだけで、その本質は変わっていないので、時流の変化に伴い、再び不死鳥の如く生き返ると考えられる。
6.「母性的経営」 -組織分析における「母親中心」視点の重要性-
日本の会社・官庁の組織が母性的となるのは、組織成員が母親の色に強く染まっているためであり、成員の母親たちの力が強く作用している証拠である。組織成員は、母親の意向を汲んで仕事をしている側面が強い。日本の会社・官庁組織は、男性たちが主に活躍しているので、男性中心と一見間違えやすいのであるが、実際は、彼らの母親の強い息がかかった、彼らの母親の意向によって左右される、実質的には母性中心(と言うことはある意味、女性中心とも言える)の組織なのである。
要するに、男性が彼ら自身の母親の支配を受けているため、いくら要職を男性が占めていても、組織は母性的となるのである。
欧米のように、ドライな父性的社会では、父親=男性を、社会の中心に据えて、社会を分析するのが有効である。しかし、それを、今まで日本の学者たちがしてきたように、欧米生まれの「家父長制」社会の理論を、日本のようなウェットな母性的社会にそのまま当てはめようとすると、社会はうまく分析出来ない。
日本のようなウェットな母性的社会では、母親役の女性を、社会の中心に据えて、母親の社会に及ぼす影響を常に念頭に置きながら、社会を分析すべきである。すなわち、母親を分析対象となる社会の中心に据えて考える、「母親中心の視点」が求められるのである。それは、母性的組織の分析においてもそうであって、組織の外にいて、組織とは一見関係ないはずの、組織成員の母親の持つ、組織に対する影響力の巨大さを、今後はもっと重視すべきであろう。
従来言われてきた「日本的経営」は、その経営のあり方が、組織構成員の母親の息のかかった、母性の影響下にある「母性的経営」であり、その特徴(集団主義、年功序列、終身雇用、護送船団、規制と談合・・・)は、総じて女性的・母性的な価値観に基づくものである。一方、バラバラに独立した個人の自由競争に基づく「欧米的経営」は、「父性的経営」と呼ぶことができる。今後は、日本的経営の分析において、その女性的・母性的性格により重点を置くことで、経営組織のあり方をより的確に把握できる、と言える。
日本の官庁・会社のような、成員相互の一体感、対人関係や協調性を重んじるウェットな組織は、もともと、個人主義的で互いにバラバラなのを好む、その本質がドライな男性にはとうてい作れない。こうした日本的経営組織の実現には、ウェットさを備えている女性、母性の強い力が必要なのであって、その点、日本的経営組織の真の作り手、創造者は、成員たちの母親であるということができる。
7.会社マザコン
日本の男性は、所属する会社(や官庁)に、心理的に強力に帰着、癒着している。そこには、会社との強力な一体化、会社への甘えが見られ、会社に対して、強い紐帯を感じていると言える。というか、所属する会社無しには、何もできない、自我が成り立たない感覚がある。
例えば、日本男性では、定時後に彼女とデートの約束をしている時に、会社から追加の仕事を命じられると、デートをキャンセルして会社の仕事をこなすということが、まだ多く見られる。この場合、男性は、彼女よりも、会社を、心理的に優先させており、会社が最終的な心理的帰着の対象となっていると言える。
日本男性が、会社で働くことをひたすら優先し、家庭を省みない、育児に参加しないのも、彼が、会社に心、魂を完全に奪われ、支配されているからだと言える。
この場合、一体化、甘えの対象である会社は、当の男性にとって、母親と同じ役割を果たしていると言える。対象との一体化、甘えは、父性ではなく母性につながるものであり、マザコン男性における母親の役割を、会社が果たしているのである。こういう日本男性の会社に対する、会社を母親代わりとしてその中に帰属しようとする、根本的な心理的依存は、「会社マザコン」といった言葉で呼ぶ事ができる。
8.会社母艦説
日本男性は、会社で働く、給与を稼ぐことに専ら心を奪われ、家庭を省みない、重んじない。それは、彼にとって、家庭ではなく、会社が「母艦」だからである。
専業主婦の妻とかからの見方だと、会社は、自分の運営する家庭から会社に出かけ、仕事をして、また自分の家庭に帰ってくる存在だと考えられている。これは、夫を、家庭という「母艦」から、飛行機として飛び立って、また舞い戻ってきて、休息する存在と捉えるものであり、こうした考え方は「家庭母艦説」と呼べる。
しかし、日本男性の会社への癒着ぶりを見ていると、上記の「家庭母艦説」は、彼には当てはまらないと考える方が理に適っている。この場合、日本男性が実際に取っているのは、「会社母艦説」(ないし職場母艦説)であると考えるべきである。
「会社母艦説」とは、会社こそが、自分の本質的に帰着、癒着する対象であり、家庭は、仮の帰着場所、立ち寄り場所に過ぎないとするものである。要は、自分が、会社という母艦に直接つながっている一級の主要構成員であり、一方、自分の家族は、そこに依存的にぶら下がる、厄介になっている二級の、劣った構成員と見なす考え方である。自分が主である家庭を、自分が所属する会社という母艦に結びつけ、その配給管、パイプ役を担い、会社という主要な幹から、家庭という従属的な枝に、養分を供給する元締めの役割を担っている、という高いプライドが、そこには存在する。
まず会社があって初めて自分がある、という「まず会社ありき」という見方を取ると共に、自分の家庭は、自分という会社からの養分を供給するパイプ役無しには成り立たないんだという強い自負、自分の家庭に対する優越感が、日本男性には見られる。
生きていくための養分をくれる会社を最も重要な存在と考えて、そこにしがみつくと共に、自分の家族をそのおまけと考え、自分の役割を、会社から配給される養分を家族に与える主要なパイプ役と捉える「会社母艦説」こそが、日本男性が、会社に対してやたらとヘコヘコすると共に、自分の家族に対して、何事も会社優先で、高圧的に接し、尊大な態度を取る理由である。
この場合、日本男性とその家庭に対して、生きていくための養分をくれる会社は、ちょうど、胎児にへその緒を通じて養分を与えてくれる母親と同じ存在であると言える。この点、日本男性とその家族にとって、「会社=母」なのである、と言える。会社のために我を忘れて一生懸命に会社の発展のために尽くそうとする、何事も会社、職場第一の日本男性は、「母なる会社」にどっぷり浸って生きているのである。
9.母性的組織からの男性解放
以上見てきたように、日本の男性がよりどころとしてきた会社・官庁の組織のあり方は、実は、彼らの母親(や母親代わりの妻)の意向に沿うものとなっている。日本の会社・官庁は「母性」によって牛耳られている面が強い。男性たちが、そうした会社組織の「母性による支配」を終わらせ、会社組織からの自立を図るには、根本的には、組織成員である男性自身が、自分の母親との間の強力な癒着を何とか断ち切って、「母子連合体」を解消させることで、母親によって所有され、母親によってもっと働け、先へ進めと尻を叩かれる「ダービー馬」のような立場から自由になるしかない。
10.母性的組織への女性進出
従来の日本では、女性は、自らは組織の内部に止まらずに外に出て、「専業主婦」として、男性(息子、夫)を組織に送り込んで業務に邁進するように仕向け、管理することに専念してきた。
しかし、専業主婦の仕事は、家事の省力化や、教育機能の学校への委託が進むにつれて「空洞化」が進み、女性たちにとって、次第に「やりがい」が薄れた魅力のない仕事となりつつある。また、専業主婦たちは、彼女たちの居場所が「家庭内」という、外界から遮断された密閉空間となっていることに息苦しさを感じている。
日本の女性たちは、息子や夫を自らの操りロボットとして操縦して組織で活躍させる、従来の「専業主婦」になることによる「間接的な自己実現」のやり方よりも、自分自身が直接会社や官庁に乗り込んで、そこで自ら活躍し、自分の手で業績をあげる、「直接的な自己実現」に、より生きがいを感じるようになっているのは確かである。女性たちは、その生涯を、男性たち同様、組織人として過ごすことを求めている。
彼女たちは、子育てで主導権を握ることにより、従来の専業主婦同様、自分の子供を自らの操りロボットとして出世競争に邁進させて自己実現を図るとともに、自分自身も組織で働いて業績をあげることで自己実現を行うという、「二重の自己実現」を狙おうとしている。
しかるに、従来の日本の官庁・会社組織で活躍しているのは専ら男性であり、女性は男性の補助的作業に回ることが多かった。それは、女性は「専業主婦」になることを求められていたからであり、女性の業務は、女性が「専業主婦」になって退職するまでの間の短期間の腰掛け業務と捉えられていたため、重要視されなかったのである。
日本の女性たちは、既に本腰を入れて、官庁・会社業務への進出を始めているが、官庁・企業組織のあり方は、依然として旧来の「専業主婦コース」を推奨するものとなっている。このミスマッチを是正するため、ごく近い将来、日本の経営組織のあり方を、女性が一生組織人として働き続けることができるように根本的に見直すことが必要となる。
母性的性格・風土を持つ「母性的経営体」である日本の官庁・会社組織は、本来、男性よりも女性により適した組織であり、現在組織の中で大きな顔をしている男性が働くよりも、女性が働いた方がより優れた業績をあげることができると考えられる。
今まで、日本の会社・官庁の風土を、「ムラ社会(日本の伝統的な農耕村落共同体)的」として、不愉快だとして批判をしてきたのは、ほとんど男性であり、女性は批判していない。これは、女性にとって、「ムラ社会」が、女性にとって居心地のよい、女性、母性向きの社会であることを意味している。
従来男性が仕切ってきた日本の官庁・会社組織で、スムーズに女性が主導権を握り、男性を凌ぐようになるには、女性が単に組織内で男性に負けない業績をあげるだけでなく、女性が、組織の中で「母親」「姑」「姐御」的存在になることで、男性たち(上司も部下も)を、母親代わりに心理的に依存させ、自分の言うことを聞かせるように仕向ける、精神的・心理的戦略が重要である。
母性による支配下で成長してきた日本男性は、年配、年下を問わず、「母親」「お袋」「姐御」的な、自分たちを強い一体感で包み込んで依存させてくれる存在に弱い。そこで、女性たちが男性たちを、自分たちの「大きな子供」扱いすることで、男性たちは簡単に女性の軍門に下り、組織上の重要ポストを女性たちに譲ると予想される。これは、女性の年齢が男性よりも年下である場合にも当てはまり、彼女たちは、母性的態度を男性たちに対して取ることで、「リトルマザー」「小さな姐御」として自分よりも年上の男性を精神的に支配可能である。
こうした、組織における、女性による男性の「母性」を通じた支配は、女性が専業主婦を止めることで、男性が感じる心理的バックアップ感の不足を補う効果を持っている。要するに、男性が従来専業主婦である自分の母親や妻に潜在的に求めていた心理的依存、甘えの感情を、職場の(特に上司の)女性に向けるように仕向けることで、女性たちが専業主婦でなくなっても、男性たちが心理的支えを得て困らなくなるようにすることができる。
従来、会社・官庁組織で自己実現を図ろうとする女性たちにとってネックだったのが、出産・育児に忙しくて、いったん退職・休職せざるを得ないことであった。
女性が生涯を組織人として業績をあげることに注力できるようにするには、この退職・休職がもたらすハンディをなくすことが必要である。それには、女性に中途採用、再雇用の道を幅広く用意することが、会社・官庁の経営上メリットとなることを本格的に実証する必要がある。つまりいったん出産・育児のために退職した女性たちも、社員・職員として組織中枢部で再雇用すれば、従来の男性同様の重要な業績をあげ得るのだ、ということを実例で示す必要がある。
女性たちは、いったん出産・育児で退職した女性を経験者待遇で再雇用した方が、一から新卒採用者に業務を覚え込ませるよりも、即戦力の正社員として使えることを、自ら示すことが必要である。あるいは、同じフルタイムで働いてもらうなら、男性社員より、女性社員を雇った方がより有能であり、より会社・官庁の業績向上に役立つことを示す必要がある。
こうしたことを実証するには、実際の官庁・企業の組織を使った「実験」が必要である。実際にいったん出産・育児のために退職した女性社員・職員を再雇用して組織の中枢で数多く働かせる官庁・企業を「パイロットケース」として数多く用意して、そうした「パイロットケース」組織の中で彼女たちがあげる業績が、従来の男性中心組織があげる業績に見劣りしないことを、実証データとして示せれば良い。こうした実験には、行政による費用・制度両面での援助もある程度必要となって来よう。
あるいは、女性たちがそもそも出産・育児に伴って退職・休職をしなくて済むようにする手も考えられる。そのためには、働く女性たちが、組織人、会社人間として組織で働きながら、なおかつ子育てができる環境を、女性主導で用意する必要がある。例えば、各職場とインターネットでつながった、24時間利用可能な保育所、幼稚園、小中学校を設け、そこに自分の子供を通わせ、インターネットを介して子供たちとコミュニケーションを取ることで、女性たちが職場にいながらにして、我が子へのフォローを可能にすることが考えられる。そうすることで、女性たちは、従来我が子との間形成してきた「母子連合体」を維持したまま、組織人として仕事に打ち込むことができる。
女性たちが、育児にも、仕事にも両方打ち込める環境を作り、女性の自己実現を支援することで女性の力を引き出すことが、日本の経営組織の体質強化には必要である。日本の「母性的」な経営組織には、従来の男性よりも、母性の担い手である女性の方がより組織の体質にマッチしており、女性主導で組織運営が進む方がより生産性が上がることが予想されるからである。母性的体質を持つ日本の官庁・会社では、いったん女性の組織中枢への進出が進めば、男性が女性たちに経営権限を譲らざるを得ない事態は、比較的短期で訪れると考えられる。
そのためにも、女性たちは、従来のように、単に結婚しない、子供を産まないなどといった消極的・受動的な抵抗ばかりするのでなく、自ら積極的に、官庁・会社に対して、「保育所の充実、24時間保育の実現」「組織中枢での再雇用」などを、社会運動の形で働きかけると共に、「自分たち女性を組織で使えば、確実に業績が向上しますよ」という証拠を見せる必要があると言える。
社会運動をするに当たっては、従来、家庭の中でくすぶっている専業主婦たちを取り込めるかどうかが鍵となる。「組織人として働き続けることで、今までのように家庭の中にとどまるだけよりも、こんなに、よりよい生活と自己実現が得られますよ。」という明るい青写真を、彼女たち専業主婦に対して、実例を示して説得する必要がある。
また、日本の女性学には、従来のように「性差別はいけません」といった、男性たちを責め続けるネガティブなキャンペーンを張るばかりでなく、「自分たち女性は、組織の中で、男性に負けないor男性にできない高い業績をあげる能力がありますよ。それは、出産・育児による退職後の再雇用時にも有効ですよ。私たちを、組織の中で積極的に利用しないと損しますよ。」ということを実証するポジティプな姿勢が、今後求められると言えよう。
なお、女性の負担となっていた食事作りや掃除、洗濯のような家事についても、例えば、栄養士の監修による弁当をコンビニで安価で販売するようにしてそれを購入すればよいようにしたり、洗濯・掃除ロボットを導入することで、家事雑用をできるだけなくすようにする必要がある。そのためには、「家事雑用をしない主婦は主婦にあらず」という考え方をなくし、主婦の仕事を、家計管理、子供の教育といった根本的に重要なものへと集約することが必要である。
この場合、男性は今まで専業主婦をデフォルトとして育ってきているので、家事をしない女性(妻)に対して違和感を感じて「もっと家事をしろ」と文句を言うことが考えられる。それについては、男性の母親である姑の世代の女性が、積極的に外に働きに出て、家事をアウトソーシングする姿勢を見せれば、母親の子分である男性たちも従うようになると考えられる。このためには、姑が、専業主婦がメインだった世代から、職業人、組織人がメインである世代へと、世代交代をする必要がある。姑が外働きをすることが当たり前となっている状態への世代交代には、あと10~20年位かかるかも知れない。
日本の男性にとって、女性たちが上記のような戦略に出て、どんどん組織内で昇進して、自分たちを追い抜くようになっていった場合、どういう対応をしたらよいであろうか?これは、難しい課題と言えよう。一つ言えることは、日本男性は、従来のような「お母さんの手下」的存在でいるままでは、いつまで経っても社会的に浮かばれないということである。「母との精神的決別」こそが、日本男性を新たな精神的段階へとステップアップさせるための鍵なのではないか?要は、母への親孝行のために働くのではなく、自分自身のために働くのである。そうしたドライな風を心にまとうことが、日本男性が働き手として真に成熟して、女性に対抗していくために必要である。それは、「浪花節的」「ムラ的」と言われた従来の日本の会社組織風土を、ドライに塗り替えることにつながっていく。男性たちによる「会社組織風土のドライ化」こそが、真に日本男性を会社組織の中で、女性と互角に渡り合っていくことを可能にするための条件と言える。
(初出2003年06月、2013年12月追加)
[要旨] 日本では、以前から母性が父性よりも優位にあると主張する「母性社会論」が存在します。母性は女性性の一部であり、母性が父性よりも強いとする母性社会論は、日本における女性優位を示すと考えられます。しかし、日本のフェミニストたちは、なぜか、女性が優位であるという結論を決して導き出そうとしません。筆者は、その原因について、嫁姑の対立という、女性内部の対立があると考えます。
◇
日本では、母性の父性に対する優位を主張する日本=母性社会論が、松本滋や河合隼雄らによって、以前から唱えられて来た。
母性は、女性性の一部であり、母性が父性よりも強いとする母性社会論は、女性優位を示すと考えられる。
これに対して、日本のフェミニズムは、女性が強いという結論を導き出そうとしない。むしろ、母性は、女性への育児の押しつけとなり、会社とかでの女性の自己実現を阻む、有害なものであるといった主張を展開している。いわば、女性と母性を互いに敵と見なす、対立させて捉える見方が横行しているのである。
実際のところ、日本社会を強い母性の力で牛耳る子持ちの年長女性、特に姑においては、女性と母性はスムーズに統合されているのであり、対立は特に見られない。
日本の女性学者やフェミニストによる母性の敵視は、実際のところ、母性を肯定し、日本女性の強さを表す日本=母性社会論が、女性が弱い立場に置かれていることを前提として発展してきた日本のフェミニズムの存在理由を根本から脅かすものであり、日本の女性学者やフェミニストたちは、触らぬ神に祟り無しということで、日本=母性社会論を無視したり、わざと歪曲した見方をして、正面切って扱うのを避けているのである。
そのため、母性社会日本をリードしている姑の権力の強さとか、今までほとんど日本の女性学で取り上げられないという、異常事態を来しているのである。
(初出2000年07月)
日本女性による家族制度批判が行われる場合、女性は、自分を嫁の立場に置いて、制度を批判する。
姑の立場に自分を置いて、家族制度を批判する女性を見たことがない。
姑の立場では、家族制度は、それなりに心地よい、批判の対象とはならないものなのではないか?
同じ女性なのに、姑と嫁という立場が違うと、協同歩調が取れない。
従来の日本のフェミニズムは、嫁の視点ばかりで、姑の視点は取ったものは見当たらない。
同じ女性なのに、姑は、解放の対象からは外れている?解放できない=十分強くて、する必要がない、というのが本音であろう。
そこには、根底に、嫁姑の対立という、同性間の対立がある。一方、同性間の連帯意識というのが建前として存在するので、対立を公にできない。
嫁の立場の女性から見ると、姑と、その息子=夫が、一体化して、嫁に対して攻撃をしかけてくる。
姑は、その家では、しきたり・慣習に関する前例保持者、先輩としての年長女性である。
姑は、嫁や息子に対して、先輩、先生である。家風として伝えられて来た前例を教えるとき、威張る。威圧的になる。
嫁の立場に立つ女性は、本来は、男性=息子も支配している、姑を、自分を抑圧する者として、批判の対象とすべきなのではないか?
女性は、自分と同性の姑の批判ができない、しにくいから、代わりに、男性(姑の息子)を批判するのではないか?
同性間では、見かけだけでも仲良いことにしておきたい、複雑な事情があるのだろう。
日本のフェミニストによる「日本家族=家父長制」攻撃の本当の目標は、夫=男性ではなく、姑=同性である女性の権力低下にあるのではないか?本当は、「日本家族=(姑=)母権制」攻撃の方が当たっている。でもそれでは、女性の地位を高めようとする、フェミニズム本来の目的と矛盾する。
「日本=母性社会」は、女性を母性の枠内に閉じこめる、いけない考え方であるとするフェミニストによる攻撃も、まだ子供を産んでいない嫁の立場からは理解できるが、子供を産んで自らのコントロール下に置くことに成功している姑の立場からは理解不能である。
同じ女性なのに、嫁の立場と姑の立場とで、まるで連携が取れていない。フェミニズムは、同性間の対立をどう取り扱うのか?
フェミニズムは、弱い立場にある女性しか対象にできない限界がある。姑のように、強い立場にある女性をどう取り扱うのか?
(初出2000年07月)
姑は、血縁(親子関係)による結合に基づいた家風の先達者として、嫁を支配し、嫁は姑に服従する関係にある。
「日本家族=家父長制」論者は、
(1)この姑との間の支配服従関係を、夫による支配と勘違いした。
(2)女同士の対立を表に見せようとしない。女同士(嫁・姑)が結束しているように見せかける。
夫婦は、異性間の結合により互いに引きつけ合う。一方、母子、親子は、互いに共通な遺伝子や価値観の共有による一体感により、互いに引きつけ合う。
血縁による結合(親子関係)と、異性間の結合(夫婦関係)とが互いにライバル・拮抗し、互いに強さを強めようとする。強い方が主導権を握る。
夫は、どちらにも深くコミットする、付くことができず振り回される。ただし、時には、漁夫の利を得ることもある。
(初出2000年07月)
マザコンは、母親による子供の一体支配を、子供が母親の意を汲んで自発的に受け入れている状態のことである。母性の力が強い日本では、結構メジャーな現象であると思われる。
日本においては、マザコンは、女性の立場の違いから、同一の女性にとって否定的にも肯定的にも捉えられる。
これから結婚する、あるいは結婚した嫁の立場の女性にとって、マザコンは、望ましくない、否定すべきものである。
自分の彼氏や夫が、姑と親密にくっついて、姑の同盟軍となって、自分のことをあれこれ批判したり、支配しようとするのに反発したり、彼氏や夫がそうなるのを避けようとして、「マザコン男はダメ」と、マザコンを必死になって批判する。
ところが、そのようにマザコンを批判していた同じ女性が、自分の子供、特に息子を持つと、子供が可愛くて、子供との一体感を楽しみにするようになり、子供を自分の思い通りに動かしたいという支配欲も働いて、子供がいつまでも自分の元にベタベタ愛着を持ってくっつく状態=マザコンを肯定的に捉えるようになる。「マザコン歓迎」となるのである。
自分の姑や夫に対しては、「マザコン反対」で、自分の子供に対しては「マザコン賛成」という、相反する立場を、両方場合に応じて便利に使い分けて、矛盾に気づかないか、気づいても開き直っているのが、日本の女性の現状であると言える。
(初出2007年05月)
稲作農耕文化は、マザコン製造機である。社会において、女性、母性の力を強め、子供たちが皆その影響を受けるからである。
一方、遊牧、牧畜文化は、ファザコン製造機である。社会において、男性、父性の力を強め、子供たちが皆その影響を受けるからである。
(初出2011年9月)
マザコンは、従来、マザー・コンプレックスという言葉の略語として用いられてきた。
しかし、それとは別に、マザーズ・コントロール(母親による制御、母親による支配)という言葉の略語としても使用することができる。
(初出2012年6月)
日本の著名な教育評論家である尾木直樹は、そのオネエ言葉から、「尾木ママ」と呼ばれ、社会的に親しまれている。彼は、本来男性なのに、母性の体現者となり、そのことがごく自然なこととして、日本社会に受け入れられているのである。これは、日本社会で母性が強く、男性に対して強く影響していることの証拠である。あるいは、日本社会において、男性が母性化しやすいことの証拠であるとも言える。
(初出2011年9月)
子育てこそが、日本社会を女性が支配するための最重要キーワードである。あるいは、子育てを女性が担っていることが、女性が日本社会を支配することができる根本理由である。
欧米女性は、子育てを軽視して、子育てよりも自分のキャリアを大切にせよと主張するが、これが、社会において、欧米女性が弱い根本理由である。
日本では、女性が、子育ての役割を独占している。日本の女性たちは、子育てに多くの時間を割いて、母親、教育ママとして、自分の時間を惜しみなく投下している。
日本では、女性と、その子供(特に息子)が一体となって、自己実現に取り組んでいる。子供(息子、娘)の自己実現が、すなわち母親の自己実現となる。例えば、息子が成功、出世すれば、それがそのまま母親自身の成功となる。
日本の母親たちは、こぞって、自分の子供を、自分の思い通りに操縦するのに必死となる。自分の思い通りに操縦することで、子供が母親の意のままに動くことにより、母親の意思決定を社会全体に、全面的に反映させることに成功している。そこには、母親が子供の独占的支配者となっている実態があり、母権社会の表れとみることができる。
(初出2012年6月)
お母さん(実母ないし妻)に、食事や服装の用意、洗濯まで、身の回りの世話一切をやってもらっている日本の男性は、マザコンだ。
いくら、自分の稼いだ給与を実家に入れているからと言って、お母さんに、炊事洗濯から家計管理も含めて生活全般を依存しているのは、お母さんに生活全体を握られ、包含され、支配されている訳で、実質マザコン状態なのである。
重要なのは、職場が男中心で動くという、いわゆる「男社会」の立役者が、実は、そうした男性の母親(、妻)=女性だということだ。
男性の母親が、男性の身の回りの世話をかいがいしく全部してあげて、男性が生活面で母親無しで暮らしていけないように依存させることで、男性が母親に精神的に支配される事態が生じている。
男性がやたらと会社でやたらと仕事熱心なのも、自分の母親に「頑張って昇進しなさい」とハッパをかけられていることと関係がある。
男性は、その母親の自己実現の道具、操りロボット、愛玩対象となるペット、奴隷なのだ。
「母の奴隷」、それが、日本の男性の実像だ。
男性が勉強や仕事に専念して、それ以外に関心を向けさせないようにわざとし向けているのが、日本の母親だ。
日本の母親にとって、自分の息子は、受験競争、会社での昇進競争にまい進させる「ダービー馬」と一緒だ。息子が、そうした競争に勝って出世して社会的勝者となることが、すなわち自分の自己実現が果たされることと一緒だと考えて必死に息子の尻をひっぱたく。
そのため、息子は勉強人間、仕事人間と化すのだ。
会社はそうした「ダービー馬」と化した息子たちで溢れている。「男社会」の出現だ。ひたすら会社の仕事に専念する男性=ダービー馬たちの集まり=「男社会」を生み出しているのは、その母親たちなのだ。
日本の母親は、炊事、洗濯といった家事や身の回りのことに対して息子が余計な気をかけることで、本来の受験競争、会社での昇進競争に遅れてしまうことを防止するため、必死になって、息子の身の回りの世話をかいがいしく焼こうとする。
そうした母親の姿勢が、息子が、勉強、仕事以外のことをやらなくなり、身の回りのことを、財布とかも含めて全て母や妻にやらせようとするあり方をもたらす原動力となっているのだ。
息子に競争に打ち勝てとハッパをかける日本の母親は、会社で、部下に成績を上げろとハッパをかける上司と同じだ。母親が上司、息子が部下だ。
そうやって必死に息子=「母親が自分の生涯を賭けたダービー馬」の身の回りの世話をする母親の姿が、息子から見ると、自分に無償の愛を提供する理想的な恩人に見えるのだから皮肉なものだ。
妻と対比させる形で、やたらと実母を理想化して捉えるのは、思考がマザコン化している証拠だ。
母は、息子にとっては、高齢の存在であり、やがて死んでしまう。そこで、仕事以外何もできない息子が頼るのが次に妻だ。そこで起きるのが、妻=専業主婦の「お母さん」化だ。
専業主婦を実母代わりにして、彼女に精神的に依存する現象が起きる。
財布も子供も、家庭の実権も、全て専業主婦に握られてしまい、男性は、自分自身はただ会社人間としてひたすら労働して家庭に給料を入れるのみ、それしか出来ない、依存的で自立できない人間となってしまう。
男性が、妻は、実母同様自分の身の回りの世話をしてくれて当たり前、妻は自分の身の回りの世話を十分するように、それ以外の外仕事はするな、専業主婦でいろと、横柄な、妻を束縛する態度に出るので、妻には嫌われる。これが熟年離婚の原因だ。その原因の源は、自分の息子を自分のダービー馬に仕立てた、夫の母親にある。また、日本の女性が、家事負担のため、外での仕事を諦めて専業主婦にならざるを得ない状況を作り出しているのも、息子を仕事人間に仕立てた、男性の母親だ。
そうしてやむなく専業主婦になった妻が、夫や息子を新たに自分の「ダービー馬」と仕立てて、受験、会社での昇進競争に向けてハッパをかけるとともに彼らの身の回りのことを全部かいがいしく行ってあげて仕事、勉強に専念させることで、妻=母が自分の自己実現の道を見いだすようになるという「専業化への世代間連鎖」(夫は、仕事専業に、妻は家事専業になる)が起きている。これが、日本において、いわゆる「男社会」がちっとも解消されない一番の原因だ。
日本のフェミニストや女性学者らが批判する「男社会」を作ったのは、ほかならぬ女性たちなのだ。もっとそのことに注意を払うべきだ。
(初出2008年05月)
従来、臨床心理の分野とかでは、母親の心理的影響力が強い日本のような社会のことを母性社会と呼んでおり、世の中ではこの呼び方がなされることが多い。
しかし、この母性社会という呼び方は、どちらかといえば社会の静的な性質を表した呼び方で、日本社会において母親が動的に行使している社会的影響力、支配力の大きさを実感するには物足りない。
筆者としては、従来の母性社会という言い方に代えて、「母権社会」(ないし母権制社会)という言い方にすることで、日本の母親の強大さを少しでも実感できるようになるのが望ましいと思っている。
同時に、欧米のように父親が強い社会は、父性社会と呼ぶよりは、父権社会(ないし父権制社会)と呼ぶのが望ましいと思っている。
(初出2008年07月)
母権社会が言われてこなかった理由は、男性の面子を潰さないための女性による配慮の結果である。女性は、自分が強いとあえて言わない。
男性は、自分自身が女性より弱いと感じると、ペニス同様、小さく、弱々しくしぼんで、女性を引っ張る強い行動力を失う。あるいは、女性を守る盾として活用することが出来なくなる。そうなると女性が困るので、女性は、必死で弱い振りをするのである。
男性がマザコン呼ばわりされるのを避けるという問題もある。日本男性が、他国の男性に比べて弱く見える、魅力無く映るのが、国防上とかで嫌だというのもある。
(初出2012年04月)
日本男性は、わがままな暴君、専制君主である。腕白で威張るのが好きで、いい格好しがちな存在である。
日本男性は、精神的には、永遠に母の懐に抱かれた「息子」としての存在であり、母の手のひらの上に乗って威張っているが、心の奥底では、母に甘え、深く依存した、未成熟な子供のままである。
日本男性は、結婚しても、実質としては妻のもう一人の子供として、妻に心理的に依存し、父になれない、父未満の存在であり続ける。
未成熟な子供のまま、力任せにわがままに強引に振る舞うので、見かけは、強大な支配者のように見え、それが「家父長」であるかのように見えるのである。
彼ら日本男性は、「皆の面前で」格好よく目立ちたい、威張りたい、皆を代表したいとか、上に立って指示、指図、命令したいとか、周囲に有能、できると思われ、周囲よりも早く出世、昇進したいといった、周囲の視線を前提とした「見栄っ張り」の性質を持っている。
日本男性は、こうした見栄を張るために、少しでも格好良く皆の前でぴしっと決めたいという欲求を持ちつつ、それを自分一人の力で実現していくだけの心の強さを持ち合わせず、無意識のうちに周囲の自分を包み支えてくれる母的存在に心理的に頼ろうとするのである。それが自分の一人の足では立てない、ひ弱な張りぼてのような「立てられる人」状態を生み出しているのである。
日本男性は、基本的に背後から「立てられた」存在である。会社とか社会の表面に立って威張っているが、その状態を維持するには、支えが必要であり、何らかの「母的存在」が彼を立たせ、支えている。この場合、「母的存在」とは、実母であったり、妻であったり、居酒屋のママであったり、所属する会社であったりと、多種多様である。
立てられているとは、自分を立ててくれている存在に依存していることを意味する。そこら辺の、自分一人では何もできず、周囲に「立ててもらっている」という自覚がなく、まるで自分一人で自立していると思いこみ、社会の表だった支配者みたいに威張っている点が、日本男性の痛いところである。そのくせ、立ててもらわないと、優秀な社員が逃げ出した会社のように、すぐ不格好に倒れたり、潰れたりしてしまう。
日本社会の実際の支配者は、見かけ上威張っている男性たちを立たせてくれる、支えてくれる、依存させてくれる、大きく温かく包んでくれる、甘えさせてくれる側の存在であり、先に述べた「母的存在」がそれに当たる。「母的存在」こそが、日本社会の奥まったところに座る真の支配者であるということができる。
こうした「母的存在」が、「立てられる人」である日本男性を行動させる、つき動かす原動力、モーター、エンジンとなっている。それは、「母性エンジン(お母さんエンジン)」「母性モーター(お母さんモーター)」とでも呼べるものである。そうした母性(母的)エンジン、モーターに基づいて行動するために、日本男性の行動様式は自然と、所属組織との一体化や集団行動を好む、母性的なものとなるのである。
(初出2008年07月)
日本の職場は、女性の管理職の割合が、他の国に比べて少なく、昇進とかも男性より遅れる等、男性中心で動く「男社会」だ、という社会学者の研究結果が、半ば社会の公式見解になっている。
しかし、そうした見解は、職場とかで表立って支配者みたいに威張って活躍する日本男性の背中に、男性の母親が、男性が子供の頃からぴったりと密着して貼り付いて、男性と心理的に一体化して、男性を自分の思いのままに操縦しているという事態を想定していない。
日本男性は、表立っては社会の支配者であるが、実はその男性の背中に更に真の支配者である男性の母が貼り付いて、男性を依存させ甘えさせると共に、男性にあれこれ指図、命令を下して支配している。そのため、日本社会で表立って活躍するのが男性でも、日本社会の性質は、相互の一体感、包含感、集団行動を重んじる母性的なものになる。こうした構図に、「日本=男社会」論者は、気づくことができていない。
その点、「日本=男社会」説は誤っており、「日本=母社会」説に修正されるべきである。
(初出2008年07月)
図による説明を設けている。
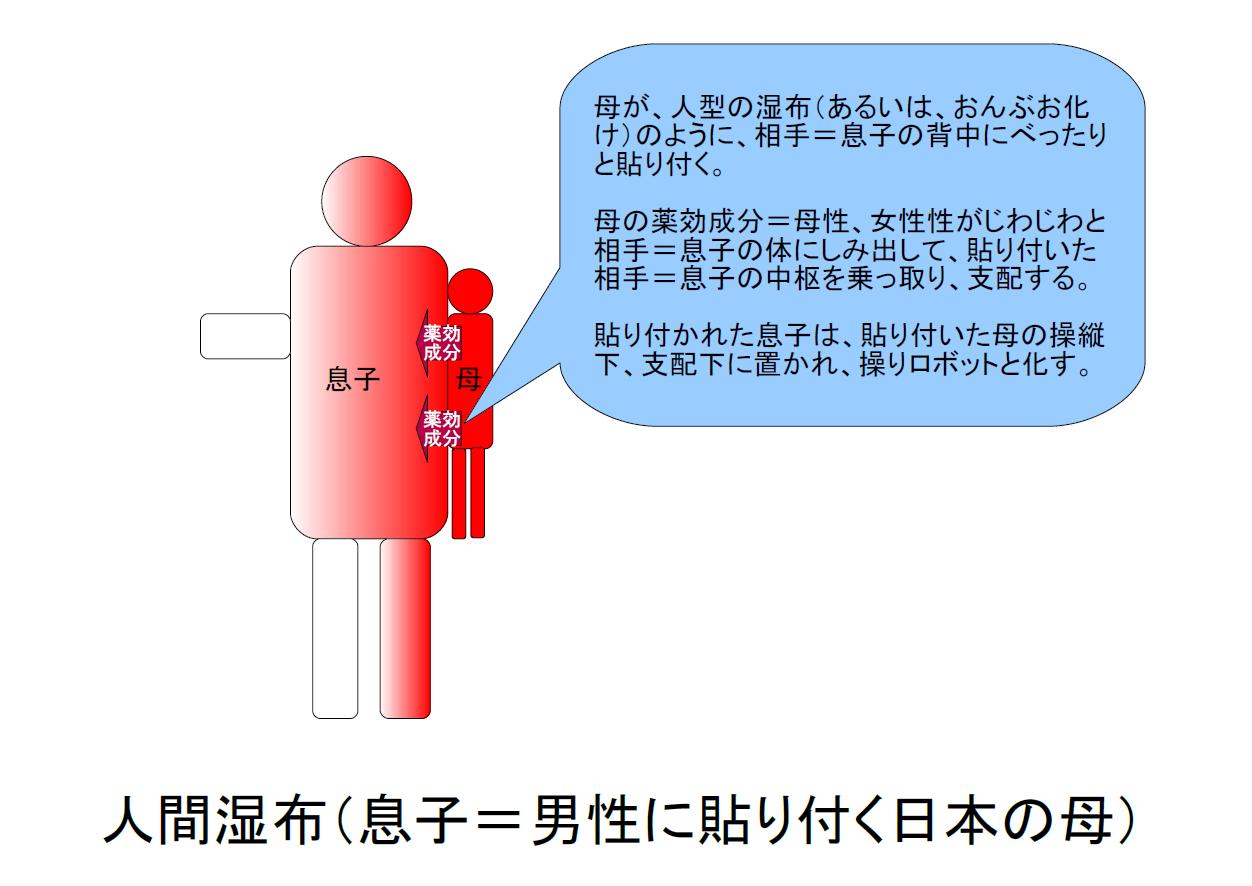
日本の女性が、男性を支配するやり方は、男性の母親としての立場を最大限に利用するものである。
(段階1)母が、人型の湿布(あるいは、おんぶお化け)のように、相手=息子の背中にべったりと貼り付く。
(段階2)母の薬効成分=母性、女性性がじわじわと相手=息子の体にしみ出して、貼り付いた相手=息子の中枢を乗っ取り、支配する。
(段階3)貼り付かれた息子は、貼り付いた母の操縦下、支配下に置かれ、操りロボットと化す。
日本の男性は、精神的、心理的に、常に母親を背中に背負っていて、半ば無意識のうちに、背中の母親の意向に沿うように行動していると言える。
(初出2008年09月)
太平洋戦争中の日本社会の心理は、その女性的、母性的性格をむき出しにした、相互一体感、包含感に基づくヒステリックな精神的高揚として捉えることができる。
すなわち、日本の女性解放運動においては、太平洋戦争時、
・高群逸枝に代表されるように、天皇=(女神である)天照大御神と見なすことが行われた。日本社会の中枢である天皇制を、女性化して捉えていた。
・また、母が息子に対して、お国のために死ねと命令することが平然と行われた。これは、母として、自分と非独立で一体化している、自分の命令を聞いてくれる息子に対して、絶大な心理的影響力を行使していたことを示している。
こうした、いわゆる日本的ファシズムと呼ばれる社会的風潮は、女性、母性の強い影響下で作り出されたものであり、日本社会における女性、母性の強さとして捉えることができると言える。
(初出2012年03月)
日本社会で一番力が強いのは、表面に出て威張っている男性ではなく、その母親の姑である。
姑は、息子との間で、強力な母子一体、癒着状態を作り出し、その中で、親→子供の支配従属関係を利用して、息子を精神的に支配するのである。
姑は、普段は、表に出ずに奥に収まって「いつも息子がお世話になっております」みたいに頭を下げて言っているので、家庭で強権を振るっている実態が、なかなか表に出にくいのである。
日本社会全体が、姑の価値観、姑根性に染まっていて、重箱の隅をつつくようなやり方で、社会の中で嫁相当の立場にある弱者をチクチク陰険にいじめているのである。
姑根性は、
「何事も、「~しなさい」の上から目線の命令、指示口調で行う」
「上位者である姑に対する精神的な絶対服従を、相手に要求し、言挙げは一切許さない」
「細かい所まで隅々まで監視の目を行き届かせ、箸の上げ下げにまで口うるさくヒステリックに文句を言う」
「自分の気が済むまで、ひたすらペラペラ相手に一方的に説教しまくり、話している最中に、次から次へと新たな説教の種を連想して思い出しては説教を続けることで、相手を心理的に窒息させ、逃げ場がないところまで徹底的に追い込む」
「既存の家風(とか社風)、しきたりへの一方的な帰依を相手に求め、新たな変革の試みをことごとく前例に反するとして、握りつぶす」
といった特徴を持つ、相手を支配する際に姑が見せる態度である。
これが、日本人の、特に弱者に対する態度の基盤になっているように思われる。先輩の後輩に対する態度とかが、この姑根性の典型である。
(初出2008年12月)
日本において、広く社会の上位者、支配者が持つ思考様式、イデオロギーである。
全ての人は、何らかの形で姑の立場、嫁の立場に二分される。
日本では、親会社、職場の上司、学校の先輩、地域の本家が姑相当の立場にいる。
下請け会社、部下、後輩、分家、小作が嫁相当の立場にいる。
姑は、自分の子供や孫への世話が行き届かないのを嫌う。
嫁が、自分の子供や孫を放って、働きに出ることはもっての他である。
姑は、嫁の手抜き、怠けを一切許さない。
嫁が子供を保育所に入れるのは、嫁による育児放棄であるとして、許さない。保育所の増設を嫌う。待機児童の解決が進まない、主な原因となっている。
姑は、嫁の落ち度をくまなく探し、指摘し、延々とエンドレスに説教する。
嫁の反抗、嫁の自分からの逃避、自主独立、嫁が自身の縄張り構築をするのを許さない。
姑思考は、
嫁を細かく、漏らさず監視、干渉する。
嫁に、自分の価値観を押し付ける。
上から目線で、嫁をうるさく注意する。
姑思考は、
マイナス点ばかりに注目する減点主義である。
責めるばかりで、褒めようとしない。
批判、ダメ出し、潰し、否定するばかりで、肯定や積極的提案が無い。
目上から目下への一方的で長時間の説教、自説展開を行う。
反論すると、根に持って、いじめる、いたぶる。反論自体を許さない。
説教の内容が、感情的、情緒的であり、客観性に欠けている。
姑思考は、
我慢を強要する。
辛さの回避を甘えと判定して批判する。
自分への完全服従を求める。
上から目線である。
サディストである。
姑思考は、
些細なことに姑息である。細かい。
漏れがない。嫁にとって閉塞感がある。
姑は、
嫁が考えた新しい知識、アイデアを否定する。自分の知識が無効化するのを拒否する。
いわゆる無縁社会の発生と、嫁の姑からの独立達成とは、深い関係がある。
個々の日本人にとって、外部社会、世間は、姑の役割を果たしているのであり、それを嫌って、内々に閉じこもって、外部社会、世間との連絡を最小限へと絶とうとするのである。
姑の影響力低減こそが、本当の日本のフェミニズムのねらいであると言えるのかも知れない。
(初出2010年7月)
母権社会日本における、日本人の思考の原型は、母であり、その思考様式は、母的思考、母思考と呼べる。
身内というか、同じ血縁内、派閥、グループ内、内輪に対しては、母思考であり、相手への慈しみと、惜しみない愛情の投入、甘えの受容が見られる。
一方、よそ者、血縁外、グループ外、派閥外に対しては、姑思考であり、相手に対する辛口の評価、批判、説教が先行する。
母思考、姑思考のいずれにおいても、相手を包み込み、呑み込む感じが強く、相手にとっては、一体感、閉塞感、窒息感、逃げ場のない被支配感が感じられる。
(初出2010年7月)
最近の日本においては、夫の妻=嫁が、夫の母親である姑と同居しなくなったことにより、姑の、息子の家庭への影響力が低下しつつある。
嫁が姑との同居を嫌い、姑と同居しなくて済む男性ばかり選んで結婚している。あるいは、嫁が夫との結婚条件として、姑との非同居を求めることが当たり前になりつつある。
姑の同居しない日本の家庭は、すっかり妻=嫁の独立王国となり、夫が妻=嫁の言うことを聞くようになり、母である姑のことを避ける、付き合わないようになりつつある。
夫は、妻=嫁の言うことを聞かないと、離婚されてしまい、慰謝料の請求とかで自分の財産を身ぐるみ剥がされた上、ひどい時には、家から追い出されてしまう。
また、夫は、マザコンだと、妻=嫁にとって、離婚する格好の理由になる。したがって、夫は、母である姑とくっつき続けることができず、母子連合体の破壊につながる。
こうした点から見て、従来筆者が主張してきた、日本において姑が家庭を支配するという構図は、やや改められなくてはならない。かといって、日本の家庭が母性中心、女性中心であることを止めたかと言えばそんなことは全然なく、子供を出産して母親となった嫁が、母子連合体の形成で、夫を圧倒、疎外する構図は変わらず、また夫が嫁に対して母親代わりに精神的に依存する傾向が強くなることで、従来の姑中心が、新たに嫁中心に変わっただけであるといえる。日本の家庭が母性、女性に支配されていることは、今までと何ら変わりない。
すなわち、従来は、嫁姑同居により、母、姑が子供(息子とか)を大人になっても、結婚後も、母、姑が存命する限り一生支配し続ける、「一生支配」の世代間連鎖が起きていた。それが、嫁が強くなって、姑との同居を避けるようになり、嫁姑別居が起きることで、母(姑)が、息子の前半生、結婚するまでを支配し、妻(嫁)が結婚後の後半生を支配する、母(姑)と妻(嫁)による「時分割支配」に変わってきていると言える。
日本男性は、前半生は母にすがり、後半生は妻に頼る、という構図になってきていると言える。
(初出2012年2月)
現在の日本は、母と娘のつながりが強い、母と娘のつながりで持っている社会である。
従来、娘は、結婚して夫の家に入り、元の家族とは断絶すると見なされてきた。
それが、結婚しても、母と娘との絆が切れなくなった。
メール、電話、ネット、交通の発達により、絆が保持されるようになってきた。
母親にとって、息子は異性な分、どうしても手を付けられない、よく分からない領域が出てくる。一方、娘は、自分との同質性がより強く、よく分かる存在であり、それゆえ絆が強くなる。
また母親にとって、息子は自分と同性のライバルである嫁に取られてしまうが、娘は取られることがなく、いつまでも親密な友達でいられる。
また、年取った母の世話をするのが、赤の他人の嫁よりも、血のつながりのある娘がする方が心理的に順当であるという点もある。
嫁が心理的に夫の家に入らなくなり、姑との付き合いや世話を嫌だという傾向が強くなってきており、それに代わる存在として、娘がクローズアップされてきているのである。
結婚した女性の場合、姑の嫁としての立場と、実母の娘としての立場の両方が同時に存在し、今までは姑の嫁としての立場が主だったのが、実母の娘としての立場に転換しつつあるということである。
あるいは、昨今の日本経済の景気悪化と雇用空洞化の深刻化により、結婚相手の男性の収入だけでは生活して行けず、女性も働きに出ざるを得ない状況が生まれているが、その際、子供をどこに預けて働くかが問題になる。
困ったことに、日本の保育所の数は、こうした現状を想定しておらず、子供の収容人数が少なすぎるため、そのままでは入所待機になってしまい、女性は働きに出ることができない。
そこで、そうした困った状況を解決するとしてクローズアップされる存在が、女性の母親である。子供を自分の母親に預けることで、女性は働きに出ることが容易になるのである。
こうして、母-娘のライン、連鎖が社会的に優勢になることで、日本の女系社会化が進んでいると言える。
というか、結婚する夫婦と、その母親との関係において、姑(夫の母)から、妻の母(これは何と呼ぶのであろうか)への権力移転が起きていると考えられる。
これは、嫁が姑と同居しなくなったというか、そもそも同居しないことが結婚条件になることが多くなってきて、姑の嫁に対する権力行使の場面が減っていることが大きい。
もっとも、夫の母から、妻の母へと、権力の持ち主が変わっただけで、同じ母という存在による支配であることには変わりない。日本は、姑による支配が弱くなっても、引き続き母権社会のままであると言える。
(初出2010年7月)
日本の家庭は、かつての姑による嫁の全面支配から、姑による嫁の部分支配を経て、嫁の姑からの独立と自由の確保の状態に移りつつあると考えられる。姑と夫の同居が当たり前だったのが、たとえ長男であっても別居するように変わりつつある。
これは、以下のような3段階の図にまとめることが出来る。
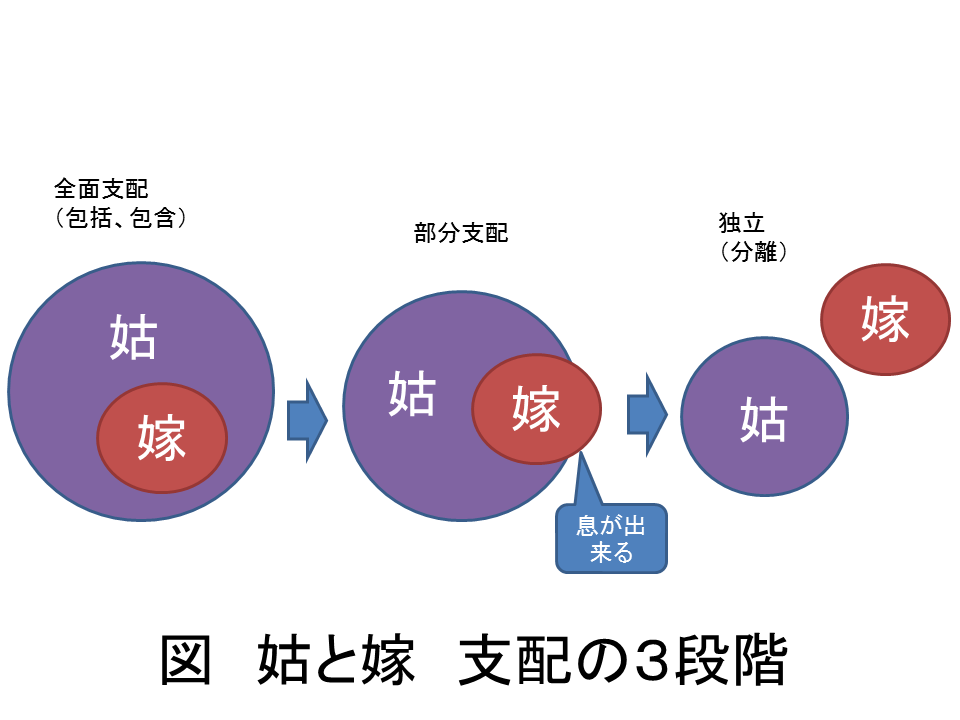
かつては、姑が嫁を包括、包含し、全面的に支配していたのが、嫁が姑のもとから表面上に頭を出して独自の息が出来るように変化し、更に、嫁が姑から分離して、独立するようになってきている。
(初出2014年1月)
日本では、最近、女性がバッシングする対象が、姑から実母に変わってきている感じがする。
それは、「母が重い」とか言った表現で、自分の母親をウザいと捉え、批判するものである。本や雑誌で、実母をバッシングする内容のものが売れているようだ。
先年までは、女性は嫁として、姑と同居する生活をしていたが、それが嫌なので、姑との別居を前提とする結婚を夫に求め、それを実現させてきたのだと思う。
その実現がようやくかなったと思ったら、今度は、実母がうざったく感じるようになったので、ストレスのはけ口を求めてバッシングを始めた感じがある。
女性の業は深いなと思わせる出来事である。
日本の母親は、一人で子育てを独占的に行う。
その結果、日本の母親は、子供にとって、自分を支配する独裁者となる。
子供は、母親に絶えず密着されて、逆らうことができず、母性の漬物と化すことになる。
この現状を打破するには、強い父性を備えた父親の介入が必要である。
そうした強い父性を日本男性が得るためには、日本男性の母からの引き離し、解放が必要である。
(初出2011年10月)
日本においては、母親が主体となって、育児、子育て、子供の教育を行なっているが、その際、幼少の時に見られる母と子との間の濃厚な精神的上下関係、支配依存関係が、そのまま小学校、中学校、高校、大学、社会人と、子供が成長していくにつれても、維持され続け、更には、子供が大人になって、結婚し、子供を設けてからも、引き続き維持され続けるのである。母による子の永続的支配がそこには見られる。
こうした、日本における、幼少時からの母子間の上下関係、支配依存関係が、永続的に維持されることが、日本社会の母権社会化と大きな関係を持っていると考えられる。すなわち、日本社会の人々が、子供として母の支配を、子供の時からの習慣、慣性で、引き続き大人になってもそのまま受け続けることが日常化していることが、社会が母権社会になること、母権社会発生の原因であると考えられる。
(初出2012年07月)
日本の男性は、母親との一体化の度合いが強く、他の女性を見るときなど、自分の母親=姑の視点で、あたかも格下の嫁を見るかのように見下して見がちな傾向がある。これが、日本において、男性=格上、女性=格下とする男尊女卑の考え方の元になっている。
後は、日本の男性が女性を批判するとき、自分の母親はその批判対象の女性には含まれておらず、別腹扱いとなり、自分の母親のことは肯定的に見がちである。同じ女性でも母親は格上の存在として捉えがちである。
(初出2014年4月)
日本のようなウェットで母性的な社会では、男性は、巨大な母艦、母胎である女、母の元から飛び立ち、帰ってくる、矮小な存在である。
一方、欧米のようなドライで父性的な社会では、男性は、母艦なしに自由に飛び回る、ある程度大きな存在であり、女性はその男性にしがみつくだけで何も出来ない無力な存在である。
(初出2009年11月)
日本社会は、母への甘え、女性への甘えで成り立っている社会である。
日本社会の基盤部分(家計管理、子育て、ウェットな対人関係・・・)を女性(特に母親)が支配している。男性は、生育の過程で、彼女らに足首をつかまれ、支持され、立たせてもらって、やっと活動できている状態であり、女性たち(特に母親)に心理的に深く依存し、甘えている。しかし、同時に社会的な行為責任を女性たちから負わされて、各種の責任者、会社・官庁の管理職とかをやっているので、表面的には、そうした男性たちが、日本社会の支配者のように外部者の目に映るのである。
そうした点を無視して、社会を父が支配する西欧流の男女共同参画社会モデルを日本社会に導入した結果、女性への作業負荷が大きくなりすぎてしまい、機能不全に陥っている。要するに、女性たちが、男性に甘えられて、男性の面倒を全面的に見ながら、かつ自分も、会社や官庁で男性並みに働かないといけないみたいな感じになっており、作業面で完全にオーバーフロー化している。
日本の少子化が指摘されて久しいが、日本の少子化の原因は、こうした感じで、社会進出を求められる余り、男性の面倒を見たり、子供を産み育てたりする余裕が、女性の側に無くなってきているのも一つの要因なのではないだろうか?
日本の少子化を解決するためには、一つは、
・男女共同参画社会モデルを日本にこれ以上導入するのを止める。旧来の、男性が女性に心理的に依存し、女性が男性を心理的に全面的に支えるモデルに戻る。
ことが上げられる。
一方、男女共同参画社会モデルを日本に導入し続ける場合、
・女性に一方的に甘え放題の男性の意識改革が必要である。女性に甘えずに、一人で何とかやっていくことで、女性に負荷を掛けないようにすることが求められる。あるいは、母、妻以外に甘えられる対象=「代理母」(のカウンセラー、ソーシャルワーカー)を社会的に用意することが求められる。
・女性の家事負担、育児負担を軽減するため、母性的人工知能、母性的情動を持った家事、育児ロボット(人肌のような温かいロボット=「人肌ロボット」)等の導入を図る必要がある。例えば、子供の様子を観察、監視して、母親の声で「いけません!」と警告を発するカメラの導入とかが必要である。
(初出2014年12月)
日本社会の少子化の原因として、男女共同参画社会の政策との関連が挙げられる。
男女共同参画社会の政策では、「男らしさ、女らしさより自分らしさを追求すべき」ということになり、互いに異性を意識したり誘引することを抑制された結果、男女の結合の発生が抑制され、男女が中性化を余儀なくされ、それが少子化につながっていると言える。
(初出2015年2月)
日本の女性が権力を握る、支配者になるには、母親になる必要がある。不妊の女性は、母になれないので、そのままでは権力からは疎外されると考えられる。
そこで、彼女らは、教師とか、企業の管理職、NPO代表とか、集団、組織成員にとって母親代わりの役に就くことで、権力を握ることになる。
(初出2011年8月)
日本の母親は、髪を振り乱していて、美しくない、みっともなくて良くないという意見がある。果たしてそうか?
権力者は、他人に、自分の言うことを聞かせるために、必死になって主張したり、子供に手を上げたりする。見かけに構っていられない、取り繕っていられない、権力者であることの現れである。
そういう点では、身なりに構わない、生活感にあふれた日本の母親は、権力者の姿そのものであると言え、社会的に力があることの表れであるとも言え、そういう点では望ましいと言える。
(初出2011年8月)
映画監督やタレントとして世界的に有名なビートたけしは、自分の弟子筋に当たる人たちに対して、自分のことを殿と呼ばせ、ハハッと平伏させて、自分に対しては絶対服従、反論を許さないかのように振る舞っている。
ビートたけしの場合、上記の振る舞いは単なるギャグなのかもしれないが、実際のところ、親分、子分関係に代表されるような、日本の上位者‐下位者関係は、この上位者に対する下位者の反論を一切許さない、専制的な対人関係になることが多いように思われる。しかもその場合、下位者が上位者に対して母親代わりに心理的になつき、甘えたり、わがままをする姿も見られるのである。
上位者に直接冷徹に刃向かう反論は許されないが、上位者になついていれば、ある程度のわがまま、いたずら、自由は許されるという構図になっている。
それでは、なぜ上位者に直接刃向かう反論がいけないのか?
それは、上位者の心にある、
(1)自分は下位者より上位におり、かつ下位者は自分になつき、自分を慕ってくれ、心理的一体感を持って付いてきてくれる、同意してくれるはずであり、それだけの人間的度量が自分にはあるのだという高いプライド、
(2)下位者への間に培われた心理的な密接な一体感、安心感、
の両者が予期せず一度に破壊され、切り裂かれて、上位者の心の中の柔な領域(ソフトエリア、デリケートエリア)に直接大きな切り傷ができて、上位者にとって心理的ダメージが大きいためであり、それゆえ禁止である。寝首をかかれるのと同じ効果があるのである。
この場合、ソフトエリア、デリケートエリアとは、あたかも人間の柔肌のような、温かく、柔らかで、ナイーブで、繊細で、敏感で、粘膜で覆われた、無防備で、傷つきやすく、いつもは、固いガードの領域(ハードエリア、ガードエリア)で覆われて、外部の侵入を容易に許さない領域である。
上位者は、下位者と心理的に一体になる(親分、子分の関係になる)時点で、心理的なデリケートエリアを下位者に対して直接さらすことになるのである。むろん、下位者も同様に上位者に対してデリケートエリアを直接さらすことになる。両者のデリケートエリア同士が直接、一体で間を割るものなしに密着したときに、上位者と下位者との間の主従関係、親分子分関係が完成するのである。
人間にとって、自分の本音、自分の本当の気持ちは、このデリケートエリアにこそ存在するのである。相手と互いに自分のデリケートエリアをさらすことは、相手と本音の付き合いをすることである。その関係を結ぶための特別な儀式(盃交わしとか)が必要となることが多い。
こうした、上位者と下位者との間のデリケートエリアの相手への露出、一体化をすることの原型は、母子関係にあると考えられる。というか、日本におけるヤクザとか体育会系の親分=上位者は、下位者にとって、包容、愛着、一体化の対象であり、母親代わりの存在であると言える。
互いのデリケートエリアに直接アクセスして、密着するのは、相互の心理的一体感、密接感を重んじる女性的、母性的な傾向であり、それゆえ親子関係としては、母子関係に特徴的に見られると言える。また、女社会での上下関係に特徴的と言える。こうした相互の密着、一体感は、上位者と下位者との間にウェットな感触を呼び起こすのである。
一方、欧米のような、男性的、父性的上下関係、父子関係を基盤とする社会、男社会においては、上位者と下位者が直接デリケートエリアを互いにさらし、密着させ合うことは原則として無く、ガードエリア越しでの対応となる。互いの自主独立、自由を保ったまま、ある程度相互の距離を置いたまま、相手の動きを観察して、相手の取る進行方向や考え方、イデオロギーを相互に見極め、最終的に相互を信頼する形で、いわば相互にドライに離れた形で主従関係を完成させるのである。相互に離れたまま、相手の人格の根幹を信頼し合うのである。
日本のような母子関係を基盤とする社会では、母や母代わりの上位者は、下位者にとってクッションとして立ち現われる。クッションは、互いに柔軟にフィットし、一体化が可能な存在であり、メンタルなデリケートエリアを直接具現化した存在である。この場合、下位者も上位者に対して、相互の柔らかな一体感を保持するため、小さなクッションであることを求められる。固いビー玉ではダメなのである。上位者、下位者共に、人間としての体質がクッション体質になる。
あるいは、日本社会自体が、国民に対して大きなクッションとして立ち現われるのである。クッション社会、クッション国家の出現である。
クッションは、それ自身に対して、あるいは相手先に対して、どうしても自然と柔らかくフィットして、迎合してしまう存在である。それと同様に、女性、日本人のようなクッション体質の人間は、物事を掘り下げたり、切れ味鋭く分析するのに根本的なところで向いていないと言える。
クッションとしての上位者に、べたべたくっつき、体を預けたまま、一体化して離れようとしないのが、なつきである。
優れたクッションは、ぐいぐい押しても、それを吸収して元の形に戻る。クッションをぐいぐい押す行為が、下位者による上位者に対するいたずらや甘えである。
女社会、日本社会のようなクッション社会においては、このクッションとしての度量が大きいほど、人間としての度量が大きいと見なされ、理想的な上位者と見なされる。
(初出2010年7月)
※この項目は、書籍「日本社会の女性的性格」と共通です。
家庭、家族関係は、大きく分けて、
(1)夫婦関係 家庭の基盤となる男女関係
(2)親子関係 父子、母子、義理の父子、母子関係
から成ると言える。
日本の家庭、家族の中の男女の勢力関係は、
(1)夫婦関係に着目すると、日本では、夫=男性が強く見えることが多い。その理由は、
・嫁が夫の家に嫁入りし、夫の家の言うことを聞く必要がある。
・男尊女卑で、夫が威張っている。
・稼ぐのが主に夫であることが多く、妻、嫁はあまり稼げておらず、経済的に夫に依存せざるを得ない。
こうした点を強調して、日本の家族は家父長制だという主張が、日本の社会学者の間では主流になっている。
一方、妻=女性が強く見える側面もある。
妻が家計管理の権限を独占していることが多く、小遣いを夫に渡す場面が多く見られる。小遣いは渡す財務大臣役の方が、もらう方より地位が上である。
(2)親子関係に着目すると、日本では、母=女性が強い。子育ての権限を独占し、教育ママゴンとか呼ばれ、怪物扱いされている。子供を自らの母性の支配下で動く操りロボットにすることにすっかり成功している。一方、父は、子供と関わりをあまり持とうとせず、影が薄い。
こうした母親の影響力の大きさを考慮して、日本社会は母性社会だという主張が、日本の臨床心理学者の間で主流になっている。
このように、夫婦関係を見た場合と、親子関係を見た場合とで、日本の男女の勢力に関する見方が分裂しているのが現状であり、両者の見方をうまくつなぎ合わせる統合理論が必要である。
筆者は、両者の見方をうまく統合させる契機として、「夫=お母さん(姑)の息子」と見なして捉えることを提唱する。
家父長として強い存在と思われてきた夫が、実は、母、姑の支配下に置かれる操りロボットとして、実は父性が未発達の、母性的な弱い存在であることを主張する。
日本において、子育てを母が独占し、子供の幼少の時から、強力な排他的母子連合体(母子ユニオン)を子供と形成し(母が支配者で、子が従属者、母の操りロボット)、この母子一心同体状態が子供が大人になってからもずっと持続し、この既存の母子連合体が一体となって、新入りの嫁を支配するという構図になっている。このうち、「母の息子=夫」と嫁の間のみを取りだして見ると、夫が嫁である妻を支配するという従来、日本=家父長制社会論で主張されてきた構図が見える。しかし実際には、夫は、母である姑に支配されており、その姑と一体となって、嫁を抑圧しているに過ぎない。
日本の夫婦における勢力関係を正しく把握するには、夫婦(夫妻)だけを見るのではなく、夫婦(夫妻)のうちの夫側に、母のくさびを打ち込むことが必要である。あるいは、母や姑が一家の実質的な中心であり、真の支配者であるとする「母」「姑」中心の視点を持つことが必要である。
夫婦だけを見るのでなく、
・母~息子(夫)←(何人も割って入ることを許さない母子連合体、ユニオン)
・姑~嫁(妻)
・夫(母の息子)~妻(嫁)
の3つを同時に見る必要がある。夫の父(舅)は、一世代前の母の息子のままの状態であり、影が薄い。夫の姉妹は、小姑として、夫同様、姑中心の母子連合体の一員として、嫁を支配する、姑に準ずる存在である。
夫は、妻にとっては一見強い家父長に見えながら、実際のところは、いつまで経っても母の大きい息子のまま、母に支配され、精神的に自立できない状態にある弱い存在であるという認識が必要である。
母の息子である夫、父は、一家の精神的支柱である母と違い、家父長扱いされながらも、母に精神的に依存し続けて一家の精神的支柱になれない、ともすれば軽蔑され見下される存在と成り下がっているのである。
夫は、仕事にかまけて子供と離ればなれになっているが、実は、この仕事が、夫の母の代わりに行っているというか、母の自己実現の代理になっている。会社での出世昇進とか、一見、夫が自分自身のために頑張ってしているように見えて、実は、夫自身が母の中に取り込まれ、母と一心同体となって母のために頑張って行っているというのが実情である。母が息子の出世昇進に一喜一憂し、夫にとって、自分の人生の成功が、そのまま母の人生の成功になっている。また、夫が会社で取る行動は、会社人間のように、会社との一体感、包含感を重視する、とかく母性的なものになりがちで、彼を含めた会社組織の男性たちが大人になっても母の影響下から脱することが出来ていないことを示している。
筆者は、こうした、
・母(姑)による息子=(妻にとっての夫)の全人格的支配
・妻による家計管理の権限独占に基づく夫の経済的支配
の両者を合わせることで、日本の家庭~社会全体において、母性、女性による男性の支配が確立しており、日本は、実は、母権社会、女権社会である、と主張する。一家の中心は、母、姑である。
欧米の権威筋の学説(Bachofen等)は、母権社会の存在をこれまで否定してきており、筆者の主張はこれに正面から反対するものである。
日本人の国民性と男女の性格との相関を取ると、日本人は女らしい(相互の一体感、所属の重視。護送船団式に守られること、保身安全の重視。リスク回避、責任回避重視。液体分子運動的でウェット・・・)で動いているという結論が出る。これは、日本社会が、女権、母権社会であることの動かぬ証拠と考えられる。日本人は、姑根性(周囲の、後輩とかの嫁相当の目下の者に対して、口答えを一切許さず、妬み心満載で、その全人格を一方的、専制的に支配する)で動いており、このこと自体が、日本社会における母、姑の影響力、支配力の強さを表している。それゆえ、日本の社会、家族分析に、姑中心、母中心の視点を取ることが必要であると言える。
従来の日本男性は、母や妻による支配を破ろうとして、がさつな乱暴者、あるいは雷親父となって、ドメスティックバイオレンスとかで対抗してきた節が見られるが、暴力を振るうだけ、より家族から軽蔑され、見放される存在になってしまう結果を生み出している。あるいは、家庭の外の仕事に逃げようとするが、仕事に頑張ることがそのまま母の自己実現になるという、母の心理的影響、支配を振り切ることはそのままでは不可能である。
こうした女性、母性による日本社会支配は、日本社会の根底が、女向きの、水利や共同作業に縛られた稲作農耕文化で出来ているために生じると考えられる。そこで、筆者は、日本男性は、従来の伝統的稲作農耕文化から脱却して、新たに、家父長制の本場である欧米やアラブ、モンゴルといった遊牧、牧畜民の父親のようなドライな父性を身につけることで、母と妻に対抗できるようにすべきだ、母と妻の支配から解放されるべきだと主張する。これが、日本男性解放論である。要するに、子育てと家計管理において父権を確立することで、父親として真に社会で支配力を持った、尊敬される存在になろうと呼びかけるものである。筆者は、その際、稲作農耕を、伝統的な日本方式から、よりドライなやり方のアメリカのカリフォルニア方式に改めることで、稲作農耕を維持しながら、ドライな父権を社会に実現できると予期している。
筆者は、最終的には、男女の力関係は、対等の50:50が望ましいと考えている。これが、究極の男女平等であると主張する。欧米みたいに、男性、父性が強くなり過ぎても、日本みたいに、女性、母性が強くなり過ぎても良くない、適度なバランスが必要と考える。家計管理を、夫と妻が1月交代で行う月番制導入とかである。
(初出2012年6月)
ドライないしウェットな性格、態度は、以下の表に書かれているようにまとめることができる。
|
|
ウェット |
ドライ |
|||
|
〔A〕 |
|||||
|
〔A1〕 |
〔他者との心理的位置の同一・共通化〕 |
||||
|
[A1.1] |
集団主義 |
個人主義 |
|||
|
[A1.2] |
密集指向 |
広域分散指向 |
|||
|
[A1.3] |
画一(同質)指向 |
多様性の尊重(異質指向) |
|||
|
[A1.4] |
同調指向 |
反同調指向 |
|||
|
[A1.5] |
主流指向(権威主義) |
非主流指向(反権威主義) |
|||
|
〔A2〕 |
〔他者との関係・縁故の構築〕 |
||||
|
[A2.1] |
関係指向 |
非関係指向 |
|||
|
[A2.2] |
縁故指向 |
非縁故指向 |
|||
|
〔A3〕 |
〔行動決定の自由〕 |
||||
|
[A3.1] |
規制主義 |
自由主義 |
|||
|
〔A4〕 |
〔行動の自己決定〕 |
||||
|
[A4.1] |
相互依存指向 |
独立(自立)指向 |
|||
|
[A4.2] |
他律指向 |
自律指向 |
|||
|
〔A5〕 |
〔プライバシーの確保〕 |
||||
|
[A5.1] |
反プライバシー |
プライバシー尊重 |
|||
|
〔A6〕 |
〔行動の明快さや合理性の確保〕 |
||||
|
[A6.1] |
あいまい指向 |
明快(反あいまい)指向 |
|||
|
[A6.2] |
非合理指向 |
合理指向 |
|||
|
〔A7〕 |
〔集団の開放性の確保〕 |
||||
|
[A7.1] |
閉鎖指向 |
開放指向 |
|||
|
〔B〕 |
〔心理的運動・活動・移動指向〕 |
||||
|
〔B1〕 |
〔動的エネルギー・移動性の確保〕 |
||||
|
[B1.1] |
静的指向 |
動的指向 |
|||
|
[B1.2] |
定着指向 |
非定着(移動・拡散)指向 |
|||
|
[B1.3] |
前例指向 |
独創指向 |
|||
以下では、上記整理結果をもとに、具体的にどのような人間の行動様式が、ドライ・ウェットさと関連があるかについて、詳細に説明する。ドライ・ウェットな行動様式の詳細な内容を、それらがどのように活動・移動性の有無、心理的に近接する指向の強弱によって説明できるかも含め、一通り述べる。
●A.心理的近接指向(ウェット)-非近接指向(ドライ)
他者と心理的に近づき(距離を縮め)、くっついて、離れようとしない指向の強さに関する。
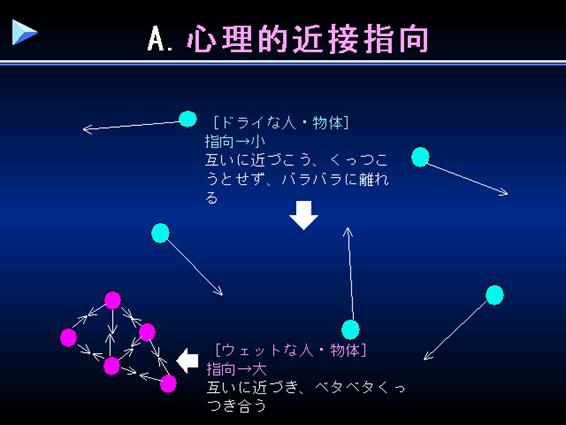
◎A1.他者との心理的位置の同一・共通化(ウェット) -相違・差異化(ドライ)
心理的に他者のいるところへ行こう・集まろうとするかどうかについての次元が存在する。すなわち、他者と心理的に近接するためには、他者と同じところ(心理的位置)を占める必要があり、そのために人々は集団を作ったり、密集したり、同調行動を取ったりする。
○A1.1 集団主義(ウェット)-個人主義(ドライ)
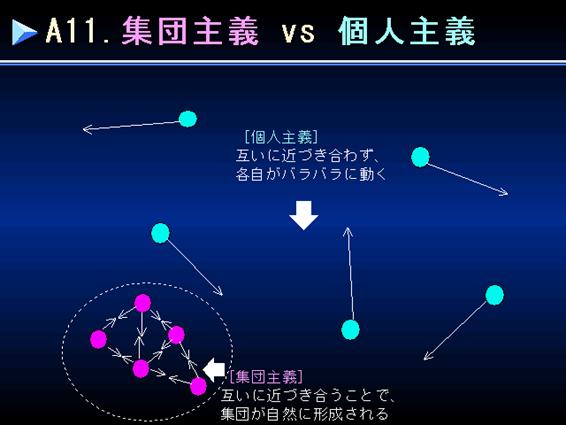
|
A1.1 |
ドライ=個人主義 |
ウェット=集団主義 |
|
定義 |
互いに一人ずつ単独・個別にバラバラに動こうとする |
互いに集まり、まとまって動こうとする |
|
No. |
[例↓] |
[例↓] |
|
1 |
単独・ひとりで行動するのを好む |
集団・団体で行動するのを好む |
|
2 |
他者からの分離・独立を好む |
他者との一体化・融合を好む |
|
3 |
自分個人の利益を優先する |
自分の属する集団の利益を(個人の利益よりも)優先する |
|
4 |
ひとりで他者とは別の道を歩むのを好む |
ひとりで他者とは別の道を歩むのを好まない |
[説明]
各個人に、心理的な引力、他者へと心理的に近接しようとする考えが働いている状態では、個人同士は、互いにくっつき合うことで、互いにまとまりを作り、一つに集まる(のを好む)。心理的に互いに接近し合うことで、各人が一つの集団・団体の中で、互いに心理的にくっついて一体化し、融合することになる。いったんくっつき合って集団を作ると、その中で互いに引き合い、まとまり合う力が働いて、みんな一緒にいようとする。集団を作って互いでひとまとまりでいる状態を維持しようとし、集団を割ろうとする力を否定しようとする。こうした集団内では、人々を集団に引き止める力(集団凝集性)が働いており、集団・団体でい続けようとし、集団全体の動きを、自分個人の動きよりも重要視するようになる。これは、集団全体の利益を、自分個人のそれよりも、優先しようとすることにつながる。中にいる個人が外に独りで出ようとする(脱退しようとする)と、それと反対方向に力が働いて、集団の中に引き戻そうとする。このように、互いに集まり、まとまって動こうとすることを、集団主義と呼ぶならば、集団主義は、互いに心理的に近接しひとまとまりになることを指向する点、ウェットな行動様式と言える。
一方、各個人に、他者へと近接しようとする考えがあまり働かないと、個人同士は、互いに近づき合って集まることなく、互いにバラバラに離れたままでいようとする。互いに一人ずつ個別にバラバラに動こうとする。したがって、集団・団体は、目的がない限り自然には発生しない。いったんできた集団を割ることも平気である。個々人は、周囲からの引力を気にせずに、単独(ひとり)で自由に動き回る(自分自身の動きや進行方向を決定する)ことができ、周囲の他者とは別の道を突き進むことができる。その点で、自分個人の動きや利益を優先することが可能である。集団外に抜け出そうとするときに、周囲の他者から、それを引き止めようとする引力が働かないので、簡単に脱退できる。このように、互いに一人ずつ単独・個別にバラバラに存在しようとしたり動こうとすることを、個人主義と呼ぶならば、個人主義は、互いに離れて、心理的に近接することを指向しない点、ドライな行動様式と言える。
○A1.2 密集指向(ウェット)-広域分散指向(ドライ)
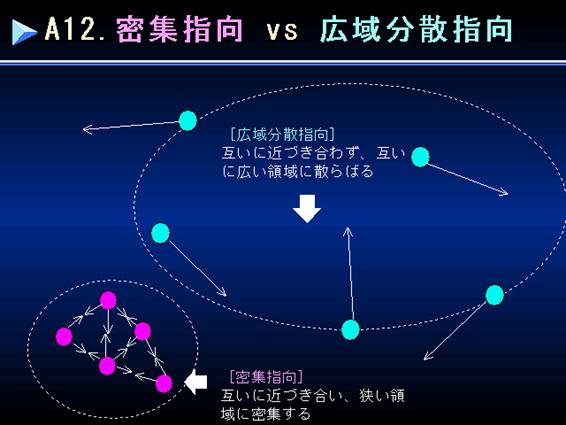
|
A1.2 |
ドライ=広域分散指向 |
ウェット=密集指向 |
|
定義 |
互いに広い領域に散らばる |
互いに狭い領域に密集する |
|
No. |
[例↓] |
[例↓] |
|
1 |
広い空間に分散していようとする |
狭い空間に密集していようとする |
|
2 |
一人ずつ個室にいるのを好む |
多人数で大部屋にいるのを好む |
|
3 |
ものの見方が客観的である |
客観的でない |
|
4 |
ものごとを見る視野が広い |
ものごとを見る視野が狭い |
[説明]
各個人に、他者へと心理的に近接しようとする考えが働いている状態では、各人は互いに近づき、くっつき合うことで、相手との距離がなくなる方向に進む。相 互に隔てのない方向へと近接することで、互いに(大部屋のように)隔てのない、狭い空間に、互いにひとまとまりになって密集するようになる。この場合、互 いに狭い範囲内でものごとを見ることになり、視野が狭くなる。あるいは、互いの間に十分な距離をとって眺めることができないため、客観性に欠けることにな る。互いにより高い密度でまとまることを指向するため、権限などがどんどん皆が集まる中央に集中し(中央集権)、周辺に広がって行こうとしない。このよう に互いの距離を小さくする指向は、密集指向という言葉でまとめることができ、ウェットな行動様式と言える。
一方、各個人が他者へと心理的に近づこうとする度合いが小さい場合、互いに近づき合ってまとまり合うことが少ない分、より低い密度で広い空間内に、互いに分散して(距離を大きく取って、離れて)存在する。仮に分布可能な領域が狭い場合、人々は、個室にいること、すなわち、壁やドアによって、他者のいる空間から隔離される(他者のいる場所からの距離を大きく取る)ことを指向する。広い領域に分散しているため、一度に広い範囲のものごとを見ることができ、視野が広い。互いの間に十分な距離をとって眺めることができるため、ものの見方に客観性がある。互いにより低い密度で周辺に広がっていくことを指向するため、権限などがどんどん地方に分散していく(地方分権)。このように、互いに距離を大きくとって、分散して分布することへの指向は、広域分散指向という言葉でまとめることができ、ドライな行動様式と言える。
○A1.3 画一(同質)指向(ウェット)-多様性の尊重(異質指向)(ドライ)
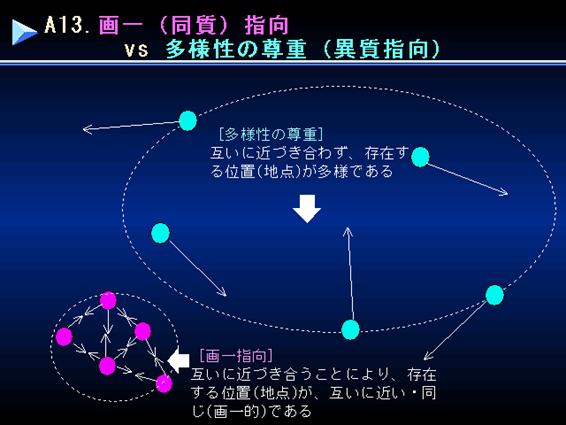
|
A1.3 |
ドライ=多様性の尊重(異質指向) |
ウェット=画一(同質)指向 |
|
定義 |
互いの多様性を重んじる |
互いを画一的な枠にはめようとする |
|
No. |
[例↓] |
[例↓] |
|
1 |
横並びであろうとしない |
周囲の他人と横並びであろうとする |
|
2 |
自分とは異なる意見を持つ人に対して寛容である |
自分とは異なる意見を持つ人に対して寛容でない |
|
3 |
人々の多様性を認める |
人々を画一的な枠にはめようとする |
[説明]
各個人に、他者へと心理的に近づこうとする考えが働いている場合、心理的に近接しようとすることで、互いに心理的に同じところ(位置・場所)に集中しているようにしようとする。互いに存在する位置を同じ(共通)にしようとする。物理的・心理的に互いに同一の位置を集中して占めようとすることで、互いに画一的な状態で横並びすることになる。存在位置が画一化した状態でひとまとまりになるため、そこから一人別の位置に行こうとする(存在位置の点で個性的あろうとする)ことをしない(没個性的である)。また、画一的な自分たちの中で個性的になろう(自分たちとは別の位置を占めようとする)個人の存在を、認めようとせず、自分たちのいる位置へ引っ張り込もうとする(異なる意見の持ち主に対して寛容でない)。このように、互いに心理的に同一の存在位置にいることを指向することは、画一(同質)指向という言葉でまとめることができ、ウェットな行動様式と言える。皆が同じ心理的存在位置を取ることは、その位置に皆が密集することであり、その点、密集指向とも関係がある。
一方、各個人が他者へと心理的に近接しようとする度合いが小さい場合、人々は相互に引き付け、まとまり合う度合いが少なく、存在する位置が、互いにバラバラに離れている(多様である)のを許容する。空間内での分布のはずれ値が多い(分布の幅が大きい)。互いに相手とは異なる独自の位置に存在する、という思いから、自分とは異なる意見の持ち主の存在に対して寛容である。このように心理的にバラバラ・多様な位置を占めることを指向することは、多様性の尊重ないし異質指向という言葉でまとめることができ、ドライな行動様式と言える。各自が互いに離れた別々の心理的存在位置にいようとすることは、各自の居場所が心理的に広く分散していると言え、広域分散指向とも関係がある。
○A1.4 同調指向(ウェット)-反同調指向(ドライ)
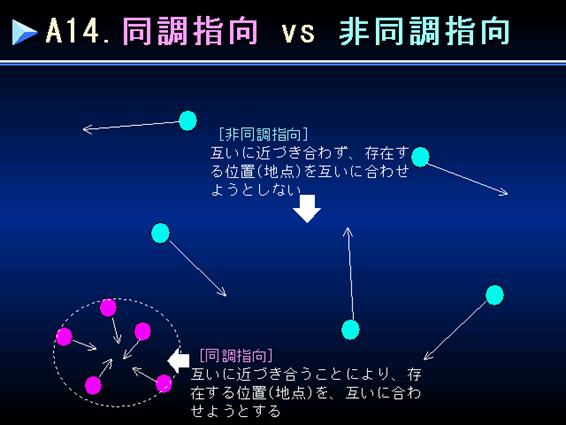
|
A1.4 |
ドライ=反同調指向 |
ウェット=同調指向 |
|
定義 |
取る行動を互いに合わせようとしない |
取る行動を互いに合わせようとする |
|
No. |
[例↓] |
[例↓] |
|
1 |
周囲の皆と違ったことをしようとする |
周囲の皆と同じことをしようとする |
|
2 |
他人の真似をするのを好まない |
他人の真似をするのを好む |
|
3 |
個性的であろうとする |
没個性的であろうとする |
[説明]
自分の行動や進行方向を周囲の他者に合わせよう(互いに同じにしよう)とすること(同調への指向)は、周囲の他者と心理的な位置を同じくしようとして、近づき合うことを意味する。同じ心理的位置を共有する仲間の数がより多く集まることで、その心理的位置における人口密度が高まる。それは、個人間に心理的引力が働いて、その結果、同一の心理的位置に各人が密集したことを指す。周囲の他者と同じことをしようとする(周囲の他者の真似をする)ことは、心理的に互いに同質化して近づこうとする(同一の位置を占めようとする)ことを意味する。意見の同じ者だけでまとまろうとするのも、相互の心理的同質性を確保して、心理的に同じ位置を持つことで、互いに一体・融合化しようとする姿勢の現れである。一人だけ孤立するのを避けて没個性的であろうとするのも同じ行動様式である。こうした指向の持ち主は、だれかと一緒にいないと不安で仕方がない。孤独に耐えられない。これらの行動様式は、いずれも、心理面引力を働かせて、互いにひとまとまりになって心理的に同じところにいようとする動機を含んでいる。このように、周囲の他者と行動を同調させることへの指向、すなわち同調指向は、周囲の他者と互いに心理的に同一の位置を保持することにつながり、ウェットな行動様式と言える。
各自が他者へと心理的に近接しようとする度合いが小さい環境下では、個人は、心理面で、互いにひとまとまりになろうとする引力から自由になって、互いに別々の(違った)、独自の(個性的な)位置を確保することが可能である。周囲の他者と心理的位置を共有する方向への引力が働かないので、行動を周囲の他者に合わせようとすることがない(周囲の皆と違ったことをする、他人の真似をしない。周囲からの孤立を恐れない。)このように、周囲の他者に行動を同調させないことへの指向(反同調指向)は、周囲の他者と心理的な近接を行おうとしない点、ドライな行動様式と言える。
○A1.5 主流指向(権威主義)(ウェット)-非主流指向(反権威主義)(ドライ)
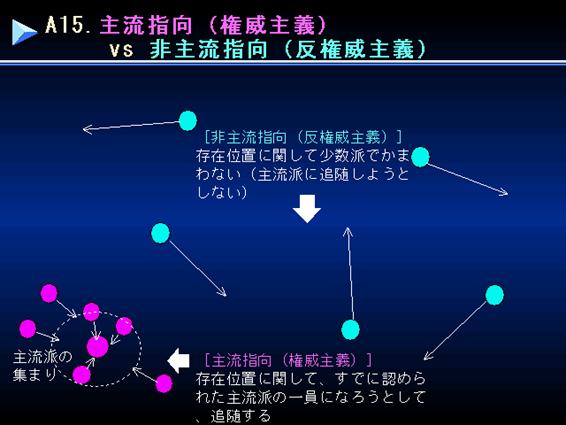
[例]
|
A1.5 |
ドライ=非主流指向(反権威主義) |
ウェット=主流指向(権威主義) |
|
定義 |
自分の取る意見について主流でなくて構わないとする |
自分の取る意見について(すでに認められた)主流派の後を付いて行こうとする |
|
No. |
[例↓] |
[例↓] |
|
1 |
少数派に属するので構わないとする |
主流派の一員でいようとする |
|
2 |
権威あるとされる者の言うことを信じにくい |
権威あるとされる者の言うことを信じやすい |
|
3 |
ブランドにこだわらない |
物を購入するときブランドにこだわる |
[説明]
主流とは、相対的により多数の人々が既に集まっている方の集団のことである。そうした主流を指向するのは、皆が既に大勢集まっているところ(メジャーなところ)に自分も行ってその仲間に加わろうとすることを意味する。そうした、既に人数がたくさんいる多数派・主流派と一緒になろうとする主流、メジャー指向は、心理的には、既に人々が沢山密集している位置と、自分のいる位置を合わせよう、同じにしようとすることになり、より大勢と互いに近接し、くっつこうとする点、ウェットな行動と言える。
権威ある者(例えば、有名大学医学部の教授や、高級ブランド品のデザイナー)は、その周囲に既に心理的追従者が沢山集まっており、その存在を既に揺るぎないものとした多数派(主流派)の中での中心人物として位置づけられる。そういう意味で、権威ある者のいる辺りは、最も心理的な人口密度が高い。権威を信じることは、心理的な高人口密度の中に参加できることを約束するものであり、権威あるとされる者のいうことを信じたり、後追いをしやすいこと(権威ある商品ブランドに対する信仰など)は、心理的距離空間内において沢山人が集まっている人口密度の高いところに自分も行きたい、密集したいと考えやすいことを指し、互いに集まり合うという、心理的引力を行使することにつながる点、主流指向の一形態であり、ウェットな行動様式と言える。
主流を指向しない(非主流であろう、マイナー指向であろうとする)のは、少数派で構わないという行動様式である。人があまり集まっていない、閑散とした方に行こうとすることである。閑散としたところは、人口密度の低い、人々があまりおらず、互いに離れているところを指し、そうしたところに行くことを指向する、非主流、マイナー指向の行動様式は、ドライな行動様式であると言える。
権威を信じないことは、権威に引き寄せられた多数派(主流派)の人々の中に進んで入ろうとしないことであり、あえて主流に入らない、集まろうとしないで、独自の道を歩もうとする行動様式である。心理的距離空間内において、他者が密集しているところ(権威ある者や彼らが作った商品のあるところ)に集まろうとしない、距離を取ろうとする行動であり、その点、非主流指向の一形態であると言える。これは、ドライな行動様式である。
(追記)
なお、身分との関係については、上流階級が、その社会の中でより主流の重要な位置を占めており、一方下層階級は、マイナーな、目立たない非主流の地位に追いやられている。
上流階級を指向する(例えば、上流階級の文化を自分も真似ようとする高級指向の)行動は、社会的主流派に属しようとする、すなわち、皆が憧れ行きたがる、集まりたがる社会的位置に自分も行こうとする行動であり、その点ウェットであると言える。
また、身分の上下にうるさくこだわり区別する態度は、自分が社会的に偉い=権威がある、主流であるかどうかにこだわることであり、主流派の価値観に染まっていることを示す。その点、主流指向であり、ウェットであると言える。
こうした身分の上下を区別することへの指向の強さと、当人が実際に属している身分の高さとは、必ずしも一致しないと見られる。例えば、日本において、「お上」=官公庁の権威に対して恭順する態度を取る下層階級の庶民は、「お上」=「官」という組織が持つ、主流の価値を無批判に受け入れ、それに合わせようとしている点、例え、その所属が非主流であっても、主流指向であり、ウェットである。
◎A2.他者との関係・縁故の構築(ウェット) -非構築(ドライ)
他者との間に関係・縁故を積極的に築こうとするかどうかについての次元が存在する。互いに心理的引力によって他者を指向する者同士が、互いに指向し合った他者と新たに心理的に結合・接続した状態をそのまま維持することで、縁故を作り出す。
○A2.1 関係・接続指向(ウェット)-非関係・切断指向(ドライ)
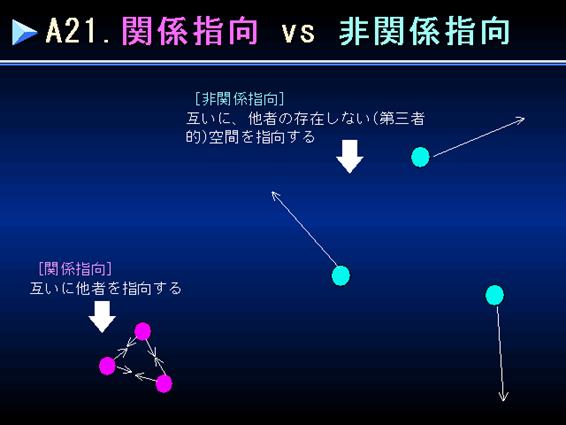
|
A2.1 |
ドライ=非関係・切断指向 |
ウェット=関係・接続指向 |
|
定義 |
他者との間であまり人間関係を持とうとしない(関係を切ろうとする) |
他者との間に積極的に人間関係を持とう、つながろうとする |
|
No. |
[例↓] |
[例↓] |
|
1 |
他人との触れ合いを好まない |
他人との触れ合いを好む |
|
2 |
周囲の他者に良い印象を与えようとは特に気にしない |
周囲の他者に良い印象を与えようといつも気にする |
|
3 |
人付き合いのあり方がよそよそしい |
人付き合いのあり方が親密である |
|
4 |
自分の内面を他者に開示したがらない |
自分の内面を他者に開示したがる |
[説明]
各個人に、他者へと心理的に近接しようとする考えが働いている状態では、個人は互いに自分が他者を引力によって自分のもとへと引き寄せる、あるいは他者に近づくことで、互いに他者を指向することになる。すなわち、他者と互いに引き付け合い、近づき合う関係に入ることを重視するようになる(人間関係そのものを重視する)。相互に引き付け合うことで、互いに他者と十分な近さまで近づきあうことで、触れ合うようになることを好み、その結果、相互の関係は親密なものとなる。互いに近い距離にいる、同じ位置を共有するようになり、心理的な面からは互いに共感し合う状態になる。自分と他者とが、互いに引き付け合って心理的・物理的に一体化することを望みやすくなる(愛という言葉を使うのを好む)。互いに心理的に近い存在になろうとするために、周囲の他者に気に入られようとしたり、よい印象を与えようと気にしたりする。あるいは、自分の内面を他者に対して積極的に開示して、互いに相手と関心を共有しようとする(ことで心理的に同じ位置を占めよう、心理的に近づこうとする)。このように相手との関係を積極的に築こう(結合、接続しよう、つながろう)とすることは、関係指向ないし接続指向という言葉でまとめることができ、ウェットな行動様式と言える。関係指向は、他の人間を直接の指向対象とすることから、人間指向ということもできる。
各個人が、周囲の他者と心理的に近づこうとしない状態では、互いを引力によって引き寄せ、近づき合う、互いに他者(人間)を指向するという契機に欠ける。その点で、人間関係を何かの手段としてしかみない。相互に引き付け合って近づくことがないため、他人との触れ合いを好まず、人付き合いのあり方がよそよそしい。互いに心理的にバラバラな位置にいるので、互いに共感し合うことが少ないし、相互間の配慮も少ない(足りない)。互いに相手と関心を共有しようということがないため、自分の内面を相手に開示したがらないし、相手にあえて気に入られようとすることもない。自分たち人間とはかけ離れた、無機物を指向する。このように、互いに心理的に離れたままでいようとして、他者との関係を築くことを指向しない(ないし、相手との関係を切る、断つことを指向する)のは、非関係指向ないし切断指向という言葉でまとめることができ、ドライな行動様式と言える。
○A2.2 縁故指向(ウェット)-非縁故指向(ドライ)
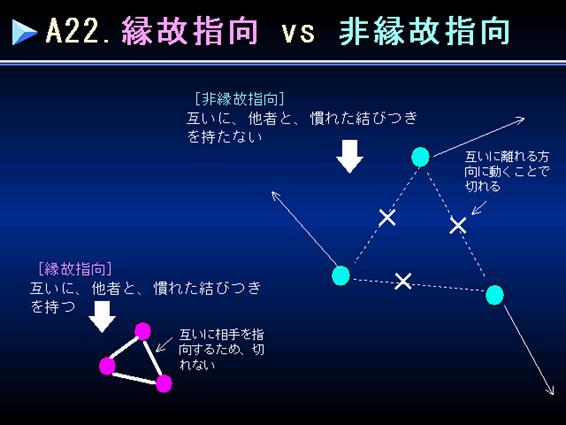
|
A2.2 |
ドライ=非縁故指向 |
ウェット=縁故指向 |
|
定義 |
他者との関係を持つ上で既存の縁故の有無を問わない |
既に結び付き(縁故)のある他者との関係を優先する |
|
No. |
[例↓] |
[例↓] |
|
1 |
縁故(コネ)を重んじない |
人付き合いで縁故(コネ)を重んじる |
|
2 |
親分子分関係を好まない |
人付き合いで親分子分関係を好む |
[説明]
個人同士が互いに心理的な引力によって、くっつき合う(心理的に一体化し合う)状態になるのを繰り返すことによって、人と人との間の結合 connection自体に慣れが生じる(結びついた状態が日常化し、癒着が生じる)。人間同士が互いに慣れた結びつきを持って、互いに引力を及ぼしている状態が「縁故がある」ことになる、と考えられる。相互に心理的に近づくおかげで人間同士が強い紐帯、癒着を持つに至ることが可能となる。相互間の引力によって互いに結びついていることが当然となった人間同士の関係は、血縁関係で結ばれた家族同様のレベルまで深まることもしばしばであり、そのときには、家族的な雰囲気を現すようになる、と考えられる(実の親子と擬制する親分子分関係など)。このように相互間の強い結合が日常化・長期化することを指向するのは、縁故指向という言葉でまとめることができ、ウェットな行動様式と言える。
各自の持つ、他者にくっつこうとする引力が小さいと、他者との結合connectionが生まれにくく、縁故ができにくい。人間同士の紐帯、癒着が弱い。あるいは、人付き合いのレベルが浅く、家族的でない。相互間の結合が生じにくい状態を指向するのは、非縁故指向という言葉でまとめることができ、ドライな行動様式と言える。
◎A3.行動決定の自由(ドライ)-不自由(ウェット)
自分の思った方向に自由に行くことができるかどうかについての次元が存在する。互いの間に心理的に近接しようとする引力が働いていると、その引力がしがらみとなって、人々は心理的に自由に動けなくなる。
○A3.1 規制主義(ウェット)-自由主義(ドライ)
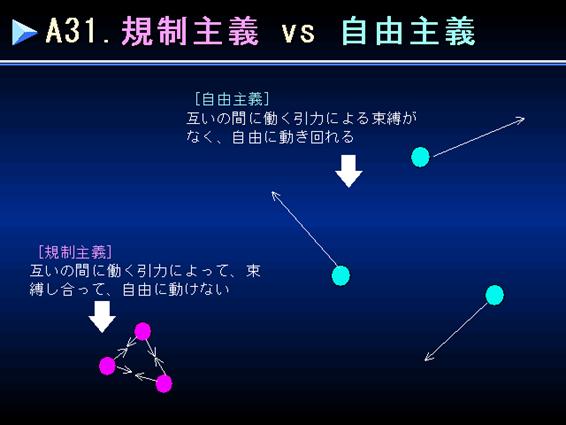
|
A3.1 |
ドライ=自由主義 |
ウェット=規制主義 |
|
定義 |
互いに自由に行動しよう(動き回ろう)とする |
互いに行動を規制し合う |
|
No. |
[例↓] |
[例↓] |
|
1 |
行動の自由を規制されることを好まない |
行動の自由を規制されることを好む |
|
2 |
互いに自由に行動することを許す |
互いに相手の行動を牽制し合う(足を引っ張り合う) |
|
3 |
互いに束縛しあうのを好まない |
互いに束縛しあうのを好む |
|
4 |
抜け駆けを許す |
集団内で一人だけの抜け駆けを許さない |
|
5 |
失敗を犯した本人のみの責任とする |
一人の犯した失敗でも周囲の仲間との連帯責任とする |
[説明]
各個人が他者に対して心理的に近づこうとして働かせる引力が大きいと、その引力がしがらみとなって、各人は、自分の当初進みたいと思う方向へ向かって、自由に動き回ることができなくなる。心理的引力は、個人同士の互いの動きを、互いに近づき合って、牽制・束縛・拘束し合う(足を引っ張り合う)方向に向かわせる。こうした相互の動きを縛り合う人間同士の引力が働いた状態が、「規制」がある状態である。人間関係において、互いの間に引力が働いていると、それが人間同士の自由な行動を抑え込む力となって(しがらみとなって)、身動きが取れなくなる。
個人同士の間に引力が働いている状態では、一人が周囲から外れた行動を起こそうとすると、周囲の他者からの、相手が一人離れて行くことを許さない、一緒にくっついたままでいようとする引力によって、その行動を規制される。これが、足の引っ張り合いや、しがらみがある、行動の自由がない、と行動を起こした本人に感じられるもととなる。
心理的引力の存在する状態で、一人が行動を起こすと、引力が働いているため、周囲の他者がついでに引っ張られてしまうなど影響が広く及ぶため、行動を起こした結果(例えば失敗)についての責任は、行動を起こした本人一人のみに限定されず、周囲の皆の連帯責任と見なすことになる。こうした状況では、個人が単独で自由行動を完遂するのは不可能である。そのため、周囲の他者が同意しない限り行動を起こさない、といった方策が取られることになる。
心理的引力がある集団内では、一人だけの抜け駆けができなくなる。一人が抜け駆けしようとすると、引力が、抜け駆けしようとする本人と周囲の他者との間に働いて、周囲の幾人かもそれにつられて動いてしまったり、周囲の他者が抜け駆けしようとする本人に対して、自分たちの中に引き戻そうとする力を働かせようとするためである。一人だけで動こうとしても、周囲の他者との間に働く、複数の互いの近さを維持しようとする心理的引力がしがらみとなって、自由に動けない。
このように互いの動きを規制し合う状態を指向することは、規制主義という言葉でまとめることができ、ウェットな行動様式と言える。
一方、個人が他者に対して働かせる心理的引力が小さいと、個人同士は、互いに近づき合って、束縛・牽制し合うことがあまりない(人間関係のしがらみがなく、自由に身動きできる)。自分がある方向に動こうとしたときに、互いに引力で相手の足を引っ張り合うことなく、だれにも規制されずに自由に動き回ることができる。一人一人が、互いに周囲の状況から独立して(抜け駆けしてなど)、自由に自分の行きたい方向へと、常に進むことができる(互いに自由に行動することを許す)。行動を起こした結果に対する責任は、行動した本人にのみ限定することが可能である。このように互いに自由に動き回れる状態を指向することは、自由主義という言葉でまとめることができ、ドライな行動様式と言える。
◎A4.行動の自己決定(ドライ) -非決定(ウェット)
自分の行動の決定が自分だけでできるかどうか(他者の意向に沿う必要があるかどうか)についての次元が存在する。心理的な引力が働いていると、互いに自分の行動が自分一人では決められず、周囲の他者の動向次第になってくる。
○A4.1 相互依存指向(ウェット)-独立・自立指向(ドライ)
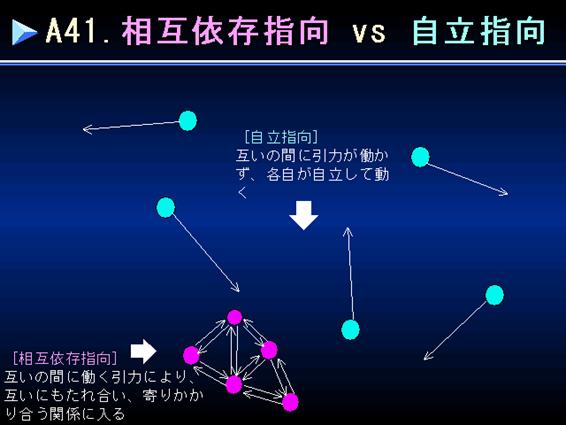
|
A4.1 |
ドライ=独立・自立指向 |
ウェット=相互依存指向 |
|
定義 |
互いに独立・自立して行動する |
互いに依存し合う(もたれ合う) |
|
No. |
[例↓] |
[例↓] |
|
1 |
互いに自立しているのを好む |
人付き合いで互いにもたれあうのを好む |
|
2 |
独立心が強い |
依頼心が強い |
|
3 |
甘えを嫌う |
互いに甘えあおうとする |
|
4 |
派閥を作るのを嫌う |
派閥を作りたがる |
[説明]
各個人が周囲の他者に対して心理的に近づこうとしている状態では、互いに引き付け、くっつき合うことで、互いに相手に寄りかかりあう、すなわち、相互にもたれ合う関係になる。心理的引力が強いと、自分の行動が相互に相手の行動次第で決まるようになる。自分の行動が相手の動きに依存する。自分のあり方を決めるのに、相手へ心理的に寄りかかる度合いが増える。相互に寄りかかりあうことで、互いに相手の状態に依存し合うことになる。互いに、相手に寄りすがろうと することになり、その点依頼心(甘え)が強くなる。言い換えれば、心理的引力が強いと、自分の行動が相互に相手の行動次第で決まるようになる。その点、自 分の行動が相手の動きに依存する。すなわち、行動が相互依存的になる。また、自分のあり方を決める相手へと心理的に寄り掛かる度合いが増えて、依頼心が強 くなることになる。これは、各自が互いに依存し合う状態で、ひとまとまりになり(=派閥を作り)、外部に対して、一つにまとまった自分たちの勢力をアピー ルしようとすることにもつながる。このような相互にもたれ合う関係への指向は、相互依存指向という言葉でまとめることができ、心理的引力に基づく指向であ ることから、ウェットな行動様式と言える。
一方、各個人が周囲の他者に対して心理的に近づこう、心理的引力を行使しようとしない場合、個人が自分の動きを決定するのに、周囲の他者の動きの影響を受けることが少なくなり、自分のことは自分で決定して行動できる(周囲の他者に行動を依存しないで済む。周囲の他者に自分の行動を決定される度合いが少ない)。その点、周囲の他者からは独立・自立している。互いに寄りかかり合うことがなく、依頼心(甘え)は少ない。こうした独立・自立ヘの指向は、心理的引力が弱く、互いに無関係に動き回る場合に顕著となることから、ドライな行動様式と言える。
○A4.2 他律指向(ウェット)-自律指向(ドライ)
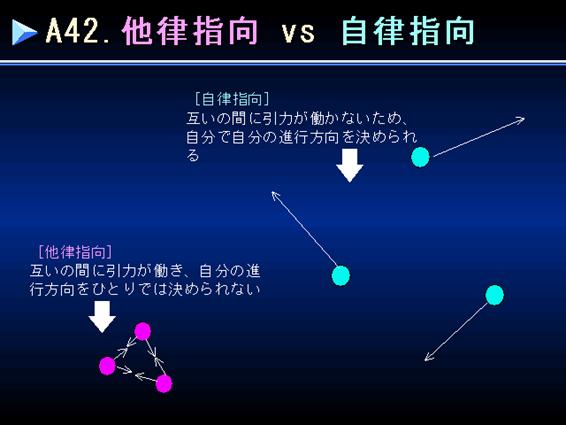
|
A4.2 |
ドライ=自律指向 |
ウェット=他律指向 |
|
定義 |
自分で自分の意思を決められる |
自分の意思を自分だけでは決められず、周囲に決定を任せる |
|
No. |
[例↓] |
[例↓] |
|
1 |
自分の意見を持っている |
周囲の意見に左右されやすい |
|
2 |
周囲の流行に振り回されない(左右されない) |
周囲の流行に振り回される |
|
3 |
自分の今後の進路を自分一人で決められる |
決められない(周囲の影響を受ける) |
[説明]
他者と互いに心理的に近接しようとする引力の只中にいる個人は、自分の行動や進行方向を、周囲の他者によって決定されることを指向する(ないし、せざるを得ない)。引力の働いている状態では、各人が周囲の他者からの相手を自分から離れようとさせない引力の影響(牽制など)を受けて、自分の動く方向を好む好まざるとにかかわらず変える必要に迫られる(自主性が保てない)。自分の進路は、自分の周囲に存在する他者由来の引力との兼ね合いで決まり、自分一人だけで決めることはできない。その意味で、周囲の他者による影響が大きい。すなわち、自分の動きが単独独立で決まらず、周囲との文脈によって決定される「文脈依存的」な行動を取ることになる。
周囲の流行に振り回されるということは、周囲から発せられる心理的な引力(友人による「私は既に○○したわ。あなたも○○しない?(そうすることで私と一緒にならない?)」といった勧誘)に引かれるままに動くことである。引力は、その中にいる個人に対して、起こす行動における主体性の欠如した、周囲の意見に左右されやすい(自分の意見を持っていない)状態を引き起こす。このように、周囲の他者からの引力に自分の行動や進行方向を任せた(預けた)状態になるのを指向することは、他律指向と言う言葉でまとめることができ、ウェットな行動様式と言える。
一方、他者との間における心理的近接の度合いが小さい場合、各人は、自分の行動や進行方向を、周囲の他者からの引力に影響されず、自分一人で決定することができる(自主性を保てる)。自分の動く方向を、周囲の他者の動きに合わせて変える必要がない。周囲の動向(流行など)に振り回されず、自分の意見を持ち続けることが可能である。自分の行動・進行方向を周囲の他者からの引力に影響されずに一人で決めることができる状態を指向することは、自律指向という言葉でまとめることができ、ドライな行動様式と言える。
◎A5.プライバシーの確保(ドライ) -不確保(ウェット)
自分の私事を秘密にすることができるかどうかについての次元が存在する。他者に対して心理的近接を試みることは、その分他者および自己のプライベートな領域を侵害する可能性を絶えずはらんでいる(他者に近づく分、自分の状態が他者に丸見えになる)。また、相手との距離を近く保とうとする心理的引力の働いている状態では、互いに他者に対して何らかの行動を起こすことで、反作用として、他者から、他者自身が何を考えていたかフィードバックを得ることができ、互いのプライバシーは侵害される。
○A5.1 反プライバシー(ウェット)-プライバシー尊重(ドライ)
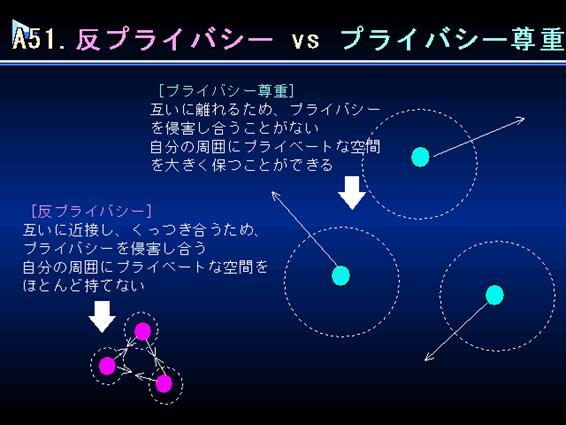
|
A5.1 |
ドライ=プライバシー尊重 |
ウェット=反プライバシー |
|
定義 |
互いのプライバシーを重んじる |
互いのプライバシーを重んじない |
|
No. |
[例↓] |
[例↓] |
|
1 |
他人のプライバシーには干渉しない |
他人のプライバシーに介入したがる |
|
2 |
互いに監視しあうのを好まない |
互いに監視しあうのを好む |
|
3 |
他人のうわさ話をするのを好まない |
他人のうわさ話をするのを好む |
|
4 |
当局への密告を好まない |
当局への密告を好む |
|
5 |
自分が他人にどう見られるかを気にしない |
自分が他人にどう見られるかを気にする |
|
6 |
化粧をするのを好まない |
化粧をするのを好む |
[説明]
他者と心理的に近づくことによって、頻繁にくっつき合い、接触し合うことは、互いのプライベートな空間への絶え間ない侵入を引き起こすことにつながり、他者(ないし自己)のプライバシーへの干渉(私事への介入)に結びつく。他人のうわさ話をするのを好む、ないし当局に他人の動向を密告しようとすることは、自分が(話や密告の種となる)他者のことを監視し、他者のプライバシーに介入するのを好むことを示す。
自分が他人にどう見られるかを気にするのは、周囲の他者からのまなざしによる牽制・監視を通じて、互いに何をしているか、互いに自分から離れて何か変なことを起こしはしないかを気にする、互いのプライベートな領域に侵入し合う(プライバシーに介入し合う)引力の存在を感じるからである。化粧をしたり、容姿、服飾に気をつかうのは、そうした他者による、自分のことをを牽制する視線の存在を予め意識して、自分の外観(顔や服装)を他者に効果的に映るように (他者を逆に牽制する形で)コントロールすることである。こうした化粧、服飾行動は、他者の視線を一身に集めることで、他者を心理的に自分の身の回りに近づけ、積極的にプライバシーを放棄することにつながる。見栄を張るのも、他者に自分がよく見えるように、自分の見た目をつくろうことであり、他者の視線による牽制を前提とした行動である。
こうした相互監視・相互牽制によるプライバシーへの干渉が起きやすいことは、互いの間に心理的引力が働いていることと相関関係にあり、ウェットな行動様式であると言える。
一方、他者に心理的に近づく度合いが小さいと、互いにくっつき合う(接触し合う)ことがないため、互いのプライベートな空間へと侵入を引き起こすことがなくなり、プライバシーが尊重された状態が保たれる。この状態では、互いに視線の送り合いやうわさ話、密告などで、相手を監視・牽制し合う、といったことがなくなる。こうした状態を好むのは、心理的引力を働かせようとしない点、ドライな行動様式であると言える。
◎A6.行動の明快さや合理性の確保(ドライ) -不確保(ウェット)
自分の行動に明快さや合理性を保つことができるかどうかについての次元が存在する。個人が、当初単独で明快・合理的に行動しようと思っても、周囲から引力という名の横やりが入ったり、周囲の人々の動向が気になると、行動はいつのまにかあいまいで非合理的なものになってしまう。
○A6.1 あいまい指向(ウェット)-反あいまい(明快)指向(ドライ)
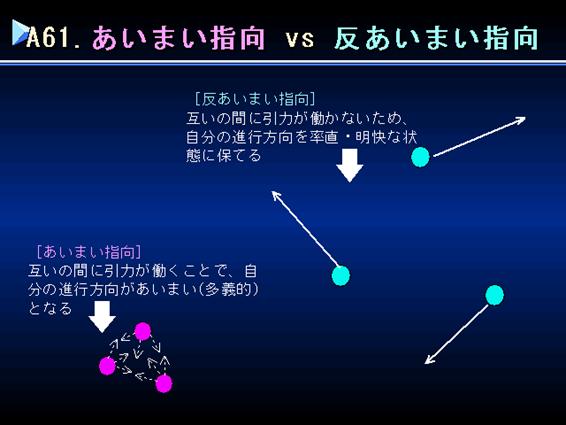
|
A6.1 |
ドライ=反あいまい(明快)指向 |
ウェット=あいまい指向 |
|
定義 |
自分の取る意見が率直・明快である |
自分の取る意見がが率直・明快でない |
|
No. |
[例↓] |
[例↓] |
|
1 |
物の言い方が率直である |
遠回し・婉曲である |
|
2 |
物事の白黒をはっきりさせようとする |
あいまいなままにとどめようとする |
|
3 |
自分の今後の進路をはっきりさせようとする |
あいまいなままにとどめようとする |
○A6.2 非合理指向(ウェット)-合理指向(ドライ)
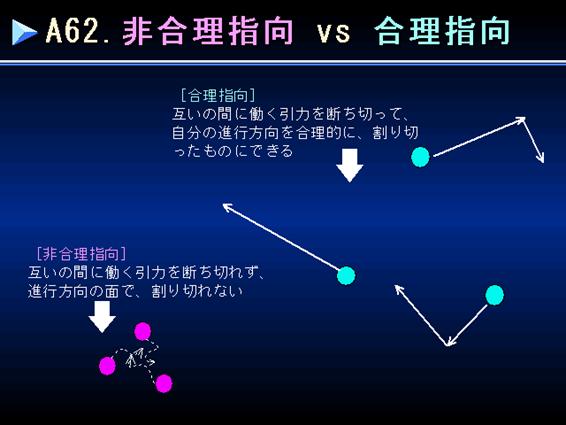
|
A.6.2 |
ドライ=合理指向 |
ウェット=非合理指向 |
|
定義 |
物事に対して心情的に割り切って、合理的に行動する |
物事に対して心情的に割り切ることができず、合理的でない |
|
No. |
[例↓] |
[例↓] |
|
1 |
考え方が合理的である |
非合理的である |
|
2 |
考え方が科学的である |
非科学的である |
|
3 |
宗教を信じない |
宗教を信じる |
[説明]
ある個人が特定の方向に進もうとしたとき、自分の周囲の多方面から引力を受けると、その影響で、進行方向があいまいとなる。すなわち、心理的引力が働く対人関係においては、当初明確な意図を持って動こうとしたとしても、周囲の他者からの引力による介入・調整の繰り返しにより、いつしか進行方向があいまい、不明瞭(玉虫色)となる。物の言い方も、率直さに欠けた遠回し・婉曲なものになる。
また、他者との相互間に引力が働く環境下では、周囲の他者からの、相互の近さを保とうとする引力による介入を断ち切れず、割り切った行動を取れないため、自分のいったん決めた方向に向かってまっすぐ進むことができず、合理的な論理や計画が、曲げられてしまう。進む方向が、その場の周囲からの引力の働く方向 (雰囲気)に絶えず影響されて、一時の感情にまかせて、気まぐれにアトランダムに変わってしまうため、自分で論理的な方針を組み立てることができず、合理的な方向へと進んでいくことができない。
このように、人が周囲に対してあいまい・非合理的な行動様式を取ることは、心理的引力がもたらすところのウェットさに基づく。
他者との間に働く心理的引力が少ない状態では、個人の動き(今後の進路を含めて)が、周囲の他者からの引力による干渉を受けて曲がることがないので、まっすぐ(率直)・はっきり(明快)な状態を続けることが容易である。当初明確な意図を持って動こうとしたとき、周囲の他者からの心理的引力による介入・調整がないので、進行方向がはっきりした、明確な状態を続けることができる(あいまいさが生じない)。物を言うに当たって、的に向かってずばり直球を投げ込むように、率直さを保てる。
また、他者との間に心理的引力が働かない状態では、周囲の他者からの引力による介入から自由になることができ、割り切った行動を取れるため、自分のいったん決めた方向に向かってまっすぐ進むことができ、合理的な論理や計画が、曲げられることなく貫徹可能である。進む方向が、引力に影響されることがないため、自分で論理的な方針を組み立てることが可能であり、合理的な方向へと進んでいくことができる。
このように、人が周囲に対して明確な、あいまいでない、合理的・論理的な行動様式を取ることは、心理的引力から自由なドライさに基づく。
◎A7.集団の開放性の確保(ドライ) -不確保(ウェット)
集団の表面を閉じようとする力(表面張力)が働いているかどうかについての次元が存在する。集団内部に互いに引き付け合ってまとまろうとする力(集団凝集性)が強ければ、集団は外部に対して門戸を閉ざすこととなる。
○A7.1 閉鎖指向(ウェット)-開放指向(ドライ)
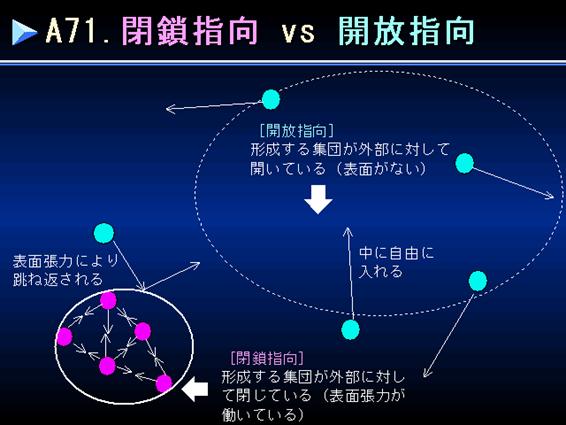
|
A7.1 |
ドライ=開放指向 |
ウェット=閉鎖指向 |
|
定義 |
開放的な集団にいるのを好む |
閉鎖的な集団にいるのを好む |
|
No. |
[例↓] |
[例↓] |
|
1 |
開放的な人間関係を好む |
閉鎖的な人間関係を好む |
|
2 |
身内・外の区別にこだわらない |
人付き合いで身内・外の区別にこだわる |
|
3 |
集団外のことにも関心を持つ |
自分の属する集団内のことにしか関心がない |
|
4 |
仲間内以外の人も受け入れる |
付き合いで仲間内以外の人を排除する |
[説明]
各個人が他者に近づこうとする心理的引力がある状態では、各人の間に、互いに距離を縮める方向へとスクラムを組み、自分の属する集団の表面積を互いに手を取り合ってできるだけ小さくしようする力が対人関係において働いており、他者は形成済の集団の表面から中に入ることができない。こうした力は、1)外部の者を中に入れようとしない、2)集団内の仲間が表面から外に出ようとすると中に引きずり込もうとするものであり、物理的液体における「表面張力」に相当する。こうした状態では、人々は閉鎖的な対人関係を好み、自分が属する集団・仲間内の相手としか付き合おうとしない(自分の属する集団内のことにしか関心がない)。こうした表面張力のような力が働いている閉鎖指向は、心理的引力に基づくウェットな行動様式であると言える。
他者に近づこうとする心理的引力がない状態では、集団の表面部分~内部の各人が互いに手を取り合って結託し、よそ者を入れようとしない表面張力のようなものは、対人関係において存在せず、形成済の集団の表面から中に入ることが容易に可能である(外部の者に対して中が開放されている。集団内の仲間が表面から外に出るのも自由である)。開放的な対人関係を好み、自分が属する集団・仲間外の相手とも付き合おうとする(自分の属する集団外のことにも関心を持つ)。こうした表面張力が存在しない開放指向は、心理的引力とは無縁のドライな行動様式であると言える。
●B.心理的運動・活動・移動・流動指向(ドライ)-静止・非活動・定着・定住指向(ウェット)
あちこち活発に動き回ろう、移動しようとする指向の強さに関する。
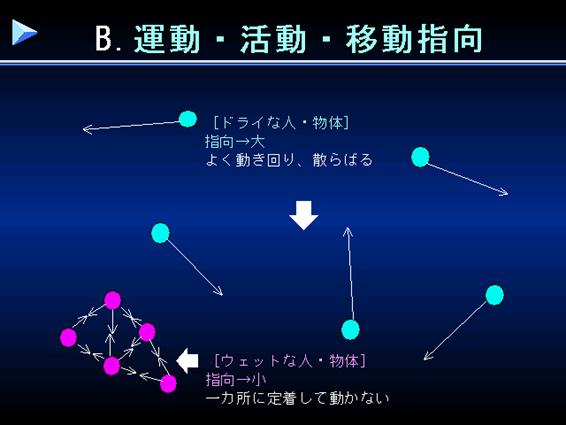
◎B1.動的エネルギー・移動性の確保(ドライ) -不確保(ウェット)
心理的な運動エネルギーが大きいかどうかについての次元が存在する。自分から進んで積極的に動き回ろう、拡散しようとする心理的な運動エネルギーが大きいと、他者からの心理的な引っ張りや牽制から自由になれる。
○B1.1 静的指向(ウェット)-動的指向(ドライ)
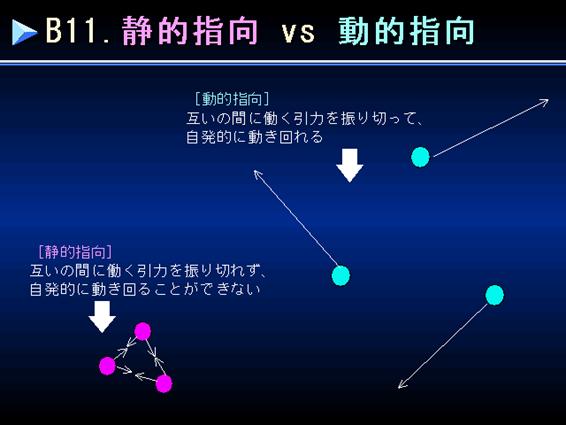
|
B1.1 |
ドライ=動的指向 |
ウェット=静的指向 |
|
定義 |
よく動き回ろうとする |
動き回ろうとしない |
|
No. |
[例↓] |
[例↓] |
|
1 |
動作がすばやい |
動作がゆっくりである |
|
2 |
物事の決定のテンポが速い |
テンポがゆっくりである |
|
3 |
行動が積極的である |
行動が消極的である |
[説明]
もしも、各人の自分から進んで自発的に積極的に動き回ろうとする活動性(運動エネルギー)が、相対的に小さい(速度がゆっくりである)と、当人はその場に静止してとどまることになり、人と人との間の心理的引力を振り切って動き回ることができにくい。運動エネルギーが小さくて、対人間に働く心理的引力に囚われがちな静的状態への指向(静的指向)は、ウェットな行動様式と言える。
一方、各人の、自分から進んで自発的に積極的に動き回ろうとする、活動性(運動エネルギー)が、(気体分子同様)相対的に大きい(速い)と、当人はその場に静止することなく動き回ることになり、個人間の心理的引力を振り切るだけの運動エネルギーにあふれている。このように、運動エネルギーが大きくて、対人間に働く心理的引力に囚われない動的状態への指向は、動的指向という言葉でまとめられ、ドライな行動様式と言える。
○B1.2 定着指向(ウェット)-非定着(移動・拡散)指向(ドライ)
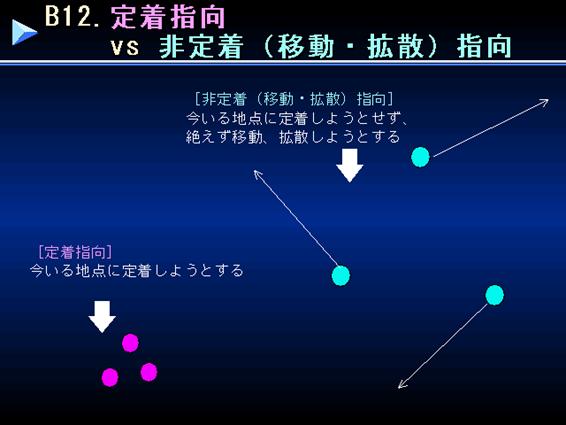
|
B1.2 |
ドライ=非定着(移動・拡散)指向 |
ウェット=定着指向 |
|
定義 |
今いる土地や組織に定着せず絶えず移動しようとする |
今いる土地や組織に定着しようとする |
|
No. |
[例↓] |
[例↓] |
|
1 |
絶えず移動する(遊牧)生活を好む |
一カ所に定住する(農耕)生活を好む |
|
2 |
人事が流動的なのを好む |
人事が停滞しているのを好む |
|
3 |
短期的契約関係を好む |
長期にわたる取引関係を作るのを好む |
|
4 |
常に新分野へと拡散しようとする |
いつまでも今までいた分野にとどまろうとする |
[説明]
自分から進んで動こうとする運動エネルギーに欠けていて、かつ、心理的引力の只中で、自分がある方向に移動しようとすると必ずそれに対する引き戻しの力がかかる状態では、個人は、いつまでも既存の、今まで、自分がその場所に存在したり、その中に所属していた、集団などの対人関係(組織)の中に、外に拡散することができずに、現状維持のままとどまり続ける(定着、定住し続ける)。人間関係が固定的(人事が停滞的)だったり、相手との取引関係が長期にわたるようになる。これは、定着指向という言葉でまとめられる。
自分から進んで動こうとする運動エネルギーに満ちていて、心理的引力が小さい状態では、個人は、自由に、今までいた場所や、所属していた集団を離れて、一カ所に定着することなく、新しい境地へと絶えず動き回ることが可能である。この状態では、人間関係は、流動的な(短期契約的で、すぐ切れやすい)ものとなり、短期間で次々所属する組織を変わることになる。これは非定着指向という言葉でまとめられる。
○B1.3 前例指向(ウェット)-独創指向(ドライ)
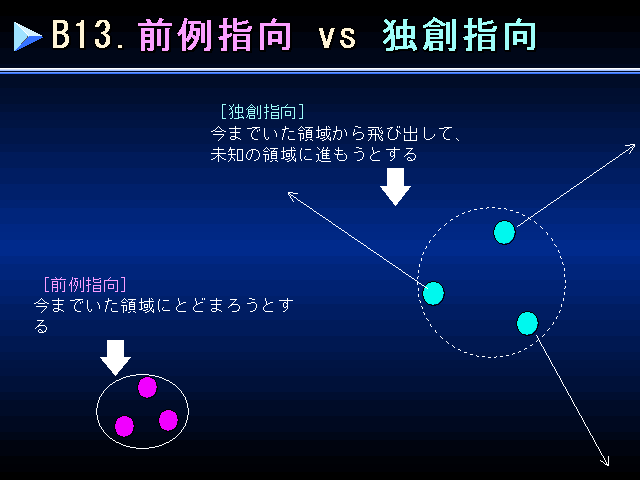
|
B1.3 |
ドライ=独創指向 |
ウェット=前例指向 |
|
定義 |
誰も行ったことのない未知の領域に進もうとする |
自分が今までいた領域にとどまろうとする |
|
No. |
[例↓] |
[例↓] |
|
1 |
行動の基準を新規の独創的なアイデアに求める |
行動の基準を既存のしきたり・前例に求める |
|
2 |
前人未踏のことにもあえて挑戦する |
前例があることだけをしようとする |
|
3 |
現状を変革するのを好む |
現状をそのまま追認するのを好む |
[説明]
今までいたところに、いつまでも、居続けようとする(一カ所に定住・定着する)状況下では、個人は、新境地(新分野)への移動・拡散性が欠如しており(冒険しようとしない)、行動の基準を、従来から存在するしきたりや前例に求める。しきたりや前例は、定住先で生活するために従来必要であった知識の蓄積であ り、その有効性に関してチェックを行わないまま(今までと同じ環境下に居続けるのであれば不要である)、無批判にそのまま受け入れることになる(現状の追認を好む)。新天地へ積極的に出ようとする姿勢が欠如しているため、自分のアイデンティティ確立を、既に定評のある、前例に当たる知識や方法との、暗記に よる一体化を行うことで果たす。しきたり・前例に関する知識の暗記量で人間の価値を推し量ろうとする(心の中での前例蓄積量や質によって人間の価値が決ま る)。人間関係を、前例を沢山蓄積している先輩と、蓄積量が少ない後輩との差別によって把握する、年功序列が常識化する。年功序列で上位の人間が、下位の人間を、ただそれだけの理由で支配する、先輩後輩関係を重視しようとする。これは、前例指向という言葉でまとめられる。
今までいたところから絶えず動き回ろうとする状況下では、個人は、新境地(新分野)への移動・拡散性にあふれており(冒険したがる、前人未踏のことに挑戦したがる)、行動の基準を、従来にない新規の独創的なアイデアに求める。しきたりや前例の暗記よりも、新たな知識の創造や、現状の変革を重んじる。こうした行動様式は、独創指向という言葉でまとめられる。
上記のうち、静的・定着・前例指向の行動様式は、ウェットな感覚を与える液体分子群(水など)において、コップなど、ふたのない容器に入れておいても、いつまでもその中にいて、外に拡散していくことがない(蒸発は、気体分子になることで初めて可能になる)現象と、同様であると考えられ、ウェットな行動様式と言える。
一方、動的・非定着・独創指向の行動様式は、ドライな感覚を与える気体分子群(空気など)において、いったん容器に閉じ込めておいた状態でふたを取ると、すぐに外に拡散してそこからいなくなってしまう現象と同様であると考えられ、ドライな行動様式と言える。
上記の今回整理した内容から、性格、行動様式などにおけるドライ・ウェットさの概念が、集団主義・個人主義、自由主義・規制主義、プライバシー尊重の有無など、これまで個別にバラバラに議論されてきた、社会学、心理学や政治学上の様々な概念をまとめ、関連づける上位概念として、今後より有望視、重要視されるようになることが予想される。
例えば、行動様式や文化の分類について、上位概念としてのドライ・ウェットさを導入することで、従来は別々に捉えられてきた集団主義-個人主義、規制主義-自由主義の概念が互いに「集団主義と規制主義とは、どちらもウェットである」、「個人主義と自由主義とは、どちらもドライである」のようにリンク付けて捉えられるようになる。そして、このことから、例えば、「個人主義と自由主義とは(両方ともドライであり)互いに関連し合って同時に起こる、見られる」、「アメリカのような個人主義の国(人)は、同時に自由主義の国(人)である」ということが言えるようになる。
つまり、今回抽出した、集団主義-個人主義、規制主義-自由主義といった、様々なドライ・ウェットな性格・行動様式は、互いに独立・バラバラに発生するのではなく、ドライに属するもの同士(個人主義、自由主義、プライバシー尊重・・・)、ウェットに属するもの同士(集団主義、規制主義、反プライバシー・・・)、互いに関連し合って同時並行的に発生する、観察されるものであると言える。
抽出した行動様式のドライ・ウェットさについての確認
上記の抽出した行動様式が本当にドライ・ウェットと感じられるかどうかについて、個別の行動様式項目毎に「この行動様式は、ウェット・ドライのどちらに感じられますか?」と尋ねるweb質問紙調査を1999年5~7月にかけて、1質問項目当たり約200名の回答者という規模で行い、当方の上記の考え方がほぼ正しいことを確認した。
web質問紙調査(確認用)手順、web質問紙調査(確認用)結果数値は、著者による湿度感覚と気体、液体に関する他著作を参照されたい。
まとめ
上記結果から、
(1)ドライな行動様式の人は、対人関係において、運動・活動性が高く、相手へと近接しようとする指向が弱い人である
(2)ウェットな行動様式の人は、対人関係において、運動・活動性が低く、相手へと近接しようとする指向が強い人である
とまとめられる。
分かりやすく言い換えれば、対人関係で、互いに他者とベタベタくっつき合って動かないのが好きな人がウェットで、他者とバラバラに離れて活発に動き回るのが好きな人がドライということになる。要約すれば、「相互離散・移動=ドライ、相互近接・定着=ウェット」ということになる。
人間が、対人関係の中で他者に与えるドライ・ウェットな感覚は、運動エネルギーの大小や、引力・粘着力(分子間力相当)の強弱という点で、それぞれ気体・液体分子や、乾いた・湿った物体一般が人間にもたらす感覚(ドライ・ウェット)と、本質的に同じ起源を持つ、と考えられる。
分析対象(群)の動きのパターンを、以下のパターンDと、パターンWとに区別する。
Dは、ドライ=Dry(乾いた)、Wは、ウェット=Wet(湿った)の頭文字である。
パターンD、パターンWの動きを、動画で示したものを巻末図表中に設けている。
(動画は、元は、パターンWは液体分子運動、パターンDは気体分子運動のコンピュータシミュレーションから作成したものである。)
|
[法則] (1)パターンDに出会う、当たる、触れると、ドライ(Dry、乾いた)と感じる。 |
パターンD、パターンWの特徴を、言葉で表現すると、以下のようになる。
|
分析視点 |
パターンW |
パターンD |
|
1.動作方向 |
近接 |
離散 |
|
(1)近づき |
くっつく。近づく。 |
サラリと離れる。離反する。 |
|
(2)つながり |
連続する。つながる。癒着する。 |
(関係を)切断する。 |
|
(3)着床 |
付く。粘着する。 |
はがれる。 |
|
(4)まとわりつき |
まとわりつく。なつく。 |
別れる。 |
|
(5)集合 |
集まる。密度が高い。 |
散る。密度が低い。 |
|
(6)一つ |
一体・融合化する。一つになる。 |
バラバラである。互いに独立している。 |
|
(7)同じ |
同じである。 |
違う。別の途を歩む。 |
|
2.動作速度 |
低速 |
高速 |
|
(1)速度 |
ゆっくりである。 |
速い。 |
|
例 |
液体分子運動。 |
気体分子運動。 |
分析対象の(知覚される)湿度は、パターンDに近づくに従って低く(ドライに)なり、パターンWに近づくに従って高く(ウェットに)なる。
対象の動く速度は、パターンDに近づくほど高く、パターンWに近づくほど低い。
対象の動く方向は、パターンDに近づくほど互いに引力が働かず離れ離れになり、パターンWに近づくほど互いに引力が働くため、近づき、くっつく。
よって、分析対象の(知覚される)湿度は、
・対象の動く速度が、高速で動くほど低く、低速で動くほど高くなる。
・対象の動く方向が、離れるほど低く、近づく~くっつくほど高くなる。
人間の皮膚触覚、視聴覚での物体知覚において、
パターンD(互いにバラバラに離れて、くっつかず、個別に散らばり、高速で動く)の分子群~物体群が肌に当たる(接触する)、見える、耳で存在を確かめられると、ドライに感じられる。
パターンW(互いにくっついて離れず、高密度、集団で分布し、低速で動く)の分子群~物体群が肌に当たる(接触する)、見える、耳で存在を確かめられると、ウェットに感じられる。
人間が、人付き合いの中で、
パターンDの人間関係(互いにバラバラに離散、自立して、別々に自由に高速で動き回る)に当たる(接触する)と、心の内部でドライに感じられる。
パターンWの人間関係(互いにくっつき一体化して離れない、一緒に低速で動く)に当たる(接触する)と、心の内部でウェットに感じられる。
パターンDとパターンWは、それが、皮膚触覚、視覚、対人関係・心理的距離知覚といった異なるモードの知覚で生起した場合においても、神経系内の共通のパターン認識野(パターンDとパターンWを判別する分野)を活性化させ、湿度判定出力をもたらすと言える。
-農業(遊牧・農耕)の視点から-
1999.1-2005.8 大塚いわお
ここでは、環境のドライ・ウェットさと、社会や対人関係におけるドライ・ウェットさとの関連を、主に、農業のあり方を軸に考察した結果についてまとめる。
なぜ、農業のあり方を考察の軸に選んだかの理由であるが、農業は、
(1)その遂行において、直接自然環境と接する、その意味で、自然環境の影響が大きい産業である。これは、例えば、穀物や野菜、牧草の栽培において、気温の寒暖、降水量、風速などの影響をもろに受ける点に現れている。
(2)食糧の確保という、人間の生活を支える上で最も基本的と考えられる産業である。人間社会の基盤・土台部分を形成し、社会風土の方向性を決定する上で影響力が大きい。これは、例えば、日本社会では、農業と直接関係のない分野(例えば厚生・労働)の官庁・会社組織などにおいても、農業村落の特質である「ムラ社会的」という形容が広く使われる点に現れている。
自然環境のドライ・ウェットさがその社会にもたらす影響を考える上では、自然環境との関わりが大きく、かつ社会全体に対する影響力が大きい産業である農業分野における社会関係のドライ・ウェットさについて、その社会を代表して考察すればよいのではないかと考えられる。
農業は、全世界的観点から見ると、遊牧(牧畜)と農耕に2分される。
遊牧(牧畜)は、馬や牛、羊などの動物(家畜)と共に、動物の食物(牧草)や水などを求めてあちらこちらを移動し、その生産物(乳、肉、皮など)を得て生活する。移動可能な動物と一緒に生活する分、その生活は動的、身軽である。自らが移動できなくなるような物資の蓄積を好まず、物資の流動(フロー)を指向する。
農耕は、穀物(稲、麦など)、野菜、果物など、植物を栽培して、その生産物(実、種など)を得て生活する。一つの場所に生えたまま移動することのできない植物と一緒に生活する分、その生活は静的、身重であり、一カ所に定着して動かず(不動)、物資、財産を蓄積(ストック)すること(物持ち)を指向する。
遊牧(牧畜)は、砂漠、ステップ地帯のような、雨の比較的少ない、ドライな自然環境で行われる。
農耕は、モンスーン地帯のように、(植物が育つのに必要な)雨が沢山降る、水の豊かなウェットな自然環境で行われる。
|
農業の分類 |
自然環境 |
生活をともにする |
生活パターンと |
物資の扱い |
機動性 |
|
遊牧(牧畜) |
乾燥(ドライ、気体) |
動物 |
移動(動的) |
流動(フロー重視) |
大(身軽) |
|
農耕 |
湿潤(ウェット、液体) |
植物 |
不動・定着(静的) |
蓄積(ストック重視) |
小(身重) |
1999.5~7にかけて行ったWWWを用いて行ったアンケート調査結果においては、態度のドライ・ウェットさについては、遊牧=ドライ、農耕=ウェットという回答結果が出た(回答者数約200名)。
|
番号 |
項目内容 |
-ドライ- |
どちらで |
-ドライ- |
項目内容 |
-Z得点- |
有意 |
|
B10 |
遊牧生活を好む |
62.727 |
20.909 |
16.364 |
農耕生活を好む |
7.733 |
0.01 |
上記の表から、農耕社会における対人関係がウェットで、遊牧社会における対人関係がドライである、と言えることが分かった。
なぜ、農耕社会の対人関係がウェットとなり、遊牧社会における対人関係がドライと感じられるか?についての考えられる説明は以下の通りである。
〔集団主義・同調指向(農耕)-個人主義・非同調指向(遊牧)〕
農耕は、稲作における田植えや稲刈り作業のように、周囲の皆と同じ作業を団体・集団一斉に行う必要があり、周囲との集団としての一体性、同調性、協調性が求められる。したがってウェットである。
遊牧は、各自が個々にバラバラな違う方向に馬や牛を連れて行って放牧を行う農業であり、単独・独自行動が多く、周囲との同調性は求められない。したがってドライである。
〔定着・縁故指向(農耕)-非定着・非縁故指向(遊牧)〕
農耕は、一カ所に定住する定着指向の農業であり、固定した地縁関係が築かれやすく、したがってウェットである。
遊牧は、一カ所に定住せずあちこち動き回る非定着指向の農業であり、相互の関係は切れやすく、したがってドライである。
〔関係指向(農耕)-非関係指向(遊牧)〕
農耕は、定住した近所同士が毎日顔を突き合わせる関係にあり、対立しても顔を合わせるはめに陥る。そこで、同じ場所に住んでいる者同士、なるべく互いに仲良くしよう、対立しないようにしようとして、良好な人間関係(和合状態)の構築・維持に心を砕く。その点、ウェットである。
遊牧は、今日互いに近い場所にいても、明日はバラバラに離れて別々の場所に行く。意見が対立し仲が悪くなっても、互いに別々の場所に移動して離れてしまえばそれで互いに顔を合わせることなく済んでしまう。したがって、良好な人間関係(和合状態)の維持にはさほど関心がなく、その点ドライである。
〔規制主義(農耕)-自由主義(遊牧)〕
農耕は、稲作における農業水利のように、携わる人間同士の相互監視・牽制が不可欠である(例えば、稲作社会において、各人が用水を勝手に自分の田んぼにたくさん引かないように互いに見張ることなど)。その意味で規制主義的であり、したがってウェットである。
遊牧は、広大な草原を、他者に束縛されずに、自由に動き回る。その意味で自由主義的であり、したがってドライである。
〔相互依存指向(農耕)-自立指向(遊牧)〕
農耕は、稲作における農業水利のように、携わる人間同士が互いに依存し合う。一方が沢山水を取ると、他方の取る水が少なくなる。あるいは、農耕においては、水路、道路の維持や収穫作業のように、独力では作業が不可能で、互いに助け合う形の集団作業が必要となる。その意味で、相互依存指向といえ、対人関係としてはウェットである。
遊牧は、携わる人間同士が、互いに一人で自立して動かなければならない。彼らは、広い草原をただ独りで馬に乗って走り回り、放牧作業を自力でこなすことが求められる。その意味で自立指向といえ、対人関係としてはドライである。
〔密集指向(農耕)-広域分散指向(遊牧)〕
農耕は、集約的農業であり、少ない面積の土地に集中的に人的・物的資源を投入する。それに携わる人間が住む地域は、人口密度が高い。したがって、密集(過密)指向といえ、対人関係としてはウェットである。
遊牧は、粗放的農業であり、広い面積の土地に、分布する人はわずかである。それに携わる人間が住む地域は、人口密度が低い。したがって、広域分散指向といえ、対人関係としてはドライである。
以上の説明は、以下の表のようにまとめられる。
|
農業方式 |
自然環境 |
対人関係 |
|
農耕 |
ウェット、液体(モンスーン) |
ウェット、液体的(定着・縁故、関係、集団・同調、規制、相互依存、密集) |
|
遊牧 |
ドライ、気体(砂漠、草原) |
ドライ、気体的(非定着・非縁故、非関係、個人・非同調、自由、自立、広域分散) |
したがって、自然環境のドライ・ウェットさと、対人関係のドライ・ウェットさは、正の相関関係にある、と言えそうである。
要するに、乾いた砂漠、草原の民(ユダヤ、アラブといった遊牧の民)はドライであり、植物の豊かに生える肥沃なオアシスの農耕の民、緑の民(東アジア、東南アジアの稲作農耕民など)はウェットである、ということになる。砂漠ほどは乾いていないが、農耕に全面的に頼れるほど植物が生育しない土地に住んでいて、家畜に頼りながら半分定住、半分移動の生活をしている牧畜・酪農の民(西欧など)は、両者の中間ということになるのかも知れない。
以上の図式からは、日本は、典型的な稲作農耕民族であり、ウェットな類型に入る。一方、欧米は、遊牧系に近い牧畜の民であり、比較的ドライな類型に入る。
この点、世界の各民族の民族性がドライか、ウェットかを判断する上で、その民族が農耕民か、遊牧・牧畜民かをまず知ることが有効であると言える。
本当に以上のように言えるかどうか、を確認するには、世界各地(乾燥・湿潤両方)の社会を回って、対人関係が乾燥地帯でドライ、湿潤地帯でウェットであることを、フィールドワークで確認する必要があることは、言うまでもない。
(c)1999-2005 大塚いわお
以下では、男女の間の対人行動面における性差を、ウェット対ドライの次元から説明する。
対人感覚の「ウェットさ」に関しては、従来から、「女性的」なものと、関連があるとされてきた。例えば、〔芳賀綏1979〕においては、日本人の特徴として、「おだやかで、きめ細かく、『ウェット』で、『女性的』で、内気な」(強調筆者)といったものをあげており、上記の表現では、ウェットさと女性性との間に関係があるように示されている。しかし、芳賀は、ウェットさと女性性との間の相関について、実証データをもとに割り出したという訳ではなく、あくまでも漠然とした印象の形でしか、捉えていない。
そこで、「女性的」=「ウェット」(「男性的」=「ドライ」)という図式が実際に成り立つかどうかを確かめるために、当調査において抽出した対人関係パターンを、男女の行動面での性差に関する、主要な学説と照合し、表にまとめた(学説抽出に当たっては、〔間宮1979〕〔Mitchell 1981〕〔皆本1986〕などを主に参考にした)。
〔男女の行動面での性差と、対人感覚のドライ・ウェットさとの関連:まとめの表〕
表中、文字列の赤色は、ウェットさ、青色は、ドライさを表しています。
全て、女性→ウェット、男性→ドライ、という結びつきとなっています(逆のパターンは、見つかりませんでした)。
なお、表中の「→B20 互いに集まる.....」といった表記は、表中の記述内容に対応する、ドライ・ウェットな性格・態度とは何かに関するアンケート回答項目を示しています。
|
〔1〕個人主義-集団主義 |
出典 |
|
男性は特定の理由で集まるが、女性は単に集まるために集まる→B20 互いに集まること自体を好む/何か目的がないと集まらない |
Mitchell 1981 |
|
女子社員の多い職場では、必ずといってよいほど、いくつかのグループができる。女性は、とくに、集団を好み、楽しむようだ。 |
影山1968 |
|
女性は、心身ごと人や事と融合して一体化する傾向があり、愛情や感情移入を示しやすい→A14 他者との一体化・融合を好む |
間宮1979 |
|
女性は、全体の中に自分を調和させる(埋没させる)行為に快感を味わう→A14 他者との一体化・融合を好む |
皆本1986 |
|
男性的な権力の使い方は、個人を重視し、個人の功績を賞賛し、個人を集団から分離するのに対して、女性的な権力の使い方は、集団の幸福と他人との関係を促進する |
Bakan 1966 |
|
〔2〕自立指向-相互依存指向 |
|
|
なし |
|
|
〔3〕広域分散指向-密集指向 |
|
|
女子は、細部に着目するような認知の速さや、手先の器用さに優れるのに対して、男子は、細部よりも、全体に着目して物事を考える。女性は、(男性のように)広い視野に立って思慮し判断をせず、感情的に断定を下す→F22 ものごとを見る視野の広さ |
間宮1979 |
|
男性は、他人との距離を、女性の場合より大きく取りたがるのに対して、女性は、人の物理的接近に対して、男性より寛容(肯定的)である |
Mitchell1981 |
|
男性は密集した状態を女性よりも不快に感じる→A3 広い空間に分散 |
Deaux 1976 |
|
女性は、(男性のような)個人と個人との二元的対置が困難である。→C3 物の見方が客観的でない |
間宮1979 |
|
女性は、ものごとを客観的に見ないで、問題を人間対人間の感情の問題に置き換える |
影山1968 |
|
女性は、中心へ密集する傾向を持ち、男性は周辺へ分散する傾向を持つ→A3 狭い空間に密集/広い空間に分散、F24 中央集権/地方分権 |
Mitchell 1981 |
|
男性は孤独に耐え、転任による独居も、女性ほどには痛痒を感じない。→E32 互いに離れているのを好む |
間宮1979 |
|
〔4〕多様性の尊重-画一指向 |
|
|
男児の方が、自由が多く、(行動が)型にはまることが少ない、予測しがたい。 |
Mitchell 1981 |
|
女子は、男子に比べて、カテゴリーの規準から逸脱する幅が少ないし、カテゴリーが狭い→B17 画一的な枠にはめようとする |
Wallach1959 |
|
〔5〕非人間指向-人間指向 |
|
|
男性は、原料、物体、機械的問題、あるいは抽象的概念のようなことを取り扱う職業の追求に心を奪われる...(のに対して)女性の世界は、..はるかにもっぱら人々の世界であり、他者の願望や期待に非常に敏感である。女性は、他者を判断する際、男性よりも、感知力がある。→E27 人間関係そのものを重視 |
Newcomb1965 |
|
男子は、物事を直接的に研究し、操作するのに対して、女子では事物よりも人間の声や顔など対人関係に引かれ..対人的交流に適合した言語機能がよく発達する→E27 人間関係そのものを重視 |
間宮1979 |
|
男子の描くモチーフは車・飛行機など..無機物であるのに対して、女子の描く主役は有機物である。...女性画には擬人化が多い。→F42 無機物/有機物を扱うのを好む |
皆本1986 |
|
〔6〕非縁故指向-縁故指向 |
|
|
なし |
|
|
〔7〕自由主義-規制主義 |
|
|
上司が、女性に注意する時は、一方的にあなたが間違っていますというよりは、自分にも責任があるような言い方をすれば非常に効果が上がる。→B15 一人の犯した失敗でも周囲の仲間との連帯責任とする |
影山1968 |
|
〔8〕自律指向-他律指向 |
|
|
女性は、自我が自律的でなく、他人との関係によって維持される |
Mitchell 1981 |
|
女性は、自主的な判断や自信をもって決断することを躊躇する→C38 取る行動に自主性がある/ない |
間宮1979 |
|
女性は、他者の期待や願望に非常に敏感である→A23 周囲の意見に左右されやすい |
Newcomb1965 |
|
男子は、学習活動に対する自我関与の程度が高いのに対して、女子は、課題の成否よりも、成績に対する(親や教師など周囲の他者の)要求水準や、(周囲との)対人比較に裏付けられた意欲が高い→A23 周囲の意見に左右されやすい |
間宮1979 |
|
〔9〕反同調指向-同調指向 |
|
|
女性は、まわりへの気兼ねから、本心とは違った意思表示をしたり、しばしば本心とは逆の行動様式を取る→B9 行動を周囲の人々に合わせようとする |
影山1968 |
|
女子は、仲間との適合性が高く、(周囲との)判断の不調和にもそれに同調して自己の判断を変えるか、不調和に耐えて友人関係を維持するの対して、男子は、自己の判断に固執し、仲のよい友人でも同調できにくいし、不調和のままに耐えることも不得手である。→B9 行動を周囲の人々に合わせようとする/しない |
間宮1979 |
|
男性は、自己表現を尊ぶが、他者との協調的表現に関心が乏しいのに対して、女性は、自己主張より、他者との調和、他者への奉仕に大きな価値を感じる。→B9 行動を周囲の人々に合わせようとする/しない |
皆本1986 |
|
女性は男性に比べて同調性が高く、同情的であるし、影響力の強い人間に同一化しやすい→C34 周囲に同調したがる |
Schwarz1949 |
|
使う言語の文法的な特徴が標準からはずれていることについて..女は男よりはるかに気にしやすい。 |
Trudgill 1974 |
|
〔10〕反権威主義-権威主義 |
|
|
女子の方が、自己防衛のためにおとなの権威を援用しようとする |
間宮1979 |
|
女の方が男よりも標準変種や威信を持つと見なされている訛りに近い形の言葉を使う...権威ある特徴の発音を使う率が、社会階級を考慮に入れても、女は男よりはるかに高い....女は男より「良い」(正しい)形の発音を使う率が高い。 |
Trudgill 1974 |
|
〔11〕プライバシー尊重-反プライバシー |
|
|
なし |
|
|
〔12〕反あいまい指向-あいまい指向 |
|
|
女性は、男性に比べ、退嬰的で、明確な態度を表明しない →A9 物の言い方が率直/遠回し |
間宮1979 |
|
女子は、万遍なく全教科を習得しようとする(筆者注:教科に対する指向が不明確である)のに対して、男子は、得意な教科にエネルギーを集中し、不得意・退屈な教科には力を抜く(筆者注:教科に対する指向が明確である)→B18 自分の今後の進路をはっきりさせようとする/しない |
間宮1979 |
|
男性は原色を使い、中間色を避けるが、女性は多く使う→A22 物事の白黒をはっきりさせる/あいまいにとどめようとする |
皆本1986 |
|
男性画は、特定の色やモチーフに関心を集中し、他を切り捨てる(筆者注:色に対する指向が明確である)のに対して、女性の色使いは、特定色に偏るのを避けて、どの色も均等に使う。この色を使ったから、あの色も使わねば、と考える(筆者注:色に対する指向が不明確である)→B18 自分の今後の進路をはっきりさせようとする/しない |
皆本1986 |
|
〔13〕合理指向-非合理指向 |
|
|
なし |
|
|
〔14〕動的指向-静的指向 |
|
|
女性は、男性のような強い自己主張を好まない→C14 自己主張 |
皆本1986 |
|
〔15〕非定着指向-定着指向 |
|
|
女児画の中心は、男児画より低めに位置することが多く、どっしりとした安定感がある。女の子は、高いものへの興味が希薄である。→C33 考え方が大地を指向する |
皆本1986 |
|
乗り物類を描く女子は、男子に比べ非常に少ない→A11 一カ所に定着して動かない |
皆本1986 |
|
〔16〕独創指向-前例指向 |
|
|
新しい道具に出会った時、男子は好奇心で目が輝きうれしい様子を示すのに対して、女子は恐怖心を示して尻込みする。→C22 新分野への拡散 |
皆本1986 |
|
女子の方が多くの種類の事象に恐怖反応を示す→D37 冒険しようとしない |
Goldstein 1959 |
|
女子は失敗に当面すると、解決の仕方がでたらめになり、課題場面から逃避する傾向が、男子より目立つ。→D37 冒険しようとしない |
Hermatz 1962 |
|
女子は以前成功した課題に戻る頻度が男子より多く、男子は以前失敗した課題に戻る頻度が女子より多い→D37 冒険しようとしない |
Crandall 1960 |
|
男子は、攻撃性を、反社会的・破壊的な行動の形で表現するのに対して、女子は、合社会的(規則を楯にする)・非破壊的(口先・態度のみ)な行動の形で表現する。女性は、反社会的行動が、男性に比べて少ない。→F30 現状を変革/追認 |
間宮1979 |
|
男性は現状を変えることを望んでいるのに対し、女性は男性が変えた現状に依存するが、自ら現状を変えることには消極的である。→F30 現状を変革/追認 |
皆本1986 |
|
女子の方が環境に適応し、規則を遵守する→F30 現状を変革/追認 |
間宮1979 |
|
〔17〕開放指向-閉鎖指向 |
|
|
女子の方が、排他的閉鎖的派閥を作りやすい |
間宮1979 |
(注) ????マークの付いた文献は、文献抽出で用いた〔間宮1979〕で、データが省略されているため、詳細データが分からなかったものである。
Bakan, D. The duality of human existence. Chicago: Rand-McNally. 1966.
Crandall, V. J., & Robson, S. (1960). Children's repetition choices in an intellectual achievement situation following success and failure. Journal of Genetic Psychology, 1960, 97, 161-168.(間宮1979 p178参照)
Deaux,K.: The Behavior of Women and Men , Monterey, California: Brooks/Cole, 1976
Goldstein, MJ (1959). The relationship between coping and avoiding behavior and response to fear-arousing propaganda. Journal of Abnormal and Social Psychology, 1959, 58, 247-252.(対処的・回避的行動と恐怖を誘発する宣伝に対する反応との関係)
Hermatz,M.C. : ????(間宮1979 p178参照) , 1962
影山裕子 : 女性の能力開発, 日本経営出版会 , 1968
間宮武 : 性差心理学 , 金子書房 , 1979
皆本二三江 : 絵が語る男女の性差 , 東京書籍 , 1986
Mitchell,G. : Human Sex Differences - A Primatologist's Perspective , Van Nostrand Reinhold Company, 1981 (鎮目恭夫訳 : 男と女の性差 サルと人間の比較 , 紀伊国屋書店 , 1983)
Newcomb,T.M.,Turner,R.H.,Converse,P.E. : Social Psycholgy:The Study of Human Interaction, New York: Holt,Rinehart and Winston, 1965 (古畑和孝訳 : 社会心理学 人間の相互作用の研究 ,岩波書店 ,1973)
Schwarz, O, 1949 The psychology of sex / by Oswald Schwarz Penguin, Harmondsworth, Middlesex.
Trudgill,P.:Sociolinguistics: An Introduction, Penguin Books, 1974(土田滋訳 : 言語と社会, 岩波書店, 1975)
Wallach M. A., & Caron A. J. ( 1959). "Attribute criteriality and sex-linked conservatism as determinants of psychological similarity. Journal of Abnormal and Social Psychology, 59, 43-50(心理的類似性の決定因としての帰属的規準性と性別関連の保守性)
Wright,F.: The effects of style and sex of consultants and sex of members in self-study groups , Small Group Behavior, 1976, 7 , p433-456
その結果、以上の表が示すように、従来の学説で取り上げられてきた対人関係と性差との関連は、ほとんど、
(1)女性的=「ウェット(互いに引き付け合い、牽制・束縛しあう力である、相互間引力が大きい)」
(2)男性的=「ドライ(分子間力相当の相互間引力が小さい)」
を示していることが、判明した。言い換えれば、
(1)女性の行動様式は、(分子間力の大きい)液体分子運動パターンに似ている
(2)男性の行動様式は、(分子間力の小さい)気体分子運動パターンに似ている
ということになる。
確認のため、どちらがドライないしウェットか、1999.5~7の、性格・態度のドライ・ウェットさを尋ねるアンケート調査の中で回答してもらったところ、以下のように、「男性的=ドライ」を選んだ人の割合が、「女性的=ドライ」を選んだ人の割合より、有意に多かった。
|
番号 |
項目内容 |
-ドライ- |
どちらで |
-ドライ- |
項目内容 |
-Z得点- |
有意 |
|
C12 |
男性的である |
46.154 |
24.434 |
29.412 |
考え方が女性的である |
2.863 |
0.01 |
こうした両者のウェット/ドライの違いが出る原因としては、女性と男性との、生物学的貴重性の違いが関係していると推定される。
生物学的により貴重な女性は、自分自身の保身のために、よりウェットな行動を取ると考えられる。
ウェットな行動を取ることが、なぜ生物学的に貴重な存在の、自己保身のために有効か、についての詳細な理由については、以下の表を参照されたい。
[行動のウェットさと生物学的貴重性(まとめの表)]
|
ウェット |
生物学的貴重性との関連 |
|
|
1 |
集団主義 |
一人でいるより、みんなと一緒に集まっていた方が、危険が迫ったときに、一人ではできないことを力を合わせて行うことができて、安心である。 |
|
2 |
相互依存指向 |
互いに頼りあったほうが、危険に合ったとき、互いの力を借りることができて、対処しやすい。 |
|
3 |
密集指向 |
分散しているよりも、一つのところに皆で集まっていた方が、皆一緒という感じが持てて、安心感がある。 |
|
4 |
画一指向 |
皆と同じ行動をすることで、周囲の中で一人だけ浮いてしまうことがなくなるようにして、周囲と同類となることで、周囲からの援助が受けやすくなるようになる。 |
|
5 |
人間指向 |
- |
|
6 |
縁故指向 |
人間関係を、予め安心だと分かっているもののみに絞ることで、自分の保身のために、より効果的に活用することができる |
|
7 |
規制主義 |
- |
|
8 |
他律指向 |
自分の行動を周囲まかせにすることで、自分からは、行動が失敗したときの責任を、積極的に負わなくて済むようにする。 |
|
9 |
同調指向 |
周囲の皆(大勢)がすることに合わせる方が、数の論理を頼みにすることができ、より安全なのだと感じて、安心できる。互いに周囲の皆と行動を合わせる方が、大勢の中の一員として振る舞うことができて、自我が拡大して、気分が大きくなり、危険に立ち向かうだけの勇気が得られるように感じる。 |
|
10 |
権威主義 |
周囲の皆が従うところの、安全性を権威ある者によって保証された行動様式に、自らも従うことで、自らの保身を確かなものにしようとする。 |
|
11 |
反プライバシー |
- |
|
12 |
あいまい指向 |
自分の言っていたことを不明瞭にして、いろいろな向きに取ることができるようにしておくことで、失敗して責任追求があったときに、「自分は本当はそうは言っていなかったのだ」として、逃げ易くする。 |
|
13 |
非合理指向 |
- |
|
14 |
静的指向 |
(安全が分かっているところで)あまり動かずじっとしていた方が、動き回って危険な領域に入る心配がなく、保身に有利である。 |
|
15 |
定着指向 |
既に安全だと分かっている場所にずっといつづけることで、新たな場所への移動に伴う新たな危険の発生を防ぐ。 |
|
16 |
前例指向 |
既に安全が保証されたことだけを選んで行うようにして、未知のことを行うことによって起きる予測不能な危険を、避ける。 |
|
17 |
閉鎖指向 |
安全がすでに保証された仲間とだけ一緒にいることで、危険・有害かも知れない外部からのよそものの侵入を防ぐ。 |
上記の、男性・女性の性差と、ドライ・ウェットさとの関連、すなわち、「女性的」=「ウェット」、「男性的」=「ドライ」が、果たして、実際に人々にその通りと感じられているかどうかを検証するためのアンケート調査を行った。
[調査方法]「2つ対にして並べた文章で示された態度のうち、どちらが、より「女々しい」ですか?」と質問する、アンケートページを、インターネットのWebページ検索エンジンに登録し、回答者を募った。
アンケートの項目は、1999.5~7に調査して、有意にドライ(ウェット)と感じられたアンケート項目全体から、(原則としてZ得点5.00以上を得た)40程度の項目を、分類毎にまんべんなく抜き出したものを採用した。
回答期間は、2000.4.中旬であった。
[結果]
回答者総数は約200名であった。男女比はほぼ40:60で若干女性の方が多かった。年令は、10~20代だけで、全体のほぼ90%を占め、圧倒的に若いといえる。
ドライ・ウェットさを示す各態度項目について、各々「より女々しい」「より女々しくない」という判定を下した被験者の割合が、
・「ウェット」な方を、有意な差(水準1%)で「女々しい」とした項目→65.8%(27/41)
・「ドライ」な方を、有意な差(水準1%)で「女々しい」とした項目→2%(1/41)
・有意な差(水準1%)がない項目→31.7%(13/41)
となり、「ウェット」な方を、有意な差(水準1%)で「女々しい」とした項目が、全体の65%を占め、より多かった。逆の項目は、ほとんどなかった。
結論としては、「女々しさ(女らしさ)」と「ウェット・ドライさ」との関連については、回答結果を見る限りでは、現代の若い日本人男女の間では、「女々しさ(女らしさ)」=「ウェット」と捉えられている、と言える。
こうした結果は、1.における、「女性的」=「ウェット」とする文献調査の結果と合致している。
(C)1999.7 -2006.4 大塚 いわお
以下では、日本人の対人関係における特徴(国民性)を、ウェット対ドライの次元から説明する。
1.既存日本人論との照合
対人感覚のドライ・ウェットさのうち、特にウェットさに関しては、従来から、日本人の性格・態度の特徴を表す、とされてきた。例えば、〔芳賀綏1979〕においては、日本人像のアウトラインとして、「おだやかで、きめ細かく、『ウェットで』(強調筆者)、女性的で、内気な」といったように、その中にウェットさを含めて考えている。あるいは、〔吉井博明1997〕においては、日本人のコミュニケーションのあり方の特質について、直接対面によるコミュニケーションの重視の現れを示すものとして、「ウェット」という言葉を用いている。
そこで、こうした見方が果たして正しいかどうか、当調査において抽出した対人関係パターンを、従来提唱されてきた、日本人の伝統的な国民性を現すとされる、主要な学説と照合した(学説抽出に当たっては、〔南1994〕〔青木1990〕などを参考にした)。
その結果、以下の表が示すように、従来の学説で取り上げられてきた日本人の対人関係における特徴は、ほとんど「ウェットさ」を示している。したがって、日本人の 伝統的な対人関係は、基本的にはウェットである、と捉えることができそうことが分かった。言い換えれば、「日本人の伝統的な行動様式は、(分子間力の大きい)液体分子運動パターンに似ている」ということになる。
また、以下の、日本人の国民性として列挙した文献データベース表は、内容的に十分網羅的である(日本人の対人関係上の特徴の大半をカヴァーしている)ことが考えられ、したがって、従来の日本人の国民性とされているものの大半を、「ウェット」というひとことで要約することができることになる。
〔伝統的な日本人論とウェットさとの関連:まとめの表〕
各論が発表された年代順にまとめてあります。
項目の赤色は、ウェットさを表しています。
|
番号 |
項目 |
研究者名 |
要旨 |
抽出した次元 |
対応する欧米文化 |
抽出した次元・欧米 |
|
(1) |
恥の文化 |
R.Benedict (1946) |
自己の行動に対する世評に気を配る。他人の判断を基準にして自己の行動の指針を定める。 |
反プライバシー、他律指向(他者の目を気にする) |
自分の行動の指針を定めるのに、自分自身の判断を基準にする。(罪の文化) |
プライバシー、自律指向 |
|
(2) |
家族的構成 |
川島武宣(1948) |
権威による支配。個人的行動の欠如。自主的な批判・反省を許さない社会規範。親分子分的結合の家族的雰囲気と、対外的な敵対意識。 |
権威主義、集団主義、規制主義、同調指向、縁故指向、閉鎖指向 |
権威への反逆。個人的行動の重視。自主的批判、反省の許可。家族的一体感の欠如と、対外的な開放意識。 |
反権威主義、個人主義、自由主義、反同調指向、非縁故指向、開放指向 |
|
(3) |
終身雇用、年功序列 |
J.C.Abegglen (1958) |
会社と従業員との間に終身的な関係がある。 |
定着指向(組織内定住)、前例指向 |
会社と従業員の関係が、契約的、一時的である。 |
移動指向、独創指向 |
|
(4) |
タテ社会 |
中根千枝(1967) |
「場」と「集団の一体感」によって生れた日本の社会集団は、その組織の性格を、親子関係に擬せられる「タテ」性に求める。 |
閉鎖指向、縁故指向、集団主義、非合理指向 |
組織が水平方向、フラットである。 |
開放指向、非縁故指向、個人主義、合理指向 |
|
(5) |
静的育児 |
Caudill,W., Weinstein, H.(1969) |
日本の母親は、子供と身体的接触を多くし、子供があまり身体を動かさず、環境に対して受動的であるように、子供を静かにさせる。 |
静的指向、相互依存指向、密集指向 |
母親は、子供と身体的接触を少なくし、子供が身体を動かし、環境に対して能動的であるように、子供を動的にさせる(動的育児)。 |
動的指向、自立指向、広域分散指向 |
|
(6) |
中央集権 |
辻清明(1969) |
中央集権的官僚制の強い拘束の前に、近代的な地方自治が完全に窒息せしめられていた歴史を持つ。 |
密集指向(中央への権限の一極集中) |
地方分権的である。権限が地方に移譲されている(地方分権)。 |
広域分散指向(権限の地方分散) |
|
(7) |
同調競争 |
石田雄(1970) |
所属集団に支配的な価値指向と行動様式に従う。他人と同じ行動を取る。 |
同調主義(大勢順応)、画一主義(横並び) |
他人とは別行動を取る(非同調)。 |
非同調指向、多様性の尊重 |
|
(8) |
甘え |
土居健郎(1971) |
日本人は、成人した後も、「母子」間での気持ちの上での緊密な結びつきと同じような情緒的安定を求め続けて行く。 |
相互依存指向、集団主義(一体感) |
母子間の結びつきが薄い。母親に対して情緒的安定を求めない(甘えの欠如)。 |
自立指向、個人主義 |
|
(9) |
間人主義 |
木村敏(1972)・濱口恵俊(1977) |
対人面での相互依存、相互信頼、対人関係の本質視、という特徴を持つ。 |
人間指向(人間関係そのものを重視) |
対人面で、相互自立を重んじ、対人関係を単なる手段として見る(個人主義)。 |
非人間指向(物質指向) |
|
(10) |
他律的 |
荒木博之(1973) |
ムラ的構造の中にあって、個人がその個性を喪失し、集団の意志によってその行動が決定されて行く。 |
他律指向 |
個人が個性を維持し、集団の中においても、個人の意志によって行動を決定する(自律的)。 |
自律指向 |
|
(11) |
集団主義 |
間宏(1973) |
個人と集団の関係で、集団の利害を個人のそれに優先させる。個人と集団が対立する関係ではなくて、一体の関係になるのが望ましい。 |
集団主義 |
個人の利害を、集団のそれに優先させる(個人主義)。 |
個人主義 |
|
(12) |
母性原理 |
河合隼雄(1976) |
「包含する」機能で示され、すべてのものを絶対的な平等性をもって包み込む、母子一体という原理を基礎に持つ。 |
人間指向(ふれあい)、集団主義(一体感) |
母子の一体感が薄い。開放的な父性原理で動く(父性原理)。 |
非人間指向、個人主義 |
|
(13) |
大部屋オフィス |
林周二(1984) |
日本のオフィス空間では、大部屋に多数の社員が机を向かい合わせに並べてがやがやと働いているのに比べて、欧米では社員は個室で働いている。 |
密集指向、反プライバシー(相互監視) |
社員が大部屋ではなく、個室で働く(個室オフィス)。 |
広域分散指向、プライバシー尊重 |
|
(14) |
権威主義、独創性の欠如 |
西澤潤一(1986) |
欧米の権威者の説をあたかも自分の体験のように思い込み、批判したりすると過剰に反応する。欧米の独創技術を自らは危ない橋を渡らずに拾い上げて集中的に実用化する。 |
権威主義(欧米学説に追随したがる)、前例指向(自分からは未知の領域には進もうとしない) |
既存の権威秩序に反抗し、破壊し、新たな独創的知見を生み出そうとする。危ない橋を進んで渡る。 |
反権威主義、独創指向 |
|
(15) |
相互協調的自己 |
Markus,H,R,&北山忍(1991) |
自己を相互に協調し、依存した存在とする。 |
相互依存指向、人間指向 |
自己を相互に独立し、自立した存在とする。(相互独立的自己) |
自立指向、非人間指向 |
|
(16) |
直接対面 |
吉井博明(1997) |
対面コミュニケーションに過重に依存する文化を持ち、集中が集中を呼ぶ体質を内在させている。 |
密集指向(物理的に至近距離)、人間指向(親密さ)、反プライバシー(視線) |
対面コミュニケーションを偏重しない。 |
広域分散指向、非人間指向 |
|
(その他) |
||||||
|
根回し |
|
交渉などをうまく成立させるために、関係方面に予め話し合いをしておく。 |
縁故指向、規制主義 |
交渉時、予め関係方面に話をせず、直接交渉を行う。 |
非縁故指向、自由主義 |
|
|
談合 |
|
互いに相手の動きを、相手が自由な行動(安い入札価格の提示競争)を取らないように、牽制し合って、相互の取る動き(入札価格)を事前の話し合いで決めてしまう。 |
規制主義(自由競争を抑制)、同調指向(相談仲間を作る) |
互いに事前の話し合いをせずに、自分の取る行動を自由に決める。 |
自由主義、非同調指向 |
|
|
政府による規制 |
|
政府が、行政指導などで、業界の動きを牽制・拘束する。 |
規制主義 |
政府が、業界の動きをあまり牽制、拘束しない。 |
自由主義 |
|
|
NOと言えない |
互いに相手に配慮して、相手の言うことを拒絶することができない。 |
人間指向(気に入られようとする)、集団主義(相互批判を許容しない) |
相手の言うことを、きっぱり拒絶する。 |
非人間指向、個人主義 |
〔日本人の伝統的国民性:文献調査結果の詳細〕
以下は、日本人の伝統的な国民性が、ウェットであることを示している、既存の日本人の国民性に関する文献の、大まかな一覧です。 文献の順序は、発表が古い順に並べてあります。 記述は、(1)文献の著者名、題名などの書誌データ、(2)ウェットさに関連する部分の要約、(3)筆者によるアンケート調査項目との関連の仕方についての情報、から成っています。
1.〔恥の文化〕
(書誌)Benedict,R. The Chrysanthemum and the Sword : Patterns of Japanese Culture, Boston Houghton Mifflin, 1948 長谷川松治訳 「菊と刀 - 日本文化の型」社会思想社1948
(要旨)日本文化は、恥の文化に属する。
悪い行いが「世人の前に露顕」しない限り、思い煩う必要がない
恥を感じるためには、実際にその場に他人がいあわせるか、そう思い込む事が必要である → 他律指向
生活において恥が最高の地位を占めているという事は、..各人が自己の行動に対する世評に気を配ることを意味する →人間指向
他人の判断を基準にして自己の行動の方針を定める → 反プライバシー
(アンケート項目との関連)↓
反プライバシー
B24 自分が他人にどう見られるかを気にする
他律指向
E26 周囲の他者の影響を受けやすい
人間指向
E18 周囲の他者に気に入られようとする
E22 周囲の他者によい印象を与えようといつも気にする
2.〔家族的〕
(書誌)川島武宣 日本社会の家族的構成 1948 日本評論社
(要旨)日本の社会は、家族および家族的結合から成り立っており、そこで支配する家族原理は民主主義の原理とは対立的のものである。家族的原理とは、
1 「権威」による支配と、権威への無条件的服従 → 権威主義
2 個人的行動の欠如とそれに由来するところの個人的責任感の欠如 → 集団主義、規制主義
3 一切の自主的な批判・反省を許さぬという社会規範。「ことあげ」することを禁ずる社会規範 → 集団主義
4 親分子分的結合の家族的雰囲気と、その外に対する敵対的意識との対立。「セクショナリズム」。 → 縁故指向、同調指向、閉鎖指向
である。
(アンケート項目との関連)↓
権威主義
D24 権威あるとされる者の言う事を信じやすい
E15 人付き合いで相手の身分・格式を重んじる
集団主義
A1 集団・団体で行動するのを好む
D29 ひとりで他者とは別の道を歩むのを好まない
B22 集団内での相互批判を好まない
規制主義
B15 一人の犯した失敗でも周囲の仲間との連帯責任とする
縁故指向
C24 人付き合いの雰囲気が家族的である
B14 人付き合いで親分子分関係を好む
同調指向
E36 意見の同じ者だけでまとまろうとする
閉鎖指向
B21 人付き合いで身内・外の区別にこだわる
D33 自分が属する集団内の人々としか付き合おうとしない
(書誌)Abegglen, J.C.,The Japanese Factory:Aspects of Its Social Organization, Free Press 1958 占部都美 監訳 「日本の経営」 ダイヤモンド社 1960
(要旨)日本とアメリカの工場組織を比較したときに直ちに気づく決定的な相違点は、日本における会社と従業員との間の終身的関係である(終身雇用)。→定着指向
従業員の給与は主として入社時の教育程度と勤続年数・家族数によって決まり、仕事の種類と仕事をした結果に基づく部分はほんの少しである(年功序列(賃金))。→前例指向
(アンケート項目との関連)↓
定着指向
D15 一つの組織(職場など)に長期間所属しつづけるのを好む(組織内定住)
前例指向
E12 年功序列を重んじる
(書誌) 中根千枝 タテ社会の人間関係 講談社 1967
(要旨)日本では、個人が社会に向かって自分を位置づけるとき、自分のもつ資格よりも「場」を重視する。自分の属する職場、会社、官庁、学 校などを「ウチの」と呼び、一定の契約(雇用上の)関係を結んでいる企業体であるという、自分にとっての客体としての認識ではなく、「私の、またわれわれ の会社」が主体として認識されている。
「イエ」は、「居住」(共同生活)あるいは「経営体」という枠の設定によって構成される社会集団の一つであり、そこでは「場」が重要性を 持つ。「場」という枠による機能集団の構成原理こそ、「イエ」において、全く血のつながりのない他人を後継者・相続者として位置づけて疑問が生じない根拠 である。
資格が異なるものが成員として含まれる日本の社会集団においては、集団のまとまりを強める働きをするのが、一つの枠内の成員に一体感をも たせる働きかけと、集団内の個々人を結ぶ内部組織を生成させて、それを強化させることである。それが、「われわれ」という集団意識の強調であり、「ウチ」 と「ソト」を区別する意識とそれに伴う情緒的な結束感が生れる。→集団主義、閉鎖指向
「場」と「集団の一体感」によって生れた日本の社会集団は、その組織の性格を、親子関係に擬せられる「タテ」性に求める。→ 縁故指向
集団原理を支配する強い情緒的一体感が見いだされる → 集団主義
「タテ社会」性が、日本人の「批判精神の欠如」、「論理性の欠如」を生じさせている→ 集団主義、非合理指向
(アンケート項目との関連)↓
集団主義
A14 他者との一体化・融合を好む
B22 集団内での相互批判を好まない
閉鎖指向
B21 人付き合いで身内・外の区別にこだわる
縁故指向
B14 人付き合いで親分子分関係を好む
非合理指向
C6 考え方が非合理的である
(書誌)Caudill,W., Weinstein, H., Maternal Care and Infant Behavior in Japan and America Psychiatry,32 1969
(要旨)アメリカの母親は、子供の自己主張を明らかにし、母親とは違う存在であることを気づかせ、子供をより独立的にさせてゆく必要があると考えている..日本の母親は、子供との間の相互依存的な関係を発展させ、他人に依存的で従順な子供になることを期待している。
アメリカの母親は、子供に対して声をかけ、活発に働きかけることで関係を持ち、子供がより身体を動かし、環境に働きかけていく事を期待して いる..日本の母親は、子供と身体接触を多くし、子供があまり身体を動かさず、環境に対して受動的であるように、子供を静かにさせる傾向にある
→相互依存指向、静的指向、密集指向
(アンケート項目との関連)↓
相互依存指向
D32 互いに依存しあおうとする
密集指向
E35 他者と肌と肌が触れ合うのを好む
静的指向
F36 静止しているものを好む
(書誌)辻清明 新版 日本官僚制の研究 東京大学出版会 1969
(要旨)わが国は、地方自治法を制定するまでの数十年間、前近代的な中央集権的官僚制の強い拘束の前に、近代的な地方自治が完全に窒息せしめられていた
地方自治法の問題の所在について...「権力的統制」の強い残映をうかがうことができる。
第一..中央官庁による多元的拘束である。地方自治体に対する主たる監督権を掌握していた内務省の支配は廃棄せられたのであるが、同時にそ の他の官庁はいずれも多岐的な地方機関を保有増設し、地方団体の自主的機能を阻害しているとともに、さらにこれらに対して煩瑣な中央的拘束を加えている。
第二..人事権を通してなされる官僚制的拘束である。従来の地方官吏は警察官を除いて地方吏員に切り換えられたのであり、したがって人事 権は地方団体長に所属している。しかしながら、そのことは極めて形式的であり、今後依然として地方吏員の任免・転任などの実権を中央官庁が掌握していく危 険ははなはだ大きい。現在、副知事や助役をはじめとして地方団体の幹部級が、ほとんど従来の内務官吏によって充当されていることは、これを裏書きする。地 方団体長が実質的な強力な人事権を保有できないならば、地方自治に対する中央官庁の権力的統制は、今後といえども隠然として存続する..
→密集指向
(アンケート項目との関連)↓
密集指向
F24 中央集権を好む
(書誌)石田 雄 日本の政治文化 -同調と競争- 東京大学出版会 1970
(要旨)同調と競争の複合..日本の歴史的発展の連続と変化を統一的に説明する上で最も便宜だと考えられる...この視角によって日本の急速な発展とそれに伴う困難とを同時に説明できる
同調 所属集団に支配的な価値指向と行動様式にしたがうこと、すなわち他人と同じ行動を取ること
集団内の強い同調が集団外のものに対する対抗意識を強め、あるいは逆に外からの脅威が集団内の同調を強めるという関係は日本近代のナショナリズムに最もよく示されている
集団内の競争と同調との結びつき....競争と同調との相互補完と相互加速の関係....忠誠競争(同調の中の競争)の結果が忠誠の度合いをいよいよ強め、それによってより強い同調性をもたらし、逆に今度はそのような同調性の中で、より激しい忠誠競争が行われる...
→同調指向
(アンケート項目との関連)↓
同調指向
B9 行動を周囲の人々に合わせようとする
C8 周囲の皆と同じことをしようとする
C34 周囲に同調したがる
E38 主流派の一員でいようとする
(書誌1)土居健郎 「甘え」の構造 弘文堂 1971
(要旨)日本人は、「母子」間の気持ちの上での緊密な結びつきを、生れてから「社会化」の過程において経験する。
日本人は、成人した後も、家庭の内外で、母親依存と同じような情緒的な安定を求め続けてゆく。
甘えの心理は、人間存在に本来つきものの分離の事実を否定し、分離の痛みを止揚しようとすることである。
甘えの精神は、非論理的で閉鎖的....甘えの「他人依存性」
→非合理指向、閉鎖指向、相互依存指向
(アンケート項目との関連)↓
相互依存指向
B2 互いに甘え合おうとする
A2 人付き合いで互いにもたれ合うのを好む
A15 依頼心が強い
集団主義
A14 他者との一体化・融合を好む
非合理指向
C6 考え方が非合理的である
閉鎖指向
閉鎖的な人間関係を好む
(書誌1)木村敏 人と人との間 弘文堂 1972
(要旨)日本人が「自己」を意識して言う、「自分」とは、西洋人の場合と違い、確たる個人主体の「自我」ではなく、恒常的に確立された主体ではない
selfとは、...結局のところは自己の独自性、自己の実質であって、...selfと言われるゆえんは、それが恒常的に同一性と連続性を保ち続けている点にある。
日本語で言う「自分」は、自分自身の外部に、具体的には自分と相手との間にそのつど見いだされ、そこからの分け前としてその都度獲得されてくる現実性である
日本的なものの見方、考え方においては、自分が誰であるのか、相手が誰であるのかは、自分と相手との間の人間的関係の例から決定されてくる。個人が個人としてアイデンティファイされる前にまず人間関係がある
→ 人間指向
(アンケート項目との関連)↓
人間指向
E27 人間関係そのものを重視する
(書誌2)浜口恵俊 「日本らしさ」の再発見 日本経済新聞社 1977
(要旨)日本人の特性である「間人主義」は、個人主義の、自己中心主義、自己依拠主義、対人関係の手段視、という特徴に対して、相互依存主義、相互信頼主義、対人関係の本質視、という特徴を持つ。→ 相互依存指向、人間指向
(アンケート項目との関連)↓
相互依存主義
D32 互いに依存しあおうとする
人間指向
E27 人間関係そのものを重視する
(書誌)荒木博之 日本人の行動様式 -他律と集団の論理- 講談社 1973
(要旨)ムラ的構造のなかにあって、個人がその個性を喪失し、集団の意志によってその行動が決定されてゆく他律的人間になりおおせていく
他律的精神構造が、日本人の行動様式決定の動かすべからざる要因として働いてきた
→他律指向、同調指向
(アンケート項目との関連)↓
他律指向
E26 周囲の他者の影響を受けやすい
E20 自分の今後の進路を自分一人で決められない
同調指向
E30 没個性的であろうとする
B9 行動を周囲の人々に合わせようとする
(書誌1)間宏,日本的経営-集団主義の功罪,日本経済新聞社,1973
(要旨)集団主義とは、個人と集団との関係で、集団の利害を個人のそれに優先させる集団中心(集団優先)の考え方である。あるいはそれに道徳的意味が加わって、そうするのが「望ましい」とか「善いことだ」とろる考え方である。
集団主義の下で、個人と集団との「望ましい」あり方は、個人と集団とが対立する関係ではなくて、一体の関係になることである。ここから、西欧の観 念から見て、個人の未確立の状態がでてくる。だが、集団主義の理想から言えば、個人と集団、もっと抽象的にいえば個と全体とは、対立・協調の関係にあるの ではなく、融合・一体の関係にあるのが望ましい。個人(利害)即集団(利害)であり、集団(利害)即個人(利害)である。
(書誌2)Triandis H.C., Individualism & Collectivism, Westview Press, 1995
(要旨)集団主義とは、互いに近接的にリンクされ、自分自身を、1つかそれ以上の集団(家族、会社、...)の一部であるとみなす個人からなる社会類型のことである。
1)自己の定義が、集団主義では、相互依存的であるのに対して、個人主義では、独立的である。
2)個人と集団の目標が、集団主義では、近接しているのに対して、個人主義では、そうではない。
3)集団主義社会における社会的行動の多くは、規範、義務によって導き出されるのに対し、個人主義では、個人の態度や欲求、権利や契約によって導き出される。
4)人間関係を強調することを、たとえそれが不利益な場合でも、重視するのが、集団主義社会である。個人主義社会では、人間関係の維持が生み出すのが、利益か不利益かを、理性的に分析することを重視する。
日本では、...全体の25%が、水平的集団主義(内集団の凝集性や一体感を重んじる)、50%が、垂直的集団主義(内集団のために尽く し、内集団の利益のために自己を犠牲にする、とともに、不平等性や上下方向の階層を受け入れる)である。水平的集団主義が高いのは、日本では、他者と違う 態度を取ることが、悪いことである、と考えられているからである。垂直的集団主義が高いのは、日本では、権威や上下関係についての感覚が強いからと考えら れる。
(書誌)河合隼雄 母性社会日本の病理 中央公論社 1976
(要旨)母性原理は、「包含する」機能で示され、すべてのものを絶対的な平等性をもって包み込む。それは、母子一体というのが根本原理である。→人間指向(ふれあい)、集団主義(一体感)
一方、父性原理は、「切断する」機能に特性があり、主体と客体、善と悪、上と下などに分類する。
日本社会は、母性原理を基礎に持った「永遠の少年」型社会といえる。
(アンケート項目との関連)↓
集団主義
A14 他者との一体化・融合を好む
B1 互いにくっつき合おうとする
人間指向
B3 他人との触れ合いを好む
C10 人付き合いのあり方が親密である
(書誌)林 周二 経営と文化 中央公論社 1984
(要旨)開場前の図書館口の人の列や、バスを待つ行列などを観察すると、日本人の場合には、人と人との間合いが狭く、いささか押せ押せ的に並んでいるのに、西欧人の場合には、列を作る人の間合いがかなり広い
西洋人の場合、 一人の個人の周辺の空間距離が日本人の場合より一般に広く、個人住居でも一人一部屋で住む傾向がある
企業オフィスでも、欧米について調査してみると、社員一人当たりのオフィス面積は、日本の二倍近くある。日本の役所や会社のオフィス空間 は、管理職は別として、いわゆる大部屋に多勢のヒラ社員が机を向かい合わせに並べて、がやがやと働いている。これに対し、西欧の会社を訪ねるとヒラの人た ちでも概して一人か二人が一部屋にこもって働いているし、米国でも、社員は一人ずつブースみたいな空間を構えている。
欧米の会社では、社員の一人一人が、ヒラに至るまでそのような隔離空間で、自分に与えられた仕事義務だけにひたすら従事し、それを果たし 終えれば、隣りの仲間がどんなに忙しかろうが、どんどん帰る習慣である...逆に、日本のように、ホワイトカラーの職場集団の、仕事を通じての一体感づく りが大事にされるところでは、大部屋空間法式が向いている... →密集指向
(アンケート項目との関連)↓
密集指向
A16 多人数で大部屋にいるのを好む
E32 互いに一緒にいるのを好む
(書誌)西澤潤一 独創は闘いにあり プレジデント社 1986
(要旨)(日本の科学者は、)自分の目で確認し、実験をやって納得しようという、あるいはそういう研究発表をあるがままに受け止めようとい う、最低限の自然科学技術者としての基本的姿勢に欠けて...その代わりに本(定説)に頼る姿勢が極めて濃厚である。なまじっか、権威者が書いている形に なっているから、ありがたくも本当のことのように、読み手のほうは思い込んでしまう。多くの人は、欧米の権威者の説だということで、あたかも自分の体験の ように思い込み、批判したりすると過剰に反応する。時には、本人以上に強烈なしっぺ返しをしたりする。欧米の知性に、それだけ寄り掛かっているが故かも知 れないが、まことに不健全な話である。→権威主義
欧米は、種子の段階から金を投入し、独創技術を根気よく育てようとしている。それだけ真の独創性の難しさを熟知し、敬意を払っているから である。ひるがえって日本は、官民共に危ない橋を渡ろうとせずに、欧米でうまくいっているかどうかを探り、工業化途上の大事なものを拾い上げて来て集中的 に実用化し、改良の努力を傾ける。 → 前例指向
(アンケート項目との関連)↓
権威主義
D24 権威あるとされる者の言うことを信じやすい
前例指向
D37 冒険しようとしない
C30 前例のあることだけをしようとする
(書誌)Markus H.R.,Kitayama,S., Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, pp224-253 1991
(要旨)日本をはじめとする東洋文化で優勢な、相互協調的自己観によれば、自己とは他の人や周りのことごとと結びついて高次の社会的ユニッ トの構成要素となる本質的に関係志向的実体である。..自己を相互に協調し、依存した存在とする....相互に依存・協調し他者と密接に結びついた自己を 確認する..→ 集団主義、人間指向、相互依存指向
(アンケート項目との関連)↓
集団主義
B1 互いにくっつき合おうとする
人間指向
B3 他人との触れ合いを好む
相互依存指向
A2 人付き合いで互いにもたれあうのを好む
D32 互いに依存しあおうとする
(書誌)吉井博明 情報化と現代社会[改訂版] 1997 北樹出版
(要旨)組織にとって重要度の高い情報は、不確実性が高く、多義性も高い、しかも外部環境情報であるため、最もリッチで、シンボリックな意 味伝達能力の高いメディア=対面コミュニケーションに依存せざるを得ず、これが立地を最も規定していることがわかる。情報通信メディアの発展は、皮肉なこ とに、情報通信メディアにのりにくい情報の希少性と価値を一層高め、情報中心地へのオフィス立地を促進しているのである。
複雑、かつ高度な相互依存の網の目で結ばれている日本の組織は、ウェットな対面コミュニケーションに過重に依存する文化を持っているのであり、日本社会は、全体として、集中が集中を呼ぶ体質(集中体質)を内在させているといえよう。
→密集指向
→人間指向(親密さ)、反プライバシー(視線)
もちろん、圧倒的な技術力を持ち、政府の規制や系列の制約を受けない組織が多ければ、このようなウェットな対面コミュニケーションへの依存度は低下し、集中の必要性が少なくなるのは言うまでもない。
(アンケート項目との関連)↓
密集指向
F24 中央集権を好む
A3 狭い空間に密集していようとする
人間指向
C10 人付き合いのあり方が親密である
反プライバシー
D27 互いに視線を送り合うのを好む
B7 互いに監視し合うのを好む
〔その他の、日本文化と関係の深い概念について〕
以上の文献以外で指摘されて来た、日本文化と関係の深い、ウェットさを表していると考えられる概念を、以下にいくつか列挙しました。説明は、なぜウェットと言えるかについて書かれています。
(説明)交渉などをうまく成立させるために、関係方面に予め話し合いをしておくことを指す「根回し」は、予め存在する縁故関係をたどって、 そのネットワークの中にいる各人の了解を取り付けようとする行為である。各人が、関係を生成する相互間引力の只中にいることを、話し合いの機会を持つこと で、再確認させる意味合いを持ち、根源的には、縁故関係とそのもとになる相互間引力の存在が前提となる行為である。
→縁故指向
相互間引力のある状態では、何か自分のやりたいことがある場合に、根回しが必須になる。相互間引力が働いている只中にいる状態で、何か新た に行動を起こそうとする個人は、事前に周囲に、自分はこれからこういうことをします、ということについて了解を取る、ないし根回しを行っておかないと、後 で、本人の行動が周囲の他者をあらぬ方向へ(相互間引力の働きで)振り回した(あるいは、逆に、周囲が本人を、自由に動けないように、相互間引力によって 拘束しようとした)ということで、互いに不本意な思いをする(互いの行動を非難し合うなど)ことにつながる。
→規制主義
〔接待〕
(説明)接待は、元々あまり近くなかった存在の者同士のうちの一方が他方に対して、より心理的に近づこうとして(相手に近づいてもらおうとして)、食事などの供与をすることを指し、その点で、相互間引力がより強く働く状態に持ち込もうとする態度の現れと言える。
→縁故指向
(説明)官公庁の入札などの際に見られる談合は、互いに相手の動きを、相手が自由な行動(各自が自由に安い入札価格を提示し合って競争する など)を取らないように牽制し合って、取る動き(特定の誰かが、高めの入札価格を提示すること)を事前の話し合い(相互拘束)で決めてしまう点で、相互間 引力の産物である。
→規制主義
〔公私混同〕
(説明)公共物と自分のものとを混同することが、公私の区別が「あいまい」となることに結びつく。
→あいまい指向
こうした、従来、日本的とされる対人関係の上での特徴は、決して、日本だけに特殊なものではなく、より一般的には、農耕、とくに高温多湿な 東アジアに広く分布する稲作社会(集約的農業型社会)での対人関係上の特徴へと拡張して捉えることができそうに思われる。この点の根拠については、筆者による環境のドライ・ウェットさとの照合についての記述を参考にしていただきたい。
現状では、研究者の関心が、日本対欧米という視点にしばられて、日本以外の東アジアの社会のあり方に対して向いていないため、日本の対人関係上の特徴を、(本当は東アジア稲作社会に共通であるのに)日本に特殊的と思い込みやすいのではあるまいか?
〔参考文献〕
青木保 「日本文化論」の変容 -戦後日本の文化とアイデンティティー- 中央公論社 1990
芳賀綏 日本人の表現心理 中央公論社 1979
南博 日本人論-明治から今日まで 岩波書店 1994
吉井博明 情報化と現代社会 北樹出版 1996
1-2.「日本的=ウェット」のアンケート調査(2000.10)による確認
上記文献調査結果である、「日本的=ウェット」を確認するため、いくつかアンケート調査を行った。
(1)日本とアメリカと、どちらがよりドライ/ウェットかと、1999.5~7に行った、「ドライ・ウェットな性格・態度は何か」を調べるアンケート内で尋ねたところ、「アメリカがよりドライ(日本がよりウェット)である」との回答があった割合が、その逆よりも、やや多かった(ただし、有意水準0.01には届いていない)。
|
番号 |
項目内容 |
-回答= |
どちらで |
-回答= |
項目内容 |
-Z得点- |
有意 |
|
C32 |
アメリカ的である |
44.796 |
21.719 |
33.484 |
考え方が日本的である |
1.901 |
0.05 |
(2)日本的、東アジア的(=韓国・台湾、フィリピン...的)、および欧米的な性格・態度が、それぞれどの程度ドライ/ウェットと考えられるかについて検証するアンケート調査を2000.10に行った。
アンケートは、より日本的、東アジア的、欧米的な態度が、とてもドライ~とてもウェットの5段階評価でどのレベルに当てはまるかを、回答してもらう形で行った。
その結果、「欧米的=ドライ」、「東アジア的(=韓国、台湾、フィリピン....的)=ウェット」、「日本的=ウェット」という傾向が確認された。 (注)
2008年1月 初出
2006年12月頃、気体、液体の分子運動のドライ、ウェットさの測定を、気体分子運動でドライと感じる度合いがウェットと感じる度合いを上回るか、液体分子運動でウェットと感じる度合いがドライと感じる度合いを上回るかを確認する作業を行った。
すなわち、インターネット利用者(研究参加者)に気体,液体の分子運動シミュレーションムービーを見せて,各分子の動きを人の動きと見立てた場合それぞれどの程度ドライ,ウェットと感じるか調べることにした。
・方法
[データ収集方法] インターネットのwebサイトで回答を収集した。回答のカウントに当たっては,同じ研究参加者が複数回回答する可能性に対応するた め,回答時に同一のIPアドレスの持ち主は同一の回答者であると見なし,同一のIPアドレスの複数回答は最新の1個の回答のみを有効と見なすととも に,cookieを利用して複数回の回答を受付けないように設定した。
[研究参加者] 回答を得た研究参加者の総数は206名(男性102名,女性104名)であった。性別情報は,回答時に性別選択欄をwebページにラジオボタンで設け,選択入力してもらうことで得た。
[調査時期] 調査時期は,2006年12月4日から9日の6日間であった。
[刺激映像] 刺激は,Ar(アルゴン)の分子運動パターンをシミュレートするJavaプログラムを,池内(2002)のwebサイトより入手し,液体と気体それぞれの分子運動を最も明確に示すように,絶対温度20度(液体)と300度(気体)のそれぞれの分子運動を表すように調整した。プログラムが表示した気体,液体各分子運動のムービーを,パソコン上でキャプチャし,各々30秒間のwindows media video形式のムービーに加工して,webサイト上で研究参加者のパソコンから再生可能とした。
[質問項目] 上記各ムービーについて「これは,人々の動きを早送りで再生したものです。一つ一つの粒々が一人一人の人間を表しています。このムービーに おける人々の性格がどの程度ドライ,ウェットに感じられるか5段階評価して下さい。」として,ドライ,ウェットそれぞれ別々に回答させた。段階は,「感じ ない(0) -少し感じる(1) -やや感じる(2) -かなり感じる(3) -とても感じる(4)」とした。
[手続き] 各ムービーは,一度に1個ずつ,順番をランダムにして呈示し,ムービー毎に回答させるようにした。また,研究参加者のコンピュータ環境に対応 しつつ,刺激提示の条件を揃えるために,「再生回数は可能な限り2回まででお願いします」の旨,断り書きを付けて,読んでもらった。なお,実験操作のデブ リーフィングとして,回答が完了した時点で,「実はこれは,気体,液体分子運動のシミュレーションムービーでした。」という断り書きを画面上に呈示した。
・結果
気体,液体分子運動パターンが,人の性格としてそれぞれドライおよびウェットと感じられた度合いの評定値の平均値と標準偏差はTable 1に示した通りである。
見せたムービーの種類別にドライ,ウェットに感じた度合いの違いを見るため,対応のあるt検定を行った。結果はTable 2の通りである。
液体の分子運動を見たとき,ドライ,ウェットと感じる度合いについては,ウェットと感じる度合いの数値が,ドライと感じる度合いよりも,有意に高かった(t(205)=8.74,p<.01)。
気体の分子運動を見たとき,ドライ,ウェットと感じる度合いについては,ドライと感じる度合いの数値が,ウェットと感じる度合いよりも,有意に高かった(t(205)=3.21,p<.01)。
気体と液体とではどちらをよりドライと感じるかについては,気体分子運動パターンをドライに感じる度合いが,液体分子運動パターンをドライに感じる度合いよりも有意に高かった(t(205)=6.32,p<.01)。
気体と液体とではどちらをよりウェットと感じるかについては,液体分子運動パターンをウェットに感じる度合いが,気体分子運動パターンをウェットに感じる度合いよりも有意に高かった(t(205)=8.25,p<.01)。
・図表
Figure.1 気体,液体分子運動パターン
分子運動シミュレーションムービー(研究参加者に見せたもの)
気体分子運動
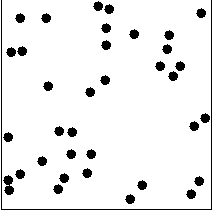
液体分子運動
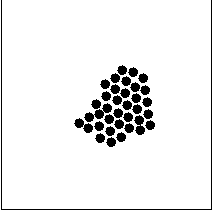
Table.1
|
刺激種類 |
ドライ |
ウェット |
|
液体分子運動 |
0.85 |
2.09 |
|
気体分子運動 |
1.60 |
1.15 |
(かっこ内は標準偏差)
Table.2
|
比較対象 |
t検定結果 |
有意水準 |
|
液体ウェット液体ドライ |
t(205)=8.74 |
p <.01 |
|
気体ドライ-気体ウェット |
t(205)=3.21 |
p <.01 |
|
気体ドライ-液体ドライ |
t(205)=6.32 |
p <.01 |
|
液体ウェット気体ウェット |
t(205)=8.25 |
p <.01 |
以上の結果により,気体分子運動のシミュレーションを人に見立てて観察させるとドライな性格と認知され,一方,液体分子運動はウェットな性格と認知される ことが分かった。気体分子運動パターンと同様に振る舞う人のパーソナリティはドライに,液体分子運動パターンと同様に振る舞う人ではウェットに感じられる と考えられる。
2008.04 初出
要約
人間のパーソナリティ認知の男性的,女性的と,物質の気体,液体の人間に与える感覚のドライ,ウェットさの間の関連を明らかにするため,webでの調査を 行った。気体・液体分子運動パターンをコンピュータシミュレートした2つのムービーを研究参加者201名に対して見せて,各ムービーで,粒子の動きが個人 の対人行動としてどの程度男性的,女性的に感じられるかを評価してもらった。その結果,気体分子運動パターンは人々の動きとして男性的,液体分子運動パ ターンは女性的と感じられることが分かった。
課題
実際に研究参加者に気体,液体の分子運動シミュレーションムービーを見せて,各分子の動きを人の動きと見立てた場合それぞれどの程度男性的,女性的と感じるか調べることにした。
方法
[データ収集方法] インターネットのwebサイトで回答を収集した。回答のカウントに当たっては,同じ研究参加者が複数回回答する可能性に対応するた め,回答時に同一のIPアドレスの持ち主は同一の回答者であると見なし,同一のIPアドレスの複数回答は最新の1個の回答のみを有効と見なすととも に,cookieを利用して複数回の回答を受付けないように設定した。
[研究対象者] 回答を得た研究参加者の総数は201名(男性105名,女性96名)であった。性別情報は,回答時に性別選択欄をwebページにラジオボタンで設け,選択入力してもらうことで得た。
[調査時期] 調査時期は,2007年8月21日から8月31日の11日間であった。
[刺激映像] 刺激は,Ar(アルゴン)の分子運動パターンをシミュレートするJavaプログラムを,池内(2002)のwebサイトより入手し,液体と 気体それぞれの分子運動を最も明確に示すように,絶対温度20度(液体)と300度(気体)のそれぞれの分子運動を表すように調整した。プログラムが表示 した気体,液体各分子運動のムービーを,パソコン上でキャプチャし,各々30秒間のwindows media video形式のムービーに加工して,webサイト上で研究参加者のパソコンから再生可能とした。各ムービーの静止画は,Figure 1の通りである。
[質問項目] 上記各ムービーについて「これは,人々の動きを早送りで再生したものです。一つ一つの粒々が一人一人の人間を表しています。このムービーに おける人々の性格がどの程度男性的,女性的に感じられるか5段階評価して下さい。」として,男性的,女性的それぞれ別々に回答させた。段階は,「感じない (0)」から「とても感じる(4)」の5段階とした。
[手続き] 各ムービーは,一度に1個ずつ,順番をランダムにして呈示し,ムービー毎に回答させるようにした。回答はムービーが実際に動いているのを見な がらでないとしにくいため,各ムービーは回答中エンドレスで流れるようにした。なお,実験操作のデブリーフィングとして,回答が完了した時点で,「実はこ れは,気体,液体分子運動のシミュレーションムービーでした。」という断り書きを画面上に呈示した。
結果
気体,液体分子運動パターンが,人の性格としてそれぞれ男性的および女性的と感じられた度合いの評定値の平均値と標準偏差はTable 1に示した通りである。
見せたムービーの種類別に男性的,女性的に感じた度合いの違いを見るため,対応ありの平均値の差のt検定(両側)を行った(n=201)。結果はTable 2の通りである。
液体の分子運動を見たとき,男性的,女性的と感じる度合いについては,女性的と感じる度合いの数値が,男性的と感じる度合いよりも,有意に高かった(t(200)=5.42,p<.01)。
気体の分子運動を見たとき,男性的,女性的と感じる度合いについては,男性的と感じる度合いの数値が,女性的と感じる度合いよりも,有意に高かった(t(200)=6.84,p<.01)。
気体と液体とではどちらをより男性的と感じるかについては,気体分子運動パターンを男性的に感じる度合いが,液体分子運動パターンを男性的に感じる度合いよりも有意に高かった(t(200)=7.47,p<.01)。
気体と液体とではどちらをより女性的と感じるかについては,液体分子運動パターンを女性的に感じる度合いが,気体分子運動パターンを女性的に感じる度合いよりも有意に高かった(t(200)=6.29,p<.01)。
考察
以上の結果により,気体分子運動のシミュレーションを人に見立てて観察させると男性的な性格と認知され,一方,液体分子運動は女性的な性格と認知されるこ とがわかった。気体分子運動パターンと同様に振る舞う人のパーソナリティは男性的に,液体分子運動パターンと同様に振る舞う人では女性的に感じられると考 えられる。
図表
Figure.1 気体,液体分子運動パターン
分子運動シミュレーションムービー(研究参加者に見せたもの)
気体分子運動
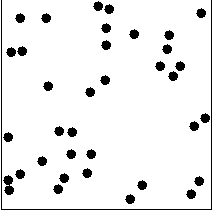
液体分子運動
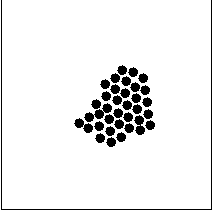
Table.1 気体,液体分子運動ムービーへのアメリカ的・日本的評価値の平均値と標準偏差(かっこ内)
|
刺激種類 |
男性的 |
女性的 |
|
液体分子運動 |
0.67 |
1.35 |
|
気体分子運動 |
1.49 |
0.65 |
n=201
Table.2 条件間の平均値の差の比較結果(対応あり)
|
比較対象 |
t検定 |
|
液体女性的-液体男性的 |
t(200)=5.42** |
|
気体男性的-気体女性的 |
t(200)=6.84** |
|
気体男性的-液体男性的 |
t(200)=7.47** |
|
液体女性的-気体女性的 |
t(200)=6.29** |
** p < .01
2012.07初出
父性的、母性的パーソナリティと、気体、液体分子運動パターンとの関係について、詳しく説明しています。父性的 パーソナリティと気体分子運動、母性的パーソナリティと液体分子運動が相関します。
要約
人間のパーソナリティ認知の父性的,母性的と,物質の気体,液体の人間に与える感覚のドライ,ウエットさの間の関連を明らかにするため,webで の調査を行った。気体・液体分子運動パターンをコンピュータシミュレートした2つのムービーを研究参加者201名に対して見せて,各ムービーで,粒子の動きが個人の対人行動としてどの程度 父性的,母性的に感じられるかを評価してもらった。その結果,気体分子運動パターンは人々の動きとして父性的,液体分子運動パターンは母性的と感 じられることが分かった。
課題
実際に研究参加者に気体,液体の分子運動シミュレーションムービーを見せて,各分子の動きを人の動きと見立てた場合それぞれどの程 度父性的,母性的と感じるか調べることにした。
方法
[データ収集方法]インターネットのwebサイトで回答を収集した。回 答のカウントに当たっては,同じ研究参加者が複数回回答する可能性に対応するため,回答時に同一のIPアドレスの持ち 主は同一の回答者であると見なし,同一のIPアドレスの複数回答は最新の1個の回答のみを 有効と見なすとともに,cookieを利用して複数回の回答を受付けないように設定した。
[研究対象者]回答を得た研究参加者の総数は201名(男性105名, 女性96名)であった。性別情報は,回答時に性別選択欄をwebページにラジオボタンで設 け,選択入力してもらうことで得た。
[調査時期]調査時期は,2007年8月21日から8月31日の11日間であった。
[刺激映像]刺激は,Ar(アルゴン)の分子運動パターンをシミュレートするJavaプログラムを,池内満(2002)のwebサイトより入手し,液体と気体それぞれの分子運動を最も明確に示すように,絶対温度20度(液 体)と300度(気体)のそれぞれ の分子運動を表すように調整した。プログラムが表示した気体,液体各分子運動のムービーを,パソコン上でキャプチャし,各々30秒間のwindowsmediavideo形式のムービーに加工して,webサイト上で研究 参加者のパソコンから再生可能とした。各ムービーの静止画は,Figure1の通りである。
[質問項目]上記各ムービーについて「これは,人々の動きを早送りで再生したものです。一つ一つの 粒々が一人一人の人間を表しています。このムービーにおける人々の性格がどの程度父性的,母性的に感じられるか5段階 評価して下さい。」として,父性的,母性的それぞれ別々に回答させた。段階は,「感じない(0)」から「とても感じる(4)」 の5段階とした。
[手続き]各ムービーは,一度に1個ずつ,順番をランダムにして呈示 し,ムービー毎に回答させるようにした。回答はムービーが実際に動いているのを見ながらでないとしにくいため,各ムービーは回答中エンドレスで流 れるようにした。なお,実験操作のデブリーフィングとして,回答が完了した時点で,「実はこれは,気体,液体分子運動のシミュレーションムービー でした。」という断り書きを画面上に呈示した。
結果
気体,液体分子運動パターンが,人の性格としてそれぞれ父性的および母性的と感じられた度合いの評定値の平均値と標準偏差はTable1に 示した通りである。
見せたムービーの種類別に父性的,母性的に感じた度合いの違いを見るため,対応ありの平均値の差のt検 定(両側)を行った(n=201)。結果はTable2の通りである。
液体の分子運動を見たとき,父性的,母性的と感じる度合いについては,母性的と感じる度合いの数値が,父性的と感じる度合いより も,有意に高かった(t(200)=5.67,p<.01)。
気体の分子運動を見たとき,父性的,母性的と感じる度合いについては,父性的と感じる度合いの数値が,母性的と感じる度合いより も,有意に高かった(t(200)=4.96,p<.01)。
気体と液体とではどちらをより父性的と感じるかについては,気体分子運動パターンを父性的に感じる度合いが,液体分子運動パターン を父性的に感じる度合いよりも有意に高かった(t(200)=4.28,p<.01)。
気体と液体とではどちらをより母性的と感じるかについては,液体分子運動パターンを母性的に感じる度合いが,気体分子運動パターン を母性的に感じる度合いよりも有意に高かった(t(200)=6.82,p<.01)。
考察
以上の結果により,気体分子運動のシミュレーションを人に見立てて観察させると父性的な性格と認知され,一方,液体分子運動は母性 的な性格と認知されることがわかった。気体分子運動パターンと同様に振る舞う人のパーソナリティは父性的に,液体分子運動パターンと同様に振る舞 う人では母性的に感じられると考えられる。
図表
Figure.1気体,液体分子運動パターン
分子運動シミュレーションムービー(研究参加者に見せたもの)
気体分子運動
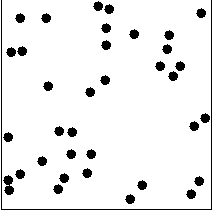
液体分子運動
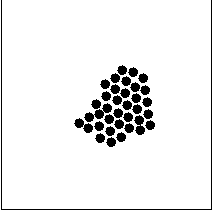
|
刺激種類 |
父性的 |
母性的 |
|
液体分子運動 |
0.37 |
0.90 |
|
気体分子運動 |
0.76 |
0.31 |
n=201
Table.2条件間の平均値の差の比較結果(対応あり)
|
比較対象 |
t検定 |
|
液体母性的-液体父性的 |
t(200)=5.67** |
|
気体父性的-気体母性的 |
t(200)=4.96** |
|
気体父性的-液体父性的 |
t(200)=4.28** |
|
液体母性的-気体母性的 |
t(200)=6.82** |
**p<.01
2008.04 初出
要約
人間のパーソナリティ認知のアメリカ的,日本的と,物質の気体,液体の人間に与える感覚のドライ,ウェットさの間の関連を明らかにするため,webでの調査を行った。気体・液体分子群の運動をコンピュータシミュレートした2つのムービーを研究参加者201名に対して見せて,各ムービーで,粒子の動きが個人の対人行動としてどの程度アメリカ的,日本的に感じられるかを評価してもらった。その結果,気体分子運動パターンは人々の動きとしてアメリカ的,液体分子運動パターンは日本的と感じられることが分かった。
目的
実際に日本人の研究参加者に気体,液体の分子運動シミュレーションムービーを見せて,各分子の動きを人の動きと見立てた場合それぞれどの程度欧米的,日本的と感じるか調べることにした。
その際,「欧米的」という言葉は,「欧米」がカバーする地球上の地域が広範囲,多種多様にわたるため,人々が捉えるパーソナリティ上のイメージが分散し,統合して捉えにくい可能性がある。そこで,今回研究参加者を日本人としたこともあり,日本人にとって,欧米地域の中で,太平洋戦争後の日本占領以来,最も身近で親しみのある,パーソナリティの具体的イメージが沸きやすいと考えられる北米のアメリカ合衆国を代表例として採用し,「アメリカ的」「日本的」のそれぞれを調べることにした。
方法
[データ収集方法] インターネットのwebサイトで回答を収集した。回答のカウントに当たっては,同じ研究参加者が複数回回答する可能性に対応するため,回答時に同一のIPアドレスの持ち主は同一の回答者であると見なし,同一のIPアドレスの複数回答は最新の1個の回答のみを有効と見なすとともに,cookieを利用して複数回の回答を受付けないように設定した。
[研究対象者] 回答を得た研究参加者の総数は201名(男性105名,女性96名)であった。性別情報は,回答時に性別選択欄をwebページにラジオボタンで設け,選択入力してもらうことで得た。
[調査時期] 調査時期は,2007年8月21日から8月31日の11日間であった。
[刺激映像] 刺激は,Ar(アルゴン)の分子運動パターンをシミュレートするJavaプログラムを,池内(2002)のwebサイトより入手し,液体と気体それぞれの分子運動を最も明確に示すように,絶対温度20度(液体)と300度(気体)のそれぞれの分子運動を表すように調整した。プログラムが表示した気体,液体各分子運動のムービーを,パソコン上でキャプチャし,各々30秒間のwindows media video形式のムービーに加工して,webサイト上で研究参加者のパソコンから再生可能とした。各ムービーの静止画は,Figure 1の通りである。
[質問項目] 上記各ムービーについて「これは,人々の動きを早送りで再生したものです。一つ一つの粒々が一人一人の人間を表しています。このムービーにおける人々の性格がどの程度アメリカ的,日本的に感じられるか5段階評価して下さい。」として,アメリカ的,日本的それぞれ別々に回答させた。段階は,「感じない(0) 」から「とても感じる(4)」の5段階とした。
[手続き] 各ムービーは,一度に1個ずつ,順番をランダムにして呈示し,ムービー毎に回答させるようにした。回答はムービーが実際に動いているのを見ながらでないと行いにくいため,各ムービーは回答中エンドレスで流れるようにした。なお,実験操作のデブリーフィングとして,回答が完了した時点で,「実はこれは,気体,液体分子運動のシミュレーションムービーでした。」という断り書きを画面上に呈示した。
結果
気体,液体分子運動パターンが,人の性格としてそれぞれアメリカ的および日本的と感じられた度合いの評定値の平均値と標準偏差はTable 1に示した通りである。
見せたムービーの種類別にアメリカ的,日本的に感じた度合いの違いを見るため,対応のあるt検定を行った。結果はTable 2の通りである。
液体の分子運動を見たとき,アメリカ的,日本的と感じる度合いについては,日本的と感じる度合いの数値が,アメリカ的と感じる度合いよりも,有意に高かった(t(200)=10.20,p<.01)。
気体の分子運動を見たとき,アメリカ的,日本的と感じる度合いについては,アメリカ的と感じる度合いの数値が,日本的と感じる度合いよりも,有意に高かった(t(200)=3.54,p<.01)。
気体と液体とではどちらをよりアメリカ的と感じるかについては,気体分子運動パターンをアメリカ的に感じる度合いが,液体分子運動パターンをアメリカ的に感じる度合いよりも有意に高かった(t(200)=7.81,p<.01)。
気体と液体とではどちらをより日本的と感じるかについては,液体分子運動パターンを日本的に感じる度合いが,気体分子運動パターンを日本的に感じる度合いよりも有意に高かった(t(200)=7.15,p<.01)。
考察
以上の結果により,気体分子運動のシミュレーションを人に見立てて観察させるとアメリカ的な性格と認知され,一方,液体分子運動は日本的な性格と認知されることがわかった。気体分子運動パターンと同様に振る舞う人のパーソナリティはアメリカ的に,液体分子運動パターンと同様に振る舞う人では日本的に感じられると考えられる。
このことから,気体と液体それぞれの分子運動のパターンと,パーソナリティの認知におけるアメリカ的,日本的という印象との間に,なんらかのつながりが存在することが推測される。しかし,なぜこうしたつながりが生じるかの理由は,現状ではよく分からず,さらなる研究が必要である。
また,今回の研究結果では,アメリカ的,日本的なパーソナリティについて日本人の研究参加者が持つ印象を単に尋ねたに過ぎず,その印象が,アメリカ人,日本人のパーソナリティの実際のあり方にそのまま即していると考えるのは早計と考えられる。実際の対人関係においてアメリカ人のパーソナリティが気体的で日本人のそれが液体的であることを示す研究が別途必要である。
また,今回の結果は,あくまで日本人サイドの見方であり,視点に偏りが見られる。より偏りのない客観的な視点を得るには,日本人の研究参加者だけでなく,アメリカ人の研究参加者を別途募って,アメリカ人から見た印象がどうなっているかを別途確認する必要がある。
また,欧米的,日本的パーソナリティの比較という当初の研究目的からは,今後は,今回の研究では対象から除外された,アメリカ以外の西欧,北欧等のヨーロッパ各地域と日本との比較等も必要となってくると考えられる。
図表
Figure.1 気体,液体分子運動パターン
分子運動シミュレーションムービー(研究参加者に見せたもの)
気体分子運動
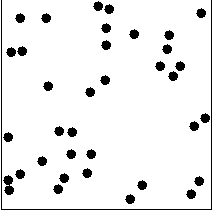
液体分子運動
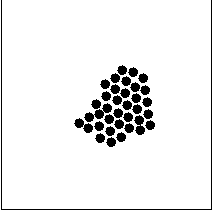
Table.1 気体,液体分子運動ムービーへのアメリカ的・日本的評価値の平均値と標準偏差(かっこ内)
|
刺激種類 |
アメリカ的 |
日本的 |
|
液体分子運動 |
0.47 |
1.71 |
|
気体分子運動 |
1.35 |
0.90 |
n=201
Table.2 条件間の平均値の差の比較結果(対応あり)
|
比較対象 |
t検定 |
|
液体日本的-液体アメリカ的 |
t(200)=10.20** |
|
気体アメリカ的-気体日本的 |
t(200)=3.54** |
|
気体アメリカ的-液体アメリカ的 |
t(200)=7.81** |
|
液体日本的-気体日本的 |
t(200)=7.15** |
** p < .01
|
女社会 |
男社会 |
|
| タイプ |
リキッドタイプ(液体的) |
ガスタイプ(気体的) |
| 感覚 |
ウェット、温かい |
ドライ、冷たい |
| 支配者 |
姑、母、お局 |
父 |
| 優勢な地域 |
日本的、東アジア的(中国、韓国・・・) |
アメリカ的、西欧的 |
|
1 |
保身preservation |
|
|
101 |
保身、安全の重視 |
危険への対峙 |
|
互いに自分のことが一番大切である。軍事的に守られるのを好む。 |
自分自身より大切な存在が他にいる。それを守るのを自己の使命とする。 |
|
|
102 |
前例、しきたり、暗記の重視、保守性 |
探検、独創性の重視、革新性 |
|
その通りにやれば大丈夫、無難と分かっている前例、しきたりが確立されたことしかしようとしない。物の見方が保守的である。 |
うまく行くかどうか分からない、前例のない事柄に挑戦して、失敗を重ねながら、新たな前例に当たる知見を作り上げる。物の見方が革新的である。 |
|
|
103 |
減点主義 |
加点主義vs直接的な欠点修正要求 |
|
相手のマイナス点、あら探しを粘着的に延々とするのを好む。相手を褒めない。いつまでも陰口、悪口を言う。建設的でない。 |
相手の長所を積極的に褒める。建設的である。相手の欠点を、単刀直入に直接的に批判、攻撃して、修正されたら、あっさり余所へ行く。 |
|
|
104 |
決定、責任の回避 |
決定、責任の不可避 |
|
決定を先送りする。 |
決定を先送りせず、リアルタイムで決定する。 |
|
|
2 |
一体性oneness |
|
|
201 |
相互一体性の重視 |
相互独立性の重視 |
|
互いに一つになる、融合するのを好む。 |
互いにバラバラに独立するのを好む。 |
|
|
202 |
依存 |
自立 |
|
自分一人だけで自立するのが不安で、誰か周囲に支えてもらいたいと考える。周囲に助け、庇護を求める。 |
自分一人で自立するのを理想とし、周囲に助けを求めない。 |
|
|
203 |
包含の重視、「袋」指向、枠内、制限指向 |
解放の重視、開放性、枠からの飛び出し、打破指向 |
|
相手を包み込む、相手に包み込まれる感覚を好む。「袋」の中にいるのを好む。決められた枠内に止まる、枠を守る、制限するのを好む。 |
包まれていた、閉じ込められていたところから解放されるのを好む。オープンなのを好む。決められた枠からはみ出す、飛び出る、枠を破るのを好む。 |
|
|
204 |
全人的支配、従属 |
支配の部分性、自由の残存 |
|
親分子分関係のように、相手を全人格的に包み込んで支配したり、全人格的に従属するのを好む。 |
相手を支配するが、全人格を支配するのではなく、相手のコアの部分には、自由を残す。 |
|
|
205 |
相手の人格制御 |
相手の道具、手段的制御 |
|
教育などで、相手教師の人格、人柄そのものを慕って付いて行こう、相手子供の人格そのものをコントロールしよう、しつけようとする。 |
教育などで、相手の人格そのものには手を付けず、相手を専ら効果的な学習のための道具、手段として効果的に利用し、あるいは具体的な指示、教示を与える対象として冷静に目視しようとする。 |
|
|
206 |
所属の重視(所属主義) |
本人個人、フリー、自由の重視 |
|
人を見る時に、その人がどの集団、団体に属しているかを重視する。 |
人を見るときに、本人の所属ではなく、本人個人そのものを直視の対象とする。どこにも従属せず、自主独立の自由であることを重視する。 |
|
|
207 |
つながり、コミュニケーション、縁故、コネの重視 |
初対面、別れ、切断前提の付き合い、契約の重視 |
|
人とのつながり、コミュニケーションを重視する。人を判断する時に、その人が自分とどういうつながりがあるか、どういうコネを持っているかを重視する。採用とかで自分とつながりのない他者をシャットアウトする。一見さんお断り。 |
人を判断する時に、その人自身の能力、利益を生み出す力を重視する。能力のあると思った人は、初対面でコネがなくても採用する。用件が済んだら、さっさと別れて、関係を切る。関係が切れることを前提とした契約を重視する。 |
|
|
208 |
妬み、足の引っ張り合い |
自他の区別・割り切り、ライバルへの攻撃 |
|
自分と関わりのある、かつて自分と同等以下で、その後自分より上等になった、なろうとする他者のことを妬んで、互いに足を引っ張る。自分は自分、他人は他人と割り切ることができない。 |
自分は自分、他人は他人と区別し、割り切る。 |
|
|
209 |
近接、粘着、くっつき |
離反、距離感、はがれ |
|
人間関係が、相手に近づきくっつくのを好む結果、粘着的になり、愛憎にまみれた、ベタベタ、ドロドロしたものになる。 |
人間関係が、相手とあまりベタベタくっつかずにはがれる、距離を保った、あっさりしたそっけないものとなる。 |
|
|
3 |
集団group |
|
|
301 |
集団、団体行動の重視(集団主義) |
個人行動の重視(個人主義) |
|
集団で行動する、群れるのを好む。相手に連れ立って一緒に付いていく、つるむのを好む。 |
個人単位で行動するのを好む。周囲と別行動を取っても咎められない。 |
|
|
302 |
同調、協調、調和、和合の重視、個性の一定枠内での許容 |
独自判断、違和感、反対の許容、個性の重視 |
|
意見を周囲や相手に合わせるのを好む。物事を相手と一緒に共同でするのを好む。個性の重視とは、一定枠内に止まりながら、その枠内で最大限目立とうとすることである。 |
意見を周囲に合わせずに独自の判断をしたり、周囲と反対の意見を述べて平気である。個性として許容する。 |
|
|
303 |
流行、トレンドへの追従 |
自己流、独自性の貫徹 |
|
皆が追随する最新、最先端の流行を身につけようとする。その時々のトレンドに乗っていこうとする。 |
周囲の動向にお構いなく、自分流を貫くのを好む。 |
|
|
304 |
仲間外れ、浮きの存在といじめ |
バラバラ、単独行動 |
|
集団の調和を乱す浮いた存在の人を、よってたかって仲間外れにして、いじめる。 |
各自が、勝手にバラバラな方向に単独行動を取り、反対する者同士攻撃を加え合う。仲間は一時的な存在であり、別れることが前提である。全員が浮いている。 |
|
|
305 |
非競争、護送船団主義、談合 |
自由競争、能力主義、成果主義 |
|
自由競争を好まず、互いに一体となって、一緒に進もうとする。競争のない年功序列、先輩後輩制、談合を好む。 |
互いに自由競争で、自分の持つ能力を最大限に発揮して、自分が成果を上げて生き残り、他者を蹴落とそうとする。 |
|
|
4 |
人間human、有機organic |
|
|
401 |
人間指向、有機指向 |
機械、無機指向 |
|
人間、対人関係そのものに対して関心、注意が行きやすい。 |
冷たい機械や岩石(宇宙)とかに興味を持つ。 |
|
|
402 |
相互監視、密告、牽制 |
プライバシーの重視 |
|
互いに周囲の他者が何をやっているかに関心が行き、盛んに首を突っ込んで、監視、牽制しようとする。 |
互いに、他者に踏み込まれない独自領域を確保することに熱心である。 |
|
|
403 |
噂、陰口指向 |
自己主張 |
|
他人の陰口やうわさ話を流すのを好む。 |
他人ではなく自分自身の主義主張を、周囲に向かって宣伝するのを好む。 |
|
|
404 |
恥の重視 |
恥知らず |
|
周囲の他人の目を盛んに気にして、恥ずかしがる。自分が他人にどう思われているかを気にする。 |
他人の目に無関心である。人目を気にせずに、自分のやりたいことに邁進する。 |
|
|
405 |
媚び、化粧、服飾指向 |
自己評価の重視 |
|
周囲の他人によく思われようとする。周囲に盛んに媚を売る。演技をする。自分が周囲によく見えるように、自分を飾る化粧や服飾に注意が行く。 |
周囲の他者ではなく、自分自身で自己を客観的に見つめなおし、自己評価を良くして行こうとする。 |
|
|
406 |
関係保持的配慮、気づき |
制御的配慮、気づき |
|
互いに、相手が、何か自分に注目してほしいというサイン(メール、ブログ書き込み等)を自分に対して送っているかどうかに常に神経を配り、リアルタイムで相手に注目していますよとすぐ返事を返すことで、相手の被注目欲求を満足させ、良好な対人関係を保持しようとする。 |
対象となる人(部下とか)や物(乗り物とか)が、自分にとって道具、手段として自分に最高の利益をもたらすように適切に動作、行動しているかどうかに常に神経を配り、リアルタイムでコントロール、軌道修正する。 |
|
|
5 |
条件condition |
|
|
501 |
好条件、温室指向 |
悪条件(寒暑)の受容 |
|
条件のよい温室の中に止まるのを好む。ぬるま湯を好む。 |
条件の悪い所に放り出されるのを受容して、それに何とか適応していく。 |
|
|
502 |
内部指向、「奥」指向、内外の区別(「膜内」指向) |
代表指向、外部露出 |
|
より環境の安定した内側に止まる、奥にいるのを好む(奥様)。「袋」の中にいるのを好む。 |
代表として、対外的に露出するのを許容する。 |
|
|
503 |
内輪指向、閉鎖、排他性 |
開放性、オープンさ |
|
気心の知れた親しい仲間内、身内だけで結束し、外部の人間に対して冷たい態度を取る。 |
誰にでも平等に開かれた空間の存在を大切にする。 |
|
|
504 |
集団ベースのセキュリティ重視 |
個人ベースのセキュリティ重視 |
|
集団の中に変な人が入ってこないように、集団への加入条件を厳しくする(入試を難しくして、なかなか入れなくする)。集団内部ではセキュリティがなあなあになって緩くなりがち。 |
新たに近づいてくる人物が危険かも知れないので、その場合排除、自身を護衛できるように、銃の所持とか、個人単位でのセキュリティを重視する。 |
|
|
6 |
感情emotion |
|
|
601 |
感情、情緒的、主観的対応 |
論理的、客観的対応 |
|
相手に対して、冷静に割り切ることができず、情緒、感情を露にして対応する。思わず涙をこぼす。 |
相手に対して、冷静、客観的に割り切って対処する。 |
|
|
602 |
生肌・粘膜的対応 |
「よろい」着用による対応 |
|
感覚的な肌合い、肌触りや粘膜(口、鼻等)への働きかけを重視する。自分自身の肌や粘膜の状態に敏感である。相手が自分と肌に合うかどうかを気にする。 |
直接肌の感覚に訴えるのを回避して、肌を覆う固いよろいに身を包もうとする。相手を判断するのに、肌への感覚を遮断する。 |
|
|
603 |
第六感による総合的判定 |
要素還元による判定 |
|
物事を判定するのに、個別の要素に分けるのではなく、第六感を駆使して、一挙に総合的に判定する。 |
物事を判定するのに、個別の要素へと還元して、部分的判定を積み上ることで、全体の判定につなげるのを好む。 |
|
|
7 |
植物plant |
|
|
701 |
低重心、定住、定着指向、植物的 |
高重心、浮上、移動、動物的 |
|
大地、一カ所にどっしりと根や腰を下ろした状態を好む。重心が低い。腰が重い。定住、定着を好む。農耕植物栽培に従事する。農耕民的である。 |
重心が高く、ふわふわ浮いてあちこち移動する、根無し草のようなフリーな状態を好む。動物、家畜の飼育に従事する。遊牧民、牧畜民的である。 |
1964年 神奈川県生まれ
1989年 東京大学文学部社会学科卒
卒業後、電機メーカーで、パソコン等の使いやすさの向上に関する業務に従事する一方、学生時代から興味のあった、男女の心理的、社会的性差と湿度感覚、日本社会との関連の分析等をプライベートで継続して行う。
「女らしさ、男らしさ -性差心理学の世界-」
「父性と母性-性格の比較-」
「ドライ、ウェットな性格、態度、社会について」
「気体タイプ、液体タイプ」
「日本社会の分析」
※ご注意
以下のシミュレーション動画の原作者および著作権保有者は、池内満さんです。
池内さんのwebサイト http://mike1336.web.fc2.com/
気体分子運動パターン 動画
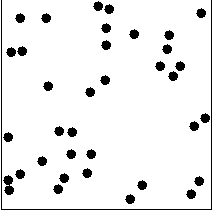
YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Lf1kTsT0ebc
液体分子運動パターン 動画
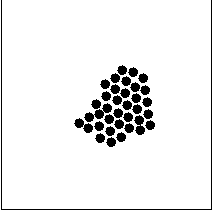
YouTube http://www.youtube.com/watch?v=31uADzoGsLA